|
�@�d�͑��A���s���u�n�����~��COCO�����^���v�́A1997�N11������u�o���邱�ƁA�g�߂Ȃ��Ƃ���܂��s�����悤�v�������t�ɁA�g�l�N�^�C��߃^�C�^���h��g�J�C�e�L�d�˒��^���h�A�g�}�C���E�}�C�G�R�o�b�O�^���h�A�X�ɂ́g���ƌv��h�ƁA���g�݂̕����L���A�e�\�����A������P�g�ɂ����Ē蒅�Ɍ����Ċ�����W�J���Ă��܂����B���̌��ʁA�������̒n�������ɑ���ӎ�������C�t�X�^�C���A���[�N�X�^�C���̉��P�Ɉ��̌��ʂ��グ�����̂Ǝ~�߂Ă��܂��B
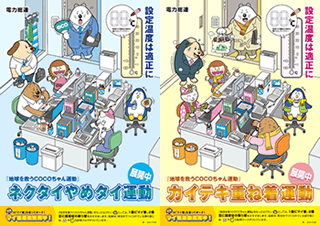
�@2017�N�x�̓d�͑��A�u�n�����~��COCO�����^���v�ɂ��Ă͍��ێЉ�̓��������܂��������ʃK�X�}���̈ꏕ�ɂȂ���u�s�[�N�J�b�g�^���v�����������d�_�I�Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�u�o���邱�ƁA�g�߂Ȃ��Ƃ���܂��s�����悤�v�������t�ɏ]���̎��g�݂��p���I�ɓW�J���Ă����܂��B
�@��̓I�Ȏ��g�݂ɂ��ẮA�ȉ��̒ʂ�Ƃ��܂��B |
| ���e |
���d�𑽂͂������Ċ��E�~���ɃI�t�B�X�E�ƒ�ɂ����āA��l�ЂƂ肪�G�R���ӎ����A�ʎ�1-1�`3�Ɋ�Â��A�d�͎��v�̃s�[�N�J�b�g�����H����B
�����{�ɂ������ẮA���{�̓d�͎������n������A�n�掖����l�����Ď��{������̂Ƃ���B |
| ���� |
���Ċ���7���`9���A�~����12���`3���Ƃ���B |
| �^���̓W�J |
���e�@���ʁ�
���e�@�ւ͊m���ɉ^�����W�J�����悤�A�H�v�E�������A���H���邱�ƂƂ���B
���@�֎��������p���āA���g�ݓ��e���L�����m����B |
���S�����A��
���A�����쐬������ނ�f�[�^�A�������B
���t�H�g�j���[�X�A�@�֎��Ŏ��g�݂����m����B |
���\�����A��
�������g���̎��g�݂�K�X�t�H���[����B
���A�����쐬������ނ�f�[�^�A���̎��m��z�z�B |
�������g����
���g�����S���Ɏ��m���A�Ƒ����܂߂Ċm���Ɏ��H�����悤�ɓw�߂�B |
| ���e |
���Ċ��̓m�[�l�N�^�C�A�~���͏d�˒��ȂNjC����̊����x�ɍ��킹�A�ߕ��̒��p���H�v���邱�Ƃɂ��A���x�̓K������}��A�s�[�N�J�b�g�A�ȃG�l���M�[�Ɋ�^����B
�����{�ɂ������ẮA�n������A�n�掖����l�����Ď��{����B |
| ���� |
���Ċ���5���`10�����A�~����11���`3�������d�_���{���ԂƂ���B
�i�A���G�R���C�t21�u�s�[�N�J�b�g�A�N�V�����v�̃G�R�X�^�C���̎��{���ԂƐ���������j |
| �^���̓W�J |
���e�@���ʁ�
���e�@�ւ͂���܂ł̎��g�݂܂��A�m���ɉ^�����W�J�����悤�A�H�v�E�������A���H���邱�ƂƂ���B�܂��A�E��ɂ����g�݂�����E��́A�ċG�́u�T�}�[�X�^�C���f�[�v�A�~�G�́u�J�W���A���f�[�v�Ƃ������j�������肷��Ȃǂ��āA�^�������H�ł�����Â���Ɏ��g��ł����B
���@�֎��������p���āA���g�ݓ��e���L�����m����B
�����Ԓ��͑g���f���ȂǂɃ|�X�^�[���f������B�܂��A���Ԓ��J�Â����莞�����ł��f���ɓw�߂�B |
���S�����A��
���e�\�����A�̗v���ɂ��A�^����W�J���邽�߂̃|�X�^�[�Ȃǂ̊�ނ�f�[�^�A�������B |
���\�����A��
�������g���̎��g�݂�K�X�t�H���[����B |
�������g����
�����Ǝ҂Ƌ��c�̏�A���������ɂ�������x�̓K�����ɓw�߂�B |
| ���e |
���X�[�p�[�E�R���r�j���̏����X���n�����W�܂��g�킸�A�}�C�G�R�o�b�N���g�p������A���ʂ̔��������̓��W�܂�f�邱�ƂŁA�S�~�̌��ʂɂ��ċp�G�l���M�[�ECO2�r�o�ʂ̒ጸ�Ɋ�^����B |
| �^���̓W�J |
���e�@���ʁ�
����������u�}�C�G�R�o�b�N�v���g�p����K��������悤�L����s���B |
���g��������
�����悵�āu�}�C�G�R�o�b�N�v�̎g�p�A�u���W�܂��f��v�����H���A������@���ʂ��đg������PR����B |
���S�g������
���Ƒ����܂߂Ď��H�ł���悤�A��������ƒ���ɂ����Ċ����ɂ��Č�荇���ȂǁA���ӎ������߂Ă������ƂƂ���B
���}�C�G�R�o�b�N�̌g�s�E���p |
| ���e |
���O�H����ٓ��w�����ɂ����āA���蔢�́u�g�p���Ȃ��v�A�u���Ȃ��v���^���̊�{�Ƃ��A�S�~�̌��ʂɂ��ċp�G�l���M�[�ECO2�r�o�ʂ̒ጸ��}��B�܂��A���蔢���g�p����ۂɂ́A�X�ѕۑS�̊ϓ_���琄������Ă��鍑�Y��(�ʎ�2�Q��)�𗘗p�������蔢���g�p����B |
| �^���̓W�J |
���e�@���ʁ�
����������u�}�C���v�g�s�̏K��������悤�L����s���B
���莞���⌤�C�Ȃǒ��H�����ꍇ�́A�Q���҂ցu�}�C���v�g�s���Ăт����A���蔢����Ȃ��悤�w�߂�B |
���g��������
�����悵�āu�}�C���v���g�s�A������@���ʂ��āA�g������PR����B |
���S�g������
���Ƒ����܂߂Ď��H���邱�ƂƂ���B
���}�C���̌g�s�E���p |
�� |
���@�� |
��̓I���g�� |
1 |
�G�A�R�� |
���x�ݒ���T���߂ɂ���i28�����ڈ��j�B |
2 |
��@�ŋ�C���z�����A�����I�ɃG�A�R�����g�p����B |
3 |
�g�p���ɔ���J�[�e���E�u���C���h��߂�B |
4 |
�t�B���^�[�����܂߂ɑ|������B |
5 |
�Ɩ� |
�d���̊Ԉ�����A�Ɠx�̒���������B |
6 |
���̂��܂߂ȑ|���Ŗ��邳���A�b�v����B |
7 |
�①�� |
���x�ݒ���T���߂ɂ���i���ɂ��Ȃ��j�B |
8 |
�J���Ă��鎞�Ԃ�Z�����A�]���ȊJ�͂��Ȃ��B |
9 |
�����l�ߍ��݂����Ȃ��悤�ɂ���B |
10 |
�M�����̂͗�܂��Ă�������B |
11 |
�e���r |
��ʂ̂��܂߂ȑ|���Ŗ��邳���A�b�v����B |
12 |
���ʂ͕s�K�v�ɑ傫�����Ȃ��B |
13 |
DVD��Q�[���@��̂����ςȂ��ɒ��ӂ���B |
14 |
���̑� |
�������֍��̉����E�֍��̉��x�ݒ���T���߂ɂ��A����Ȃ��Ƃ��ɂ͕ۉ��֍��̂ӂ���߂�B |
15 |
�d�C���ߗފ����@�͋ɗ͎g�p���Ȃ��B |
16 |
�d�����i���� |
�X�C�b�`�����܂߂ɐ�B |
17 |
�ȃG�l���ʂ̍������i�ւ̔���������A�ȃG�l���[�h��^�C�}�[�@�\�����p����B |
18 |
�G�߂ɂ���ĕK�v�Ȃ��@���A�g�p�p�x�̒Ⴂ�@��̓R���Z���g���܂��͎�d�����B |
19 |
�X�C�b�`�t���e�[�u���^�b�v�̊��p�ŁA�ҋ@�d�͂̍팸��S������B |
20 |
�����s��
�̍H�v |
�ƒ�ɂ����āA���Ƀs�[�N�J�b�g�����߂��鎞�ԑ�
�i13:00�`16:00�j�i���j�̓d�͎g�p���ɗ͗}����B |
21 |
�Ƒ������������ʼn߂����A����d�͂�}����B |
�����ԑтɂ��ẮA���{�̓d�͎�����ɂ���Č������\��������B |
�� |
���@�� |
�@�� |
1 |
�G�A�R�� |
�g�[�̉��x�ݒ���T���߂ɂ���i20�����ڈ��j�B |
2 |
�g�p���ɔ���J�[�e���E�u���C���h��߂�B |
3 |
�t�B���^�[�����܂߂ɑ|������B |
4 |
�����Ȃnj����ǂ������g�[��A�Ζ��^�K�X�X�g�[�u�A������ۂȂǓd�͂�����Ȃ����̊��p��S������B |
5 |
�d�˒���G�����ȂǁA�ߗނ̍H�v��S������B |
6 |
�Ɩ� |
�d���̊Ԉ�����A�Ɠx�̒���������B |
7 |
���̂��܂߂ȑ|���Ŗ��邳���A�b�v����B |
8 |
�①�� |
���x�ݒ���T���߂ɂ���i��ɐݒ肷��j�B |
9 |
�J���Ă��鎞�Ԃ�Z�����A�]���ȊJ�͂��Ȃ��B |
10 |
�����l�ߍ��݂����Ȃ��悤�ɂ���B |
11 |
�e���r |
��ʂ̂��܂߂ȑ|���Ŗ��邳���A�b�v����B |
12 |
DVD��Q�[���@��̂����ςȂ��ɒ��ӂ���B |
13 |
���̑� |
�������֍��̉����E�֍��̉��x�ݒ���T���߂ɂ��A����Ȃ��Ƃ��ɂ͕ۉ��֍��̂ӂ���߂�B |
14 |
���т͑����ɂ܂Ƃߐ��������A�ۉ��@�\�͎g�p���Ȃ��B |
15 |
�d�C���ߗފ����@�͋ɗ͎g�p���Ȃ��B |
16 |
�d�����i���� |
�X�C�b�`�����܂߂ɐ�B |
17 |
�ȃG�l���ʂ̍������i�ւ̔���������A�ȃG�l���[�h��^�C�}�[�@�\�����p����B |
18 |
�G�߂ɂ���ĕK�v�Ȃ��@���A�g�p�p�x�̒Ⴂ�@��̓R���Z���g���܂��͎�d�����B |
19 |
�X�C�b�`�t���e�[�u���^�b�v�̊��p�ŁA�ҋ@�d�͂̍팸��S������B |
20 |
�����s���̍H�v |
�ƒ�ɂ����āA���Ƀs�[�N�J�b�g�����߂��鎞�ԑ�
�i18:00�ȍ~�j�i���j�̓d�͎g�p���ɗ͗}����B |
21 |
�Ƒ������������ʼn߂����A����d�͂�}����B |
�����ԑтɂ��ẮA���{�̓d�͎�����ɂ���Č������\��������B |
�� |
���@�� |
�@�� |
1 |
�� |
�N�[���r�Y�A�E�H�[���r�Y�i���j�����H���A���x�ݒ���T���߂ɂ���i�Ċ��F28���A�~���F20�����ڈ��j�B |
2 |
����J�[�e���E�u���C���h�̎g�p�A��@�̊��p�Ȃǂɂ��̌��������͂���B |
3 |
�Ɩ� |
���x�݂▢�g�p���̎������E��c���E�g�C���Ȃǂ́A���܂߂ȏ�����S������B |
4 |
LED�d���ւ̔���������A�\�Ȕ͈͂œd���̐��̊Ԉ������s���B |
5 |
�①��
�����̔��@ |
���x�ݒ���T���߂ɂ���i���ɂ��Ȃ��j�B |
6 |
���̗]���ȊJ�������A�J���Ԃ��Z������B |
7 |
�g�C�� |
�������֍��̎g�p��A���x�ݒ���T���߂ɂ���B |
8 |
�g�p��͕K���ۉ��֍��̂ӂ���߂�B |
9 |
OA�@�� |
�ȃG�l���[�h��ݒ肵�A���g�p���ɂ͓d�������܂߂ɐ�B |
10 |
�v�����^�[���̋��L�@��̎g�p�䐔���A�K�v�Œ���ɂ���B |
11 |
�ŏI�ގ��҂͋��L�@��̎�d������đގЂ���B |
12 |
�G���x�[�^�[ |
�K�i�̗��p�𐄏����A�G���x�[�^�[��G�X�J���[�^�[�̎g�p���Œ���ɐ�������B |
���N�[���r�Y�F2017�N�x�����������X�[�p�[�N�[���r�Y�Ƃ���5���`10���ɓW�J
�@�E�H�[���r�Y�F11���`3�� |
�@���Y�ނ𗘗p���邱�Ƃɂ�莑�����R�ɊҌ�����A�X�ѕۑS�E�����ɂȂ���ACO2�̐X�ыz�����i�ނ��Ƃ���A���̗��p����������Ă��܂��B
�@���Y�ނ��g�p�������i�Ƃ��Č�������ɂ́A�ȉ��̃��S�}�[�N���Q�l�ɂ��ĉ������B |

