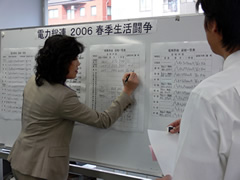|
 |
| ○「電力総連2006春季生活闘争のまとめ」を確認 (2006.7.27) |
電力総連は、7月27日(木)第5回三役会議にて、「電力総連 2006 春季生活闘争のまとめ」を確認した。
電力関連産業を取り巻く厳しい情勢の中、加盟組合は厳しい交渉を余儀なくされながらも、全体的には上向き基調の解決に至っている。
なお、会議における確認事項の概要については以下のとおり。 |
| 電力総連2006春季生活闘争のまとめ(要旨) |
| I はじめに |
電力総連 2006春季生活闘争は、電力関連産業を取り巻く環境が依然として厳しい状況下での取り組みとなったが、経済社会の明るい情勢などを前向きに捉え、組合員とその家族の生活の安心・安定、並びに働きがい・活力を確保する観点から、雇用安定と基本的な労働条件を守ることを重要課題に置き、電力総連が一体となって労働条件の維持・向上に取り組むこととした。
加盟組合は厳しく難しい交渉を余儀なくされながらも、構成総連と連携を図りながら精一杯の交渉を展開し、現時点 (7月4日現在)の集約結果では、バラツキはあるものの概ね昨年実績を上回る水準の獲得、労働条件の充実や改善など、全体的には上向き基調の中で、要求217単組のうち209単組が解決に至っている。 |
| II 今次交渉を巡る情勢について |
景気は、原油価格の動向など先行きの不安要因はあったが、踊り場を脱し回復基調にあり、企業業績はバラツキがありながらも4年連続の増益見通しであった。また、雇用情勢は改善が進んでいる状況にあったが、雇用・就労形態の多様化や労働者の就労意識が変化する中で、働き方や労働時間のあり方への課題認識が深まっていた。
一方、労働者の生活改善は遅れ、所得や働き方の二極化が顕著になる中で、社会保障などの負担増・給付減が懸念されるとともに、少子高齢化の急速な進展、団塊世代の大量退職などにより経済社会が構造的に変化する中で、直面する問題は深刻で課題山積という現状にあった。
電力関連産業を取り巻く経営環境は、厳しさを抜け出すことが難しい状況下にあり、各企業は生き残りをかけて、経営基盤や価格競争力の強化を図るため、効率化・コスト削減に邁進していた。また、電力各社は経営資源の再配分や企業再編などによりグループ経営の強化を進めていた。一方、職場では質・量とも労働負荷が増している中で、経営施策に懸命に取り組んでおり、雇用安定や処遇改善に対する希求が高まっていた。
連合は「生活防衛から生活向上」「下支えから底上げ」と従来の春季生活闘争の取り組み基調を変えるとともに、「格差拡大阻止、二極化の是正」を焦点にあて、5年ぶりに賃金改善に取り組み、他産別でも好調さを取り戻した国内景気や企業業績の大幅改善などを背景に、製造業の大手組合が賃金改善に前向きに取り組んだこともあり、労働界全体として久しぶりの賃上げ中心の春季生活闘争となった。
日本経団連は、企業の業績回復を担った「普通の人」の重要性を認め、行き過ぎた成果主義に警鐘を鳴らして、マクロ的には労働側への分配に一定の理解を示したが、グローバル化による国際競争が激化し、先行き不透明な経営環境にあって、賃上げは支払能力と総額人件費管理の観点から個別労使で決めることを原則とし、横並びの賃金水準引き上げはありえず、短期的な業績は賞与・一時金に反映するとした基本方針を示した。 |
| III 各種会議等の開催について |
○第1回労働政策委員会 ( 平成17 年10月19 日 ) :春闘方針の策定に向けた論議
○第1回三役会議 ( 平 成17年10月27 日 ) :春闘方針の策定に向けての経過報告
○第2回労働政策委員会 ( 平成17年11月17 日 ) :春闘方針 ( 案 ) の論議
○第7回執行委員会 ( 平成17年12月1日 ) :春闘方針 ( 案 ) の確認
○第2回三役会議 ( 平成17 年12月6 日 ) :春闘方針 ( 案 ) の確認
○第1回中央委員会 ( 平成17 年12月15 日 ) :春闘方針の決定
○第1回中央交渉推進委員会 ( 平 成18年2月15 日 ) :進め方 ( その1 ) の確認
○第2回中央交渉推進委員会 ( 平成18 年3月7 日 ) :進め方 ( その2 ) の確認
○第1回交渉連絡責任者会議 ( 平成18 年3月30 日 ) :交渉状況の意見交換
○第3回交渉推進委員会 ( 平成18 年4月7 日 ) :進め方 ( その3 ) の確認
○第4回交渉推進委員会 ( 平成18 年5月19 日 ) :早期解決に向けた進め方の確認 |
| IV 評価と課題について |
| 1 妥結内容ついて |
| (1) 雇用安定の取り組み |
| |
雇用安定に関する労使の共通認識を醸成する取り組みを行った加盟組合は、74単組 (昨年は67単組)と昨年より僅かながら増加した。近年の継続した取り組みにより労使の共通認識は醸成されているものと判断しているが、電力関連産業の先行きは依然として不透明な中で、グループ企業の再編が進められるなどから、直接的な雇用喪失に限らず雇用不安を一掃できる状況でないとの認識に立てば、引き続き、雇用安定を最優先に置き、労働条件の維持・向上に向けて取り組まなければならないと考える。
また、 構成総連を中心としたグループ労使懇談会などの設置・充実については、グループ経営施策が強化される状況にあって、その必要性は益々高まっていると判断される。しかし、グループ労使関係を強め、その機能を充実させることは一朝一夕には難しいため、引き続き、要求の趣旨に沿った地道な取り組みを行っていく必要があると考える。 |
| (2) 労働協約に関する取り組み |
| |
【 労働協約の完全締結及び整備・充実】
労働協約が未締結の17単組のうち2単組が締結、4単組が締結に向けて協議中、11単組は未だ締結に至っていない現状にある。また、労働協約の整備・充実を図った加盟組合は107単組であり、着実に取り組みの成果を上げていることは十分に評価できる。
労働協約については、雇用の確保や労働条件の維持を担保するだけでなく、労使関係安定の絆としての役割・機能を有している。一方、労働法の改正、雇用・就労形態や就業意識の多様化など、これまで働き方を支えてきた要因が大きく変化していることから、その変化や職場実態などに対応できる協約内容の整備が重要になってきている。更に、労働者の基本的な権利と労働条件の最低保障を定めた労働基準法などの労働法の機能が低下する中にあって、具体的な労働条件や権利の保障について成文化した労働協約の機能と役割の重要性は益々増していると考える。この認識に立って、加盟組合の完全締結はもちろんのこと、定期的に労働協約の点検を行い交渉の強化を図りながら、整備・充実に取り組んでいく必要があると考える。 |
| |
【労使協議会の設置・充実】
労使協議会が設置されていない21単組のうち4単組で成果を上げるなど、年々徐々にではあるが労使協議会の設置・充実が図れている。一方、労使協議会は設置されているが、その運営についてルール化されていない加盟組合もあることから、引き続き、労使協議会の目的と役割を認識し、その充実に向けて取り組んでいく必要があると考える。
近年、労働基準法などの労働法については、社会情勢や構造改革に伴った使用者側の意向に沿った見直しが進められているが、法改正の内容をみると、職場での取り扱いについては労使自治に委ねられる傾向が強まっている。また、経営環境が激変する中で、各企業の置かれた状況は様々であり、それぞれの事情は異なっているため、労働条件を画一的に改善していくことは難しくなってきている。このような状況を踏まえ、雇用を安定的に確保し、労働条件を維持・向上させていくためには、個別の労使関係が益々重要になっており、日頃から労使が情報を共有化しながら、労働組合の経営チェック機能を働かせ、経営側に対して現場の声を反映させることが必要である。この認識に立って、機能的かつ効果的な労使協議会の運営が図られるよう、その充実に取り組んでいく必要があると考える。 |
| |
【定年退職者継続雇用制度の新設・充実】
各加盟組合では、本年4月から施行された高年齢者雇用安定法に沿った対応が行われたものの、多くの加盟組合では65歳までの制度確立に至っていないものと判断される。
将来、65歳までの勤労社会が到来することになるが、その過程において、団塊世代の退職による影響などマクロ的な課題、個別企業内での様々な課題が顕在化することが想定される。特に、個別企業においては、仕事と処遇のバランス、働く場所の確保など対応すべき事項も山積していることから、引き続き、職場実態や現行制度の運営状況などを把握しながら、法の趣旨を踏まえ、職場で働く全ての人たちが、生き生きと働ける条件整備に努めて行く必要があると考える。
今次春季生活闘争において、初めて退職一時金制度の確立・充実に取り組み、1単組が制度を確立し、9単組が制度の充実を図ることができた。
国の財政が逼迫し、社会保障制度に大きな期待ができない中で、今後、消費税率の引き上げなども想定され、生活者への負担は増すばかりの状況にある。このような中で、退職後も安心できる生活を送るためには、退職一時金の果たす役割は重要との認識から、引き続き、社会水準と比較しても遜色のない退職一時金制度の確立・充実に向けて取り組んでいく必要があると考える。 |
| |
【仕事と生活の調和がはかれる環境の整備】
仕事と生活の調和がはかれる環境整備に取り組んだ92単組のうち、成果を上げた加盟組合は、育児・介護に係わる制度の充実で25単組、次世代法に基づく企業行動計画のフォローで19単組、年次有給休暇の取得促進や時間外労働時間の削減で49単組という結果になった。特に、電力総連内においては、職場環境が厳しさを増す中で、年次有給休暇の取得日数が減少し、時間外労働時間が増加する傾向にある実態を考えれば、49単組で成果を上げたことは評価できる。しかしながら、全体的には年間総実労働時間は増加傾向にあることから、今後とも職場実態を把握しながら、年間総実労働時間の縮減に取り組んでいかなければならない。
今後、職場環境は益々厳しくなることが想定されるが、社会的な責務を果たすためにも、取り組みの趣旨について経営側や組合員に対する認識の醸成に努めながら、引き続き、育児・介護休業制度の整備・充実、制度を活用し易い運用面の改善に向けて取り組んでいかなければならないと考える。
また、仕事と生活の調和がはかれる環境の整備については、労働時間や働き方に対する社会的な関心が高まる中で、賃金や賞与・一時金のみならず春季生活闘争の重要な柱になりつつある。
一方、厚生労働省は今後の労働時間制度のあり方の検討を進めており、その動向なども注視しながら、労働時間や働き方について電力総連の考え方を整理して、具体的な取り組みについて論議・検討を進める必要があると考える。 |
| |
【災害補償制度等の充実】
災害補償制度の充実に取り組んだ31単組のうち13単組が現行水準に100万円から1500万円の上積みを図るとともに、そのうち6単組が方針の3 ,500万円以上の制度確立を果たすことができ、例年このように、若干ではあるが制度の充実に向けて成果を上げている。今後も これらの成果を踏まえつつ、働く者が万一業務上災害に見舞われた場合、家族の生活補償を確保する上で、災害補償制度は転ばぬ先の杖として極めて重要であるとの考えに立って、引き続き、社会水準を参考にしながら、制度確立、更なる充実に向けて取り組む必要があると考える。
また、労働者災害補償保険法の一部改正について、43単組が労働協約の締結や労使間の確認等を行った。一方、104単組が未対応であったが、通勤災害の範囲を示した関係省令が施行されたことから、加盟組合にその内容を周知しつつ、それぞれの実態を踏まえた対応を促していきたいと考える。 |
| (3) 賃金改定の取り組み |
| |
賃金カーブ維持分確保の要求を行った97単組 ( 定昇制度等があることから賃金改定の要求を行わなかった組合もあり ) のうち73単組が確保することができた。その内訳は、45単組が賃金表の維持、15単組が1歳1年間差又は所定内賃金の2%の要求を行い獲得したものである。
賃金改定での妥結結果については、個別比較可能な加盟組合による昨年比較を行うと、平均方式では全体の106単組の加重平均で3 , 164円 ( 昨年比+303円 ) 、300人未満の78単組の加重平均で2 , 894円 ( 昨年比+81円 ) という結果になった。また、個別方式 ( 高卒30歳 , 勤続12年 ) では、22単組の加重平均で2 , 814円 ( 昨年比▲101円 ) 、300人未満の14単組の加重平均で2 , 327円 ( 昨年比▲38円 ) という結果になり、全体的にはほぼ昨年並みの賃上げ水準を獲得した。
次に、賃上げ率において、連合大の集約では1 . 8% ( 300人未満の中小組合では1 . 67% ) を超えているにも拘わらず、電力総連大では1 . 2 % にも満たない結果となっており近年この傾向が続いている。一般的に賃金カーブは下方傾向にあるが、賃金構造基本統計調査から算出される賃金カーブ維持分が中小規模でも2%程度であることを考えれば、このままでは、電力総連の賃金水準の低下のみならず、社会水準との格差拡大も懸念される。このため、賃金改定の方針策定にあたっては、社会水準も踏まえた検討を行う必要がある。
他産別では、横並びで賃金水準を底上げする市場横断的なベアはもはやあり得ないとする経営側の堅固な姿勢を踏まえ、一律的な賃金引き上げの「ベア」から月例賃金における多様な改善である「賃金改善」という考え方により賃金改定が取り組まれた。グローバル化する競争環境などを背景に厳しい交渉が展開され、結果的に多くの組合で有額回答を勝ち得たものの、年功的賃金制度の見直しや成果主義型賃金の導入等によりここ数年で賃金制度が大きく変わってきている中で、個別賃金水準や配分のあり方などが課題として表面化した。
また、「賃金改善」については、各産別で考え方に差違があっただけでなく、各組合においてもそれぞれの事情により異なった取り扱いがされたこともあり、「賃上げ」を画一的に捉えることができなかった。加えて、同一産業の業種・業態でも業績のバラツキが常態化する中で、結果して横並び的な賃金引き上げが難しくなるなど、春闘の賃金改定は新たな局面を迎えることになったと判断される。電力総連大でも、賃金を巡る状況変化の中で、成果を重視した人事・賃金制度などの見直しが行われており、今次春季生活闘争で表面化した他産別の課題等については、電力総連の課題としても受け止め、どのように対応していくか検討し整理する必要がある。
賃金制度の有無、賃金実態の把握の有無により賃上げ結果に二極化の傾向があることから、賃金改定交渉を臨むにあたっては、通年的な活動の中で、賃金の実態把握・分析や改善点の抽出を行っておくことが必要である。その上で、賃金カーブの是正、賃金制度上の各種課題への対応などに加え、賃金制度の確立に向けて取り組むことが重要である。この認識のもと、取り組みの指針となる現行の電力総連賃金政策については、賃金制度を巡る状況変化などを適切に捉えて見直しを図っていく必要があると考える。 |
| (4) 賞与・一時金の取り組み |
| |
賞与・一時金の交渉については、生活給的部分である「年間4 .0ヵ月」に拘り、適正な成果を求めて粘り強い交渉を展開した結果、夏季分の集約において、個別比較可能な191単組の加重平均が753,594円、2.14ヵ月(前年比+8,023円、+0.01ヵ月)と額・率とも昨年実績を上回ることができた。
また、組合員300人未満の中小組合114単組の加重平均が573 ,734円、2.05ヵ月(前年比+15,685円、+0.03ヵ月)と率・額とも昨年実績を上回る結果となり、全体的にはバラツキはあるものの概ね昨年を上回る賞与水準を獲得した。電力総連のクリア水準である「年間4.0ヵ月」を上回った加盟組合は82単組(昨年比+17単組)となった。
この結果は、厳しい経営環境下での交渉であったことを勘案すると、労働界全体の前向きな基調を背景に、各加盟組合が電力総連方針に沿った精一杯の交渉を展開した賜物であると判断する。また、経営施策に懸命な努力を傾注している組合員の期待に対する経営側のギリギリの決断であったと受け止めるとともに、生活給的部分である年間4 .0ヵ月は最低限確保するとした電力総連方針に対する経営側の認識が徐々にではあるが深まっていると推察される。
近年、社会的には短期的な企業業績は賞与・一時金に反映する考え方が定着し、業績連動方式を導入する組合も増加する傾向にある。しかし、賞与・一時金は生活を支える重要な柱であると考えれば、企業業績に偏った水準決定では年間収入が大きく振れ、生活の安定性が損なわれることが懸念される。この認識を踏まえ、月例賃金の水準引き上げを重視しつつ、引き続き、賞与・一時金については、生活給的部分である「年間4 .0ヵ月」の最低水準の確保に拘り、その上で、組合員の努力に報いることができる適正な成果の配分を求めていくこととする。 |
| (5) その他の取り組み |
| |
【適正な労働時間の充実に向けた取り組み】
要求の趣旨に沿って116単組が取り組み、協定の締結、過重労働による健康障害防止などの成果を上げた。一方、年々春季生活闘争において取り組む加盟組合が減少しているが、これは徐々にではあるが、労働時間の適正管理に対する労使の共通認識のもと、通年の活動において取り組みが展開されているからであると判断する。
また、本年4月から労働時間等設定改善法が施行され、その指針が示されたが、取り組みにあたっては労働時間の適正な管理が不可欠であるとともに、常に労使の認識を喚起していかねばならない。その認識に立って、労働時間に関するアンケート調査の結果を踏まえつつ、今後も適正な労働時間管理の充実に向けて継続的かつ地道に取り組んでいく必要があると考える。 |
| |
【パート労働者等全従業員を視野に入れた取り組み】
パート労働者等がいないなどの理由から、8単組の取り組みとなったが、6単組が複数項目で成果を上げ、派遣労働者を受け入れる際の労使間ルールの確立には4単組が取り組み、2単組が成果を上げた。
一方、社会的には パート労働者等が増加の一途を辿る中で、雇用・就労形態の多様化による労働者間の格差拡大など二極化が進展しており、パート労働者等の均等・均衡待遇の実現は社会的課題として認識しなければならない。これらの情勢を踏まえつつ、連合のパート共闘連絡会での論議などを参考にしながら、パート労働者等の待遇改善に向けて取り組みを進めていく必要があると考える。 |
| |
【政策制度要求への取り組み】
働く者が将来に亘って安心・安定した生活を送るためには、社会保障制度のみならず社会的なセーフティネットの構築や公正・公平な社会の実現が求められている。しかし、産別・単組の組織力だけでは実現していくことは難しく、真に国民・働く者の視点に立った社会を目指すためには、今後とも連合の政策制度要求への取り組みに対し、 連合の中核産別としての役割を果すべく 積極的に参画していくことが必要であると考える。 |
| 2 進め方について |
| (1) 事前準備 |
| |
労働条件・労働環境の改善・向上を図るためには、それぞれの事情を踏まえた課題に気付き、自らで解決していく取り組みが必要である。構成総連の評価や労働組合の機能を高めるなどの趣旨に立てば、来期も引き続き労働環境点検活動に取り組んでいくことが望ましいと判断する。その認識に立って、構成総連や加盟組合からのチェック項目などに対する意見を踏まえ、点検活動の内容を精査し、春季生活闘争方針の関連資料などとの整合性や重複解消を図りつつ、実施時期の早期化を念頭に次期実施に向けて検討を進める。 |
| (2) 要求書等の提出 |
| |
要求書の提出は ,昨年に引き続き、統一要求日を設定して電力総連加盟組合185単組(昨年186単組)が一斉に要求を行った。また、3月末までに要求書を提出した加盟組合は29単組(昨年29単組)と昨年並みの提出状況となったが、構成総連では統一要求に向けて加盟組合の認識を促し調整等を行うとともに、加盟組合は要求書等の提出に向け早期に準備を進めるなど、統一要求の趣旨に対する認識は深まっていると考える。 |
| (3) 交渉の進め方 |
| |
統一交渉ゾーンの設定については、加盟組合の交渉強化・促進に効果があったと概ね肯定的な評価を得ている。これは交渉ゾーンの設定に加え、構成総連独自の様々な支援強化の取り組みが、構成総連と加盟組合の一体感を醸成しつつ、加盟組合の交渉を後押ししたからであると推察される。また、経営側の交渉に対する前向きな姿勢を促し、個別労使における慣行的な交渉の進め方を変えていく契機になったものと考える。
ただし、今年が初めての試みであり、各加盟組合の妥結日が昨年並に推移したことから判断すると、加盟組合が統一交渉ゾーンの設定に十分対応できなかったことも推察されることから、来期に向けて加盟組合の早期解決の促進と交渉強化に繋がる統一交渉ゾーンや統一解決ゾーンのあり方などについて論議・検討する必要があると考える。 |
| (4) その他 |
| |
連合の中小共闘は3年目の取り組みとなり、その効果を発揮する中で、電力総連も連合の中核産別としての役割を果たすべく可能な限り参画し、一定の役割は果たせたものと考える。しかし、電力総連では中小共闘の効果を加盟組合の交渉へ波及させていく取り組みになっていないことから、今後、中小共闘の波及効果が得られる進め方については検討する必要があると考える。 |
| V 最後に |
今次の春季生活闘争は、厳しい環境下での取り組みとなったが、加盟組合の真摯かつ粘り強い交渉により一定の成果を上げることができた。一方、働く者を取り巻く情勢や環境は大きく変化する中で、春季生活闘争も従来の枠組みで捉えることが難しくなるとともに、多くの課題が顕在化するなど新たな局面を迎えている。
電力関連産業は依然厳しい経営環境下にあるが、雇用を守り総合的労働条件の維持・向上を図るため、 2007春季生活闘争に向けては、賃金・労協専門委員会において電力総連賃金政策の見直し、労働時間や働き方に対する電力総連の考え方の整理などを行いながら、以上の評価と課題を踏まえ、課題整理とその対応について論議・検討を進めていきたいと考える。 |
| 以 上 |
|

第3回中央交渉推進委員会にて
「電力総連2006春季生活闘争 進め方(その3)」を決定! (2006.4.7) |
電力総連は、4月7日(金)第3回中央交渉推進委員会を開催し、「電力総連 2006 春季生活闘争 進め方(その3)」を決定した。
現在、電力総連大における妥結単組は、77単組(平成 18 年 4 月 4 日現在)であり、今後の交渉においては、本指針を踏まえ、早期解決を念頭に取り組みを進めていただきたい。 |
| 電力総連2006春季生活闘争 進め方(その3) |
電力総連 2006春季生活闘争については、第2回中央交渉推進委員会(3月7日開催)で確認した進め方(その2)をもとに、4月4日現在、214組合が要求書を提出し、先行する各部会の全組合を含む77組合が解決に至っています。
先行する各組合の交渉は、経営環境の厳しさや先行きの不透明さから、厳しく難しい展開を余儀なくされながらも、精一杯の努力により経営側の強い主張を押し返し、概ね昨年実績を上回る賞与水準を獲得するなど、電力総連 2006春季生活闘争は上向き基調の中で推移しています。
後続する各組合は、それぞれの事情はありますが、 先行する組合および連合の中小共闘の妥結状況を前向きに捉え、電力総連・構成総連と連携を図りながら、以下の進め方により 要求趣旨の実現に向けて今後の交渉に臨むこととします。 |
| l 進め方について |
| (交渉の進め方) |
| 1 |
労働協約 |
| |
労働協約については、要求の趣旨に沿って一歩でも前進が図れるよう交渉を強化することとします。また、今次の交渉期間での実現が難しいと判断される要求項目については、今次の話合い・協議の経緯を踏まえ、今後の実現に向けた取り組みに繋げていくこととします。 |
| 2 |
賃金 |
| |
賃金改定については、賃金カーブ維持分 (1歳1年間差の算定が困難な組合は所定内賃金の2%)を最低限確保できるよう、最後まで粘り強い交渉を進めることとします。更に、個別賃金水準の上積みを要求している組合は、電力総連の目標水準を指標にしつつ、連合の中小共闘の妥結集約結果などを活かして、要求に沿った賃金水準の引き上げを目指して追い上げを図っていくこととします。
また、今次交渉で賃金制度の確立が難しいと判断される場合は、今後の制度確立に向けての話し合い・協議について、会社に対応を求めていくこととします。 |
| 3 |
賞与・一時金 |
| |
賞与・一時金については、生活給的部分である「年間4 .0ヶ月」を最低限の水準として、その確保を図るとともに、更なる水準の上積みに向けて、最後まで粘り強い交渉を進めることとします。
ただし、「年間4 .0ヶ月」の確保が難しい場合は、先行した組合が、概ね昨年を上回る水準を獲得したことを前向きに捉え、 組合員の努力と貢献に報いるとともに、職場の意欲・活力の向上に繋げるためにも、少なくとも昨年の妥結水準を上回れるよう追い上げを図ることとします。 |
| 4 |
そ の 他 |
| |
その他の要求項目については、要求の趣旨に沿った解決が図れるよう交渉の追い込みを図った上で、一定の整理に向けて見極めを行いつつ、 今次の話し合い・協議の経緯を踏まえ、今後の実現に向けた取り組みに繋げていくこととします。 |
| (要求書の提出) |
| |
企業業績の判断等の事情により要求書提出に至っていない組合は、引き続き、経営状況等について会社側と認識の共有化を行い、構成総連と連携を図りながら要求方針の交渉日程に沿った解決が図れるよう要求書提出に向けて努力することとします。 |
| ll 日程について |
| 1 |
解決時期 |
| |
電力総連の加盟組合は、第2回中央交渉推進委員会で確認した「進め方 ( その2 ) 」を踏まえ、構成総連と連携を図り統一交渉ゾーンを活かしながら、自力・自決を基本原則として前年実績よりも前倒しを念頭に置き、4月中の解決を目指して追い上げを図ることとします。
ただし、会社回答に納得し難い場合は、早期解決を念頭に置きつつも、当初日程に拘ることなく、会社側の誠意ある回答を引き出すべく、更に交渉を強化することとします。 |
| 2 |
会議開催 |
| |
電力総連全体の交渉状況を見極めながら、交渉促進への対応が必要と判断される場合は、その後の進め方について構成総連・加盟組合の一体的取り組みを図るべく、中央交渉推進委員会の開催を考慮することとします。 |
| |
以 上 |
|

○電力総連2006春季生活闘争
「検集部会」全組合が妥結 (2006.3.30) |
| 電力総連 2006 春季生活闘争における検集部会の交渉は、 2 月 23 日の一斉要求以降、各組合が精力的な交渉を重ね、 3 月 30 日までに全ての組合が妥結に至った。賞与の妥結内容は以下のとおり。 |
| |
賃金改定 |
賞 与 |
妥結日時 |
| 夏季分 |
冬季分 |
| 北海道 |
検針 |
363 円( 0.12 %) |
445,100 円 |
445,800 円 |
3/23
14:15 |
| 集金 |
1,497 円( 0.44 %) |
599,500 円 |
601,400 円 |
| 東北 |
全職 |
205 円( 0.15 %) |
399,700 円 |
395,900 円 |
3/25
17:15 |
| 北陸 |
検針 |
2,045 円 (0.68 %) |
459,100 円 |
457,900 円 |
3/29
19:10 |
| 集金 |
2,285 円 (0.68 %) |
512,300 円 |
511,600 円 |
| 東京 |
検針 |
790 円( 0.29 %) |
412,500 円 |
415,500 円 |
3/16
19:10 |
| 集金 |
500 円( 0.14 %) |
749,900 円 |
755,800 円 |
| 中部 |
検針 |
改定なし |
407,600 円 |
409,400 円 |
3/16
21:50 |
| 嘱託 |
改定なし |
737,900 円 |
741,000 円 |
| 中国 |
検針 |
改定なし |
469,800 円 |
469,800 円 |
3/27
16:20 |
| 集金 |
改定なし |
584,700 円 |
584,700 円 |
| 四国 |
検針 |
2,082 円( 0.77 %) |
453,400 円 |
457,100 円 |
3/24
17:05 |
| 集金 |
1,786 円( 0.54 % ) |
589,100 円 |
592,500 円 |
| 九州 |
検針 |
-5,640 円 (-2.0 %) |
498,750 円 |
504,750 円 |
3/30
12:30 |
| 集金 |
-15,290 円 (-3.6 %) |
749,450 円 |
758,500 円 |
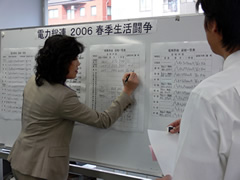

○電力総連2006春季生活闘争
「電工部会」全組合が妥結 (2006.3.29) |
| 電力総連 2006 春季生活闘争における電工部会の交渉は、 2 月 23 日の一斉要求以降、鋭意交渉の結果、 3 月 24 日から 3 月 29 日にかけて、全ての組合が妥結に至った。賞与の妥結内容は以下のとおり。 |
| |
賃 金 |
賞 与
(夏季分) |
妥結日時 |
| 北海電工 |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 95,000 円 |
3/27 21:10 |
| ユアテック |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 160,000 円 |
3/24 16:50 |
| 関電工 |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 156,000 円 |
3/24 9:00 |
| 北陸電工 |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 97,000 円 |
3/24 19:00 |
| トーエネック |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 126,000 円 |
3/24 17:10 |
| シーテック |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 152,500 円 |
3/24 17:45 |
| きんでん |
定昇の確保 |
業績連動方式 |
3/24 12:30
( 労協のみ) |
| 中電工 |
2,200 円 (0.98 % )
(高卒30歳勤続12年個別) |
1.5 ヵ月+ 70,000 円 |
3/24 19:00 |
| 四電工 |
4,300 円 (1.43 % )
(組合員平均) |
1.5 ヵ月+ 150,000 円 |
3/29 17:15 |
| 九電工 |
定昇の確保 |
1.5 ヵ月+ 82,000 円 |
3/28 18:15 |

○電力総連2006春季生活闘争
「電保部会」全組合が妥結 (2006.3.23) |
| 電力総連 2006 春季生活闘争における電保部会の交渉は、 2 月 23 日、一斉に要求を行い、 1 ヶ月に亘る交渉努力の結果、 3 月 23 日に全ての組合が妥結に至った。賞与の妥結内容は以下のとおり。 |
| |
賃 金 |
賞 与
(夏季分) |
妥結日時 |
| 北海道 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 303,400 円 |
3/23 18:10 |
| 東北 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 274,800 円 |
3/23 18:00 |
| 関東 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 319,800 円 |
3/23 15:30 |
| 中部 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 325,000 円 |
3/23 17:10 |
| 北陸 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 250,000 円 |
3/23 18:10 |
| 関西 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 319,000 円 |
3/23 16:45 |
| 中国 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 273,400 円 |
3/23 17:00 |
| 四国 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 266,000 円 |
3/23 17:00 |
| 九州 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 234,000 円 |
3/23 17:00 |
| 沖縄 |
賃金カーブ維持 |
1.5ヵ月 + 154,015 円 |
3/23 17:00 |

○電力総連2006春季生活闘争
「電力部会」全組合が妥結(2006.3.20) |
| 電力総連 2006 春季生活闘争における電力部会の交渉は、 2 月 23 日の一斉要求以降、各組合が粘り強く精力的な交渉を展開してきた結果、 3 月 20 日までに全ての組合が妥結に至った。賞与の妥結内容は以下のとおり。 |
| |
賞 与 |
妥結日時 |
| 夏 季 分 |
冬 季 分 |
(年間総額) |
| ほくでんユニオン |
1.5ヵ月+ 254,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,726,000円 |
3/16 16:50 |
| 東北 |
1.5ヵ月+ 265,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,723,000円 |
3/17 0:25 |
| 東京 |
1.5ヵ月+ 262,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,726,000円 |
3/16 11:40 |
| 中部 |
1.5ヵ月+ 293,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,792,000円 |
3/16 11:50 |
| 北陸 |
1.5ヵ月+ 262,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,723,000円 |
3/16 16:50 |
| 関西 |
1.5ヵ月+ 262,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,723,000円 |
3/16 12:50 |
| 中国電力ユニオン |
1.5ヵ月+ 262,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,726,000円 |
3/16 15:45 |
| 四国 |
1.5ヵ月+ 285,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,762,000円 |
3/16 14:50 |
| 新九州 |
1.5ヵ月+ 251,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,729,000円 |
3/16 15:15 |
| 原電 |
1.5ヵ月+ 226,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,501,000円 |
3/16 13:40 |
| 電発 |
H17年〜H19年の間、業績連動による賞与決定方式を採用。最低保証月数4ヶ月 |
| 沖縄 |
1.5ヵ月+ 263,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,545,000円 |
3/20 23:35 |
| 原燃 |
1.5ヵ月+ 161,000 円 |
夏季分に準ずる |
1,173,000円 |
3/17 0:50 |

○電力総連2006春季生活闘争
「第2回中央交渉推進委員会」を開催(2006.3.7) |
電力総連は、 3 月7日(火)第 2 回中央交渉推進委員会を開催し、「電力総連 2006 春季生活闘争 進め方(その2)」を確認した。
会議では、これまでの各組合の交渉が従来以上に厳しくなっていることに対し、連合の「全ての労働者とともに従業員主権主義の復活を目指し、真面目に働く者が報われる公正な社会を実現する」とした闘争方針を踏まえ、経営施策に対し懸命に努力している組合員の期待に応えるべく、以下の考え方により交渉を進めることとした。 |
≪進め方 その2(概要)≫
| ・要求書提出 |
| |
要求書提出に至っていない組合は、構成総連と連携をはかり、早期交渉を念頭に遅くとも3月末までに実施する。 |
| ・交渉の進め方 |
| |
(1) 雇用安定の取り組み |
| |
雇用安定の重要性について労使の共通認識を醸成するとともに、雇用安定に資する労使一体となった取り組みがはかれるよう会社対応を求める |
| |
(2) 労働協約に関する取り組み |
| |
労働協約の整備・充実、労使協議会の設置・充実に向けて、要求の趣旨に沿った具現化がはかられるよう経営側の対応を求める。また、定年退職者継続雇用の新設・充実、ならびに仕事と生活の調和がはかれる環境整備などについては、法改正に沿った対応をはかるとともに、更なる制度内容の充実に向けて協議を進める。 |
| |
(3) 賃金改定の取り組み |
| |
近年の賃金引上げ抑制に歯止めをかけるため、賃金カーブ維持分を最低限確保できるよう精一杯の交渉を行う。その上で、連合の中小共闘における妥結集約結果などを有効に活用しながら、個別水準の積極的な引き上げに向けて交渉を強化する。
また、賃金制度が確立されていない組合は、制度確立を求める。 |
| |
(4) 賞与・一時金の取り組み |
| |
年間賃金の一部として生活設計の重要な役割を担っていることを踏まえ、生活給的部分である年間 4.0 ヶ月を最低限確保する。その上で、組合員の経営諸施策への懸命な努力に報いるため、適正な成果配分として更なる上積みをはかる。 |
| |
(5) その他の取り組み |
| |
適正な労働時間管理の充実、パート労働者等の処遇改善への取り組みなどについては、要求の趣旨に沿った具体的な対応策がはかれるよう労使間の話し合い・協議を進める。 |
| ・解決時期 |
| |
構成総連ごとの統一交渉ゾーンや連合のヤマ場・解決促進ゾーンを踏まえ、前年の前倒しを念頭に、 3 月中の解決を目指して最大限の努力を行い、遅くとも 4 月中の解決に向けて鋭意交渉を強化する。 |
| ・会議日程 |
| |
(1) 第 1 回交渉責任者会議を 3 月 30 日(木)に開催する |
| |
(2) 第 3 回中央交渉推進委員会を 4 月 7 日(金)に開催する |
|

| ○電力総連2006春季生活闘争スタート (2006.2.23) |
電力総連 2006 春季生活闘争は 2 月 23 日(木)、電力総連加盟のおよそ8割以上の組合が要求書を提出し、交渉がスタートした。
今次春闘は、精力的な交渉と早期かつ有利解決がはかれるよう、構成総連ごとに「統一交渉ゾーン」を設定し、電力総連が一体となって取り組むこととした。
同日、電力総連の中島会長は、電気事業連合会に対し、雇用安定に関する要望を表明した。 |
我が国の経済社会は、長期にわたる景気低迷を脱し堅調な回復基調にあるとともに、雇用情勢も明るい兆しにありますが、一方で二極化が進む暮らしの中で、国民の不安定や不満が増大しており公正・公平な社会のあり方が求められています。
また、少子高齢化の急速な進展の中で、社会保障制度のみならず構造的変化への対応など、将来に向けては社会的な重要課題が山積している状況にあります。
一方、電力関連産業を取り巻く情勢は、受注競争の激化、電力の本格的な競争環境が整う中で、景気の回復基調にもかかわらず、未だ厳しい環境を抜け出すことが難しい状況にあります。この情勢の下、電力関連の各企業は生き残りをかけて難しい対応と選択を余儀なくされ、依然として先行き不透明な中で、電力関連産業で働く者においては、雇用への不安感、労働条件に対する不満が高まっているといえます。
電力総連としては、電気事業が今日までお客さま・地域に信頼され、安定的に電力供給を可能にしてきたのは、電力関連の各企業がそれぞれの役割を踏まえ、電力各社と一体となって事業運営に取り組んできた賜物であると考えています。特に、今般の台風や風雪による災害復旧にもみられるように、電力供給の信頼性が損なわれず、また、電力各社の経営が健全であるのは、電力関連産業に働く者が、年々厳しくなる経営環境下にありながらも、安定的な雇用を背景として、技能・技術の維持・向上に努めながら経営諸課題に対して前向きかつ地道に努力を傾注しているからであると考えています。
以上の認識に立って、今次春季生活闘争においては、個別労使間の交渉を通じて、雇用安定の重要性について労使の共通認識を情勢しつつ、雇用の安定確保と基本的な労働条件を守ることを最重要課題として取り組むこととしました。電力各社の経営の皆さまは、電気事業の健全な発展、更には社会的責務を果たすためにも、取り組みの主旨を十分ご理解いただき、電力関連産業に働く者の雇用安定に最大限の配慮を要望します。
また、電力各社を中心とするグループ経営強化への取り組みにおいて、グループ企業で働く組合員の将来に対する不安感が高まっています。この現状を踏まえ、構成総連を中心としたグループ懇談会などの設置・充実に取り組むこととしましたので、グループ経営を健全に推進するためにも、前向きな対応が図られることを求めます。 |
| なお、統一要求日に先立ち、各構成総連の代表者を委員とする第 1 回中央交渉推進委員会を 2 月 15 日(水)に開催し、「電力総連 2006 春季生活闘争 進め方(その1)」について確認を行った。 |
≪交渉の基調(概要)≫
日本経済は、長期に亘る景気低迷を脱し回復基調にあるとともに、雇用情勢も明るい兆しにあるが、電力関連産業を取り巻く情勢は、受注競争の激化、電力自由化の本格的な競争など、未だ厳しい環境を抜け出せない状況にあり、今次春闘も厳しく難しい交渉となることが想定される。
電力総連はこのような経営施策を真摯に受け止め、懸命な努力を傾注している組合員の雇用安定と基本的労働条件を守るため、構成総連、部会および加盟組合の連携を強化しつつ、交渉を展開していくこととする。
≪進め方 その1(概要)≫
| ・申し入れおよび要求書提出 |
| |
雇用安定に関する申し入れおよび要求書提出は、平成 18 年 2 月 23 日(木)に一斉に実施することとするが、一斉要求への対応が難しい加盟組合は、早期交渉を念頭に遅くとも3月末までに実施する。 |
| ・当面の日程 |
| |
第 2 回中央交渉推進推進委員会を 3 月7日(火)に開催することとし、それ以降の日程については、連合や他産別の動向などを総合勘案して決定する。 |
| ・交渉推進(連絡)体制 |
| |
交渉推進(連絡)体制を確立し、情報の共有化をはかりながら加盟組合の交渉を支援するとともに、統一交渉ゾーンを念頭に有利解決に向けて交渉の促進をはかる。 |
| ・その他 |
| |
電力総連は「電力総連 2006 春季生活闘争情報」により、適宜情報を発信する。
また、連合の中小・地場組合の共闘強化は、連合の中核産別としての役割、電力総連加盟組合への波及効果などを踏まえ、可能な限り連合方針に沿った対応を行う。 |
|

| ○電力総連2006春季生活闘争方針を決定 (2005.12.15) |
電力総連は 12 月 15 日(木)、 2005 年度第 1 回中央委員会を開催し、電力総連 2006 春季生活闘争方針について審議し、満場一致で決定した。
2006 春季生活闘争では、平成 18 年 2 月 23 日(木)を統一要求日とし、電力総連、構成総連、部会および加盟組合の連携を十分に図りながら、電力総連の総力を結集して取り組むことなどを確認した。 |

| 「電力総連2006春季生活闘争方針」を決定(2005.12.15) |
電力総連は、12月15日(木)に東京都内において、2005年度第1回中央委員会を開催し、電力総連2006春季生活闘争の方針を決定した。
これに基づき、各構成総連および各加盟組合は、現在進めている「労働環境点検活動」などを踏まえ、電力総連統一要求日(2006年2月23日)に向け、要求準備を進めていくこととする。なお、2月15日(水)に中央交渉推進委員会を設置する予定である。
また、連合は2006春季生活闘争の闘争方針を第1回中央委員会(2005年11月30日)にて決定し、12月15日には第1回中央闘争委員会において当面の方針(その1)を確認した。
加えて、全日本金属産業労働組合協議会(IMF-JC)でも第1回戦術委員会(2005年12月14日)が開催され、2006年闘争の大綱日程を決定した。
参考資料:電力総連2006春季生活闘争方針( 203KB) 203KB) |
|