|
 |
����R�������i�ψ���ɂ�
�u�d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ��i���̂R�j�v������I �i2010.4.8�j
�@�d�͑��A�́A�S���W���i�j��R�������i�ψ�����J�Â��A�u�d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ�(���̂R)�v�����肵���B
�@����̌��ɂ����ẮA�{�w�j�܂��A����������O���Ɏ��g�݂�i�߂Ă������������B
�����i�ߕ�(���̂R)����
�@�d�͑��A2010�t�G���������́A��Q�������i�ψ���Ŋm�F�����i�ߕ��i���̂Q�j�̂��ƁA�S���U�����݂ɂ����āA�Q�P�P�g�����v�������o���A��s�����S����S�P�g���܂߂X�P�g�����S�苭������W�J���A�����Ɏ����Ă���B
�@�������e�́A�����ɂ��Ă͒����J�[�u�ێ������m�ۂ�����ŁA��Ƃ̔��W�Ɍ����ĘJ�g�̋��ʔF�����������A�������茴�����l�����Ă�������g��������B�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�������o�c���������ŁA�ΑO�N��ő����z�Ƀo���c�L��������̂́A�T�ˑ��z��Ő��ڂ��Ă���B
�@���ẮA�����t�G�����������j�ł���u�������܂ޘJ�������̒�グ�v�Ɍ����A�㑱��������g���́A���������d�͑��A�E�\�����A�Ə��A�g�𖧂ɂ��A���L�̐i�ߕ��ɂ��v���̎����Ɍ����āA�Ō�܂ŔS�苭������W�J����B
�T�@��̓I�Ȏ��g�݂ɂ���
�P�@�������グ�ɂ���
�@�d�͑��A�̒������Ԃ́A�����̉����g���𒆐S�ɁA�ʒ����������ቺ�X���ɂ���A������������܂��グ�z�ɂ����Ă��Љ���������ɂ���B
�@�����t�G���������ɂ�����v���́A����ȏ������ቺ�����Ȃ����߂ɁA�����J�[�u�ێ����̊m�ۂ��ŏd�_�ۑ�Ƃ��A�o�c���ւ͒����J�[�u�ێ������m�ۂł��Ȃ��Ƃ������Ƃ́A�����I�Ȓ������ɂȂ邱�Ƃɂ��Ă�������Ƒi���A�Ō�܂œO��I�ɂ������������W�J����B
�@����ɁA�����g���̎��Ԃɉ�������������́A��Ɗ����̌���ł���u�l�v�ւ̓������s�����ƂŁA�l�ފm�ۂƋZ�\�E�Z�p�̌p���A���Y���̌����}��A��Ƃ̎����I�Ȕ��W�ɂȂ��Ă����Ƃ̎v�������߂��v���ł���A�Ō�܂ł������������W�J����B
�@�܂��A�A����5���J���ψ���i���������Z���^�[�j�ɂ����āA�Ì��~�j�}����Ƃ��āu�����J�[�u�ێ��������̊m�ہB�Z�肪����ȂƂ����4,500�~�ȏ�v�Ƃ��A
�@�����āu�������P���̊l�����߂����v�Ƃ��Ă��邱�Ƃ����܂�������������B
�Q�@�ܗ^�E�ꎞ���ɂ���
�@�����g���̗v���̎�|�܂��Ȃ���A�����������ł���N��4.0�������Œ���m�ۂ��邱�Ƃɂ������������W�J����B
�@���̏�ŁA�g�����̌o�c���{��ւ̌����ȓw�͂ɕ邽�߁A�K���Ȑ��ʔz���̊ϓ_�ɗ����āA����ɏ�ς݂�}��ׂ�������������B
�R�@���ԊO�������̈��グ�ɂ���
�@�����J����@�i���ԊO�������̈��グ���j�ւ̑Ή��ɂ��āA���j�ɑ���u1����60���Ԓ���50�������v�ɂ��Ċ�ƋK�͂ɂ�����炸�A���ׂĂ̐E��ɓK�p������悤�A�˂苭������W�J����B
�S�@���̑��̗v�����ڂɂ���
�@���̑��̗v�����ڂɂ��ẮA�v���̎�|�ɉ������O�i������ł��}���悤������������B
�@�������A�������ł̎���������Ɣ��f�����v�����ڂɂ��ẮA���̒ǂ����݂�}��Ȃ�����̐����Ɍ����Č��ɂ߂��s���A����̋���Ɍ��������g�݂Ɍq����B
�U�@�����ɂ���
�P�@��������
�@�����g���́A�O�q�̋�̓I�Ȏ��g�݂܂��A�\�����A�ƘA�g��}��Ȃ���A���́E��������{�Ƃ��āA�ł������̑���������O���ɒu���A�S�����̉������߂����B
�@�Ȃ��A�Ɛє��f���̎���ɂ��v�����̒�o�Ɏ����Ă��Ȃ��g���́A�\�����A�ƘA�g��}��Ȃ���A���j�ɉ����������ł̉����Ɍ����āA�����̗v������o�ɓw�͂���B
�Q�@��c�J��
�@�d�͑��A�S�̂̌������ɂ߂Ȃ���A�����i�̑Ή����K�v�Ɣ��f�����ꍇ�́A���̌�̐i�ߕ��ɂ��č\�����A�E�����g���̈�̓I���g�݂�}��ׂ��A���������i�ψ�����J�Â���B

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� |
| �`�u���W����v�S8�g�������i2010.3.30�j�` |
|
�d�͑��A 2010 �t�G���������ɂ����錟�W����̌��́A 2��22���̈�ėv���ȍ~�A�e�g�����S�苭�����͓I�Ȍ���W�J���Ă������ʁA 3 ��30���܂łɑS�Ă̑g�����Ì��Ɏ������B �����E�萔������яܗ^�E�ꎞ���̑Ì����e�͈ȉ��̂Ƃ���B
|
�E�� |
�����E�萔������z |
�� �^�E�ꎞ��
�i�N�ԑ��z�j |
������ |
�k�C�� |
�߰�Ű�Ј� |
0�~ |
564,720�~ |
3/30 |
�Ј� |
3,380�~�@�i�菸�����j |
1,126,000�~ |
���k |
�S�E |
0�~ |
737,300�~ |
3/27 |
�k�� |
���j |
0�~ |
563,500�~ |
3/26 |
�W�� |
0�~ |
1,006,400�~ |
���� |
���j |
1,040�~�@�i�菸�����j |
803,000�~ |
3/18 |
�W�� |
480�~�@�i�菸�����j |
1,467,600�~ |
���� |
���j |
0�~ |
794,000�~ |
3/18 |
�W�� |
0�~ |
1,417,600�~ |
���� |
���j |
0�~ |
849,800�~ |
3/26 |
�W�� |
0�~ |
1,014,000�~ |
�l�� |
���j |
�|2,369�~ |
872,500�~ |
3/26 |
�W�� |
�|2,569�~ |
1,125,200�~ |
��B |
�S�E |
0�~ |
1,279,750�~ |
3/25 |

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� |
| �`�u�d�ە���v�S10�g�����Ì��i2010.3.25�j�` |
|
�d�͑��A 2010�t�G���������ɂ�����d�ە���̌��́A 2��22 ���̈�ėv���ȍ~�A�e�g�����S�苭�����͓I�Ȍ���W�J���Ă������ʁA 3��25���A�S�Ă̑g�����Ì��Ɏ������B �����E�ܗ^�̑Ì����e�͈ȉ��̂Ƃ���B
|
������ |
���� |
��������i�g�������ϕ����j |
�ܗ^�i�ċG�x���z�j |
�k�C�� |
0�~ |
785,400�~ |
3/25 |
���k |
0�~ |
774,000�~ |
3/25 |
�֓� |
0�~ |
800,700�~ |
3/25 |
���� |
140�~ |
805,200�~ |
3/25 |
�k�� |
238�~ |
704,700�~ |
3/25 |
�� |
0�~ |
781,000�~ |
3/25 |
���� |
0�~ |
722,600�~ |
3/25 |
�l�� |
0�~ |
768,500�~ |
3/25 |
��B |
0�~ |
785,000�~ |
3/25 |
���� |
0�~ |
549,132�~ |
3/25 |

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� |
| �`�u�d�H����v�S10�g�������i2010.3.25�j�` |
|
�d�͑��A 2010 �t�G���������ɂ�����d�H����̌��́A 2 �� 22 ���̈�ėv���ȍ~�A�e�g�����S�苭�����͓I�Ȍ���W�J���Ă������ʁA 3 ��25���A�S�Ă̑g�����Ì��Ɏ������B �����E�ꎞ���̑Ì����e�͈ȉ��̂Ƃ���B
|
������ |
���� |
��������i�g�������ϕ����j |
�ꎞ�� �i�N�ԁj |
�k�C�d�H |
0�~ |
1,180,000�~ |
3/25 |
���A�e�b�N |
�\ |
1,212,000�~ |
3/25 |
�֓d�H |
0�~ |
1,270,000�~ |
3/25 |
�k���d�H |
0�~ |
�ƐјA������ |
3/25 |
�g�[�G�l�b�N |
0�~ |
1,320,000�~ |
3/25 |
�V�[�e�b�N |
0�~ |
1,270,000�~ |
3/25 |
����ł� |
0�~ |
�ƐјA������ |
3/25 |
���d�H |
0�~ |
1,230,000�~ |
3/25 |
�l�d�H |
0�~ |
�ƐјA������ |
3/25 |
��d�H |
�������P���@700�~ |
1,300,000�~ |
3/25 |

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� |
| �`�u�d�͕���v�S13�g�����Ì��i2010.3.19�j�` |
|
�d�͑��A2010�t�G���������ɂ�����d�͕���̌��́A2��22���̈�ėv���ȍ~�A�e�g�����S�苭�����͓I�Ȍ���W�J���Ă������ʁA3��18������19���ɂ����āA�S�Ă̑g�����Ì��Ɏ������B�ܗ^�̑Ì����e�͈ȉ��̂Ƃ���B
�i�P�ʁF�~�j
�P�@�g�@�� |
�ܗ^�i�N�ԑ��z�j |
���� |
�k�C���d�J |
1,685,000 |
3��18�� |
���k�d�J |
1,680,000 |
3��18�� |
�����d�J |
1,680,000 |
3��18�� |
�����d�J |
1,750,000 |
3��19�� |
�k���d�J |
1,700,000 |
3��19�� |
���d�J |
1,725,000 |
3��18�� |
�����d�J |
1,720,000 |
3��18�� |
�l���d�J |
1,760,000 |
3��18�� |
��B�d�J |
1,723,000 |
3��18�� |
����d�J |
1,543,000 |
3��18�� |
���{���q�͔��d�J�g |
1,424,000 |
3��18�� |
�d���J���J�g |
H20�`H22��3�N�ԁA�N��4�������x�[�X�Ƃ��āA�ƐјA���^�ܗ^�ɂ��x������������ |
���{���R�J�g |
1,163,000 |
3��18�� |

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ��i���̂Q�j���m�F�I |
| �`��2�������i�ψ�����J�Ái2010.3.9�j�` |
|
�@�d�͑��A2010�t�G���������́A��P�������i�ψ���Ŋm�F�����i�ߕ�(���̂P)�܂��A�����g����2��22���Ɉ�ėv�����s���A�\�����A�ƘA�g��}��Ȃ��琸�͓I�Ȍ���W�J���Ă���B
�@�S�̏�ɂ��ẮA�ٗp����ˑR�Ƃ��Č������ɂ�����̂́A��Ǝ��v�͉X���ɂ���A����Ƃ�2010�N3�����̌o�험�v�͑O����ő��v���m�ۂ��錩�ʂ��ł���B�������Ȃ���A�o�c���͍��ۋ����͈ێ��̊ϓ_����A���������ٗp�̈ێ����d�v�ł���A�����J�[�u�ێ��ɂ��Ă��T�d�ɔ��f���ׂ��Ƃ��āA���z�l����}���̎p�������߂Ă���B
�@�d�͊֘A�Y�Ƃɂ����ẮA�̔��d�͗ʂ̗������݂ɂ�锄�㍂�̌������Y�f�Љ�ւ̑Ή����܂߁A��s���s�������������Ă��邱�Ƃ���A�����g���̎咣�ɑ���o�c���̎p���͐T�d�ł���A������ƂȂ��Ă���B
�@���̂悤�ȏ���ł̍����t���́A�����̒ቺ�X���Ɏ��~�߂�������ϓ_����A���ׂĂ̑g���Œ����J�[�u�ێ����̊m�ۂɓO��I�ɂ������A���̏�ŁA�����g���̎��Ԃɉ����Ē����̒�グ���߂�������������Ɏ��g�ނ��ƂƂ��Ă���A�g�����̊��҂͑傫���B
�@�ȏ�̔F���ɗ����āA�A���̓������܂��Ȃ���A���L�̍l�����ɂ�荡��̌���i�߂Ă����B
|
��\���A���s���퉪� |
|
| �e�\�����A��\�� |
�����i�ߕ��i���̂Q�j����
I�@�v������o�ɂ���
�@�v������o�Ɏ����Ă��Ȃ��g���́A�\�����A�ƘA�g��}��A�u�d�͑��A2010�t�G�����������j�v�܂��A��������O���ɒx���Ƃ��R�����܂łɎ��{����B
II�@��̓I�Ȏ��g�݂ɂ���
�P�@���������グ
�@�����ɂ��ẮA�ቺ�X���Ɏ��~�߂������邽�߁A���ׂĂ̑g���ɂ����Ē����J�[�u�ێ������m���Ɋm�ۂ��邱�ƂƂ���B����ɁA��������Ɏ��g�ޑg���́A��Ɗ����̌���ł���u�l�v�ւ̓������A�l�ފm�ۂƋZ�\�E�Z�p�̌p���ɂȂ���A���Y�������߁A��Ƃ̎����I�Ȕ��W�ɂȂ����Ă����Ƃ̍l���Ɋ�Â��A������������B
�Q�@�ܗ^�E�ꎞ��
�@�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�v���̎�|�܂��Ȃ���A�����������ł���N��4.0�������Œ���m�ۂ��邱�Ƃɂ������A�S�苭������W�J����B
�@���̏�ŁA�g�����̌o�c���{��ւ̌����ȓw�͂ɕ邽�߁A�K���Ȑ��ʔz���̊ϓ_�ɗ����āA����ɏ�ς݂�}��ׂ�������������B
�R�@�d���Ǝ������̒��a���}�����̐���
�@�����J��@�i���ԊO�������̈����グ���j�ւ̑Ή��ɂ��ẮA���j�ɑ���u�P����60���Ԓ���50�������v�ɂ��āA��ƋK�͂Ɋւ�炸�A���ׂĂ̐E��ɓK�p������ȂǁA������������B
�@�܂��A�����玙�E���x�Ɩ@�ւ̑Ή��ɂ��Ă��A�������e�܂����J�������A�ƋK���̉����E�����Ɏ��g�ށB
�S�@�����ɂ킽���Ĉ��S�ł���J�������̊m��
�@�g�����Ƃ��̉Ƒ����܂߂āA�����ɂ킽���Ĉ��S�ł�����������E�ꊈ�͂Ɍq������p���ٗp�A�ސE�ꎞ������эЊQ�⏞���x�̐����E�[���Ɍ����āA��̓I���ʂ�������悤����W�J����B
�T�@�p�[�g�^�C���J���ғ��̑ҋ����P
�@�p�[�g�^�C���J���ғ��ɂ��ẮA�v���̗L���Ɋւ�炸�A�܂��͘J���������ɂ��Ď��Ԕc�����s���A���Y�҂���јJ�g�O�҂ł̋��ʔF����}��B���̏�ŗv���E�v�����s���Ă���g���́A�ҋ����P�Ɍ����Ĉ���ł��O�i���}����悤���g�ށB
III�@���̐i�ߕ��ɂ���
�P�@�d�͑��A
�@�d�͑��A�́A���������g���̌����L���ɐi�߂���悤�A�������Ԗ��c���̑g���ɑ��A�������Ԕc���E���͂̎x�����s���ƂƂ��ɁA�����g���̗v���Ɋ�Â��o�c���͂̎x�����s���B
�@
�܂��A�A����╔��Ȃǂ̏t���������ɂ��āA���������K���ɏ����s���Ă����B
�Q�@�\�����A
�@�\�����A�́A������]�[���̐ݒ�Ȃ�тɌ����i�ψ����K�X�J�Â���Ȃǂ��āA�����g���̗L�������Ɍ����Č����i��}���Ă����B
�@
�܂��A������q���Ă�������g���ɑ��ẮA�ʑΉ����܂ߎx������������B
�R�@�����g��
�@�����g���́A�\�����A�ƘA�g��}��A������]�[�����������Ȃ���A�v���̎�|�ɉ������������}����悤���͓I�Ɍ���W�J����B
�@
�Ȃ��A��������яܗ^�E�ꎞ���ɂ��āA���̓��������ɂ߂Ȃ����̓I�Ȍ�������Ɣ��f�����ꍇ�́A���̑O�i�Ƃ��āA��������яܗ^�E�ꎞ���ȊO�̗v�����ڂ̎����Ɍ����āA�o�c���̗����E�F����[�߂�Ȃǂ̌���W�J����B
IV�@�����ɂ���
�P�@��������
�@�R�����̉�����ڎw���čő���̎��g�݂��s���B����ɂ�肪�����ꍇ�́A�x���Ƃ��S�����̉��������ĉs�ӌ�����������B
�Q�@��c�J��
(1) ��P����A���ӔC�҉�c���R���R�P��(��)�ɊJ�Â���B
(2) ��R�������i�ψ�����S���W��(��)�ɊJ�Â���B

| �� 2010�t�G�����������X�^�[�g�@2��22������v���� |
�@�d�͑��A2010�t�G���������́A2��22���i���j�A�����g�����v��������Ăɒ�o���A�����X�^�[�g�����B����A���͓I�Ȍ��Ƒ������L���������͂����悤�A�����g���ւ̎x�����������A�\�����A���ƂɁu������]�[���v��ݒ肷��ȂǁA�d�͑��A����̂ƂȂ��Ď��g�ނ��ƂƂ��Ă���B
�@
�����A�퉪��́A�d�C���ƘA����ɑ��A�ٗp����ȂǂɊւ���v�����ȉ��̂Ƃ���\�������B
| �u�퉪��ɂ��d�C���ƘA����ւ̗v�����e�v |
�@�䂪���̌o�ς́A���E�o�ς̉��P��ً}�o�ϑ�̌��ʂȂǂ�w�i�Ɏ����������i��ł��܂����A��s���ɂ��Ă͓����̉͂��キ�A�ٗp��̈�w�̈�����f�t���̉e���Ȃǂɂ��A�i�C�́u��Ԓ�v�����O�����Ƃ����\�f�������Ȃ��ɂ���܂��B
�@����A�J���҂̐������Ԃ́A��ƕ���Ɖƌv����̔z���̘c�݂�������̒ቺ�X���Ɏ��~�߂��������Ă��炸�A�����i���̊g���Ꮚ���w�̑������i��ł���A�l��������������ԂŁA�ٗp�s���ƍ��킹�ĕ�炵����芪�����͋ɂ߂Č��������̂ƂȂ��Ă���܂��B
�@�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪�����́A�̔��d�͗ʂ��ʍH��������܂߂��H���ʂ̌�������ɂ͒�Y�f�Љ�����Ɍ����Ă̑z�肳���ۑ�ւ̑Ή��Ȃǂɂ��A��s���s�������������Ă���A�O���[�v��Ƃ݂̂Ȃ炸���͉�Ђ��܂߂������͂̔����Ǝ��v�͂̋��������߂���ɂ���܂��B
�@
�d�͑��A�͂��̂悤�ȏ܂��A�ٗp�̈ێ��E�g��A�J�g�̋��͂Ƌ��c�A���ʂ̌����ȕ��z�𒌂Ƃ����u���Y���R�����v�̈Ӌ`�ƁA�������I�ϓ_�ɗ������u�l�ւ̓����v�̏d�v��������x�J�g�ŋ��L�����Ă������Ƃ��̗v�ł���ƍl���Ă���܂��B���̏�Œ��������g���𒆐S�ɁA�ʒ����������ߔN�ቺ�X���ɂ���A�Љ�����������Ԃ����邱�Ƃ���A�J���ӗ~�̌���A�E�ꊈ�͂̏����A�l�ފm�ہE�琬�Ȃ�тɓ����g��̊ϓ_����ቺ�X���Ɏ��~�߂������A�������܂ޘJ�������̒�グ���߂����܂��B
�@���܂��ẮA�d�͑��A�̉����g���́A�{��2��22����v�����Ƃ��āA�������グ��p�[�g�^�C���J���ғ��̔K�J���҂̑ҋ����P����ɂ̓��[�N����C�t��o�����X�̎����Ɏ����鎞�ԊO�������̈����グ�Ȃǂ̗v��������Ăɒ�o�������܂��B�M�A����ɂ�����܂��ẮA�ٗp�̈ێ��Ɗg��A�����ĘJ�������̌���Ɏ�����ő���̂��z�������肢�������܂��B
�@�܂��A�\�����A��ɂ����ẮA�O���[�v�J�g���k��Ȃǂ�ʂ��A���ۑ�ɂ��ċc�_���Ă������ƂƂ��Ă���܂��̂ŁA���킹�Ă��������������܂��悤���肢�������܂��B
|

| �� �d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ��i���̂P�j �i2010.2.17�j |
����22�N2��17��
��1�������i�ψ��� |
| �d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ��i���̂P�j |
�@ �䂪���̌o�ς́A���E�o�ς̉��P��ً}�o�ϑ�̌��ʂȂǂ�w�i�Ɏ����������i��ł��邪�A��s���ɂ��Ă͓����̉͂��キ�A�ٗp��̈�w�̈�����f�t���̉e���Ȃǂɂ��A�i�C�́u��Ԓ�v�����O�����Ƃ����\�f�������Ȃ��ɂ���B
�@ ���̂悤�ȏ�̒��A�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪�����́A��Y�f�Љ�ւ̑Ή����܂ߐ�s���s�������������Ă�����̂́A�d�͑��A�́A�A���̕��j�ł���u���������̒ቺ��j�~���A�S�J���҂̐������ێ��E�h�q����ϓ_������g�݂����͂ɓW�J����v���ƂȂǂ��A���j�Y�ʂƂ��Ă̖����ƐӔC��S�����ׂ��A��d�͑��A2010�t�G�����������j��Ɋ�Â��A�\�����A�A����y�щ����g���̘A�g���������A���ɂ����𐄐i���Ă������ƂƂ���B
�P�@���O����
�@ �\�����A�A����y�щ����g���́A�d�͑��A2010�t�G�����������j�Ɋ�Â��A�v�����̒�o����ьٗp����Ɋւ���\������Ȃ�тɖ{�i�I���Ɍ��������O�����ɖ��S�������B
�@ �܂��A�������L���ȉ�����ڎw���Đ��͓I�Ȍ����W�J�ł���悤���̐��̊m�����s���B
�Q�@�v������o�E�ٗp����Ɋւ���\������
�@ �v�����̒�o�A�ٗp����Ɋւ���\������ɂ��ẮA����22�N2��22��(��)�Ɉ�Ď��{����B
�@ �������A����ɂ���ėv���ւ̑Ή�����������g���́A��������O���ɒx���Ƃ��R�����܂łɎ��{����B
�R�@�X�g���̊m��
�@ �J���W�����@��37���P���̋K��Ɋ�Â����v���ƂɊւ��鑈�c�s�ׂ̗\���ɂ��ẮA3��1��(��)�ɓd�͕����ь��W����̍\���g�������ꊇ���ēd�͑��A���s���A3��12��(��)�ɃX�g�����m������B
�S�@�����i
(1) |
�@ �d�͑��A���̘A�g���L���Ȃ�тɌ����i�̋�����}�邽�߁A�����i�̐����m�����A�����g���̌����x�����Ă����B |
| (2) |
�@ �d�͑��A�́A���������g���̌����L���ɐi�߂���悤�A�p���I�Ȓ������Ԕc���E���͂���ьo�c���͂̎x�����s���ƂƂ��ɁA���̎咣�_�Ȃǂ̏��M���Ă����B |
| (3) |
�@ �\�����A�́A�S�̏�̋��L���Ȃǎ��@���Ƃ炦�Č��ʓI�ȃI���O�����{����Ȃǂ��āA�����g���̑������L���ȉ������x������B |
| �i4�j |
�����g���́A�\�����A���ݒ肷�铝����]�[����O���Ɍ�������g�ݗ��āA�L�������Ɍ����Č��̑��i��}���Ă����B |
�T�@���ʂ̓���
�@ ��Q�������i�ψ����3��9��(��)�ɊJ�Â��邱�ƂƂ��A����ȍ~�̓����ɂ��ẮA�����g���̌��A�A���⑼�Y�ʂ̓����Ȃǂ𑍍����Ă��Č��肷��B
�U�@���̑�
(1) |
�@ �t�G���������Ɋւ�����ɂ��ẮA�K�X�K�ɢ2010�t�G�����������ɂ�蔭�M����B |
| (2) |
�@ �A���̃C���t���E���v�����A����c�⒆�������A�p�[�g�����Ƃ̘A�g��}��A�A���̒��j�Y�ʂƂ��Ă̖����܂��A�����g���̒�グ�Ɏ�������g�݂�i�߂�B |
|

| �� �d�͑��A2010�t�G�����������j������I�i2010.2.17�j |
| �`�d�͑��A�|�\�����A�|����|�����g���̘A�g���������A���͂Ɍ���W�J�` |
|
| �d�͑��A�́A2��17���i���j�ɓ����s���ɂ����āA��1���ψ�����J�Â��A�d�͑��A2010�t�G���������̕��j�����肵���B����Ɋ�Â��A�e�\�����A����ъe�����g���́A����̒������ԂȂǂ܂��A�d�͑��A����v�����i2010�N2��22���j�Ɍ����A�v��������i�߂Ă������ƂƂ���B�܂��A�����A��3��O����c�ɂĒ��������i�ψ���̐ݒu���m�F���A����������P�������i�ψ���ɂ����āA�u�d�͑��A2010�t�G�������� �i�ߕ��i���̂P�j���m�F�����B |
|
|
| �c���߂�k�����A�E�g�c�����ψ� |
|
����22�N2��17��
��1���ψ��� |
| �d�͑��A2010�t�G�����������j |
I.�@�o�ώЉ�̏
| �� |
�f�c�o�̓}�C�i�X���� |
�����f�c�o�́A2009�N1�`3�����܂�4�������ă}�C�i�X�����ƂȂ�����A4�`6�����i�N���Z�{2.3���j�ɑ����A7�`9�����i�N���Z�{1.3���j���v���X�����ƂȂ����B�������A��X�̐��������ɋ߂����ڂf�c�o�Ō���}�C�i�X�����i����3.4���j�ƂȂ��Ă���A����W�]���|�[�g�ł����N�x�̌��ʂ��͎���GDP��3.2���Ɨ\������Ă���B
2008�N�̔N���ȍ~�}���Ȍ��Y�ƁA�ɒ����͌o�ϐ����̃}�C�i�X�v���ƂȂ邪�A���̍ɒ������ꏄ�����Y����ɂ��邽�߁A����̌i�C�̉ɂ̓v���X�v���ƂȂ�B�������A���Y�̐����͍�N�̉Ăɔ�ׂ���̐����͒Ⴂ���Ƃɉ����A����A�Z��A�ݔ������̓������ア�B |
| �� |
���v��������Ǝ��v |
| 2009�N�x�̊�Ǝ��v�́A�O�N�x�ɑ����啝�Ȍ��v���\�z����Ă���B����Z�ςɂ��A�S�Y�ƁE�K�͌v��2009�N�x�̌o�험�v��19.3���̌��v�A���������Ƃ�39.1���̌��v�A���Ƃ�9.8���̌��v�����݂ł���A�i�C�ߒ��ő傫�ȗ��v�������������Ƃ𒆐S�ɑ傫����������ł���B�����Ƃ̒��ł�������Ƃ�46.2���̌��v�ƌ��������ʂ��ƂȂ��Ă���B2009�N9�����̒��Ԍ��Z�́A��萻���Ƃ𒆐S�ɂR�����̑啝�Ԏ����獕���ւƉ��P���ꂽ���̂́A��s���ɑ��Ă͐T�d�Ȍ��ʂ��ƂȂ��Ă���B |
| �� |
������������������� |
| ���t����G�R���ł��͂��߂Ƃ���o�ϑ�̌��ʂ������āA���Ƃ̐����Ƃ𒆐S�Ɋ�Ƃ̌i���������P��������ƂȂ��Ă���B�������A������Ƃ̌i�����͉��~�Ƃ݂��Ƃ��ˑR�Ƃ��đ����B�܂��A�����̌i���ɂ��Ă��A����Ƃ͐�s���ɖ��邳����������̂́A�ΏƓI�ɒ�����Ƃ́A���������ʂ��ƂȂ��Ă���A��芪�����͈ˑR�Ƃ��Č������������ƌ�����B�Ȃ��ł��A�������v�̈ˑ��x���������ƂŌ��������Ă���B |
| �� |
�ቺ�������������� |
�ꎞ���A�c�ƍ��݂́u�������^���z�i���Γ��v�E5�l�ȏ㎖�Ə��j�v�́A��N�̔N���P����̃}�C�i�X�ł��������̂��A2009�N�ɓ����2�`3���Ƀ}�C�i�X�����g�債���B�Ă̈ꎞ���̎x�������ł���6���́�7.0���A�V���́�5.6���ƂȂ�A9���̓}�C�i�X�����k�����Ă�����̂́�1.6���ƂȂ��Ă���B
�����I�Ɍ����������ቺ���Ă���B�����\����{���v�����ŕ��Ϗ���������̐��ڂ��݂�ƁA2001�N��305,800�~���s�[�N��2008�N��299,100�~�ɉ��������B���̂��Ƃ́A�����Ȃ��z���Ƃ���ꂽ�i�C�ߒ��ɂ����Ă��A�J���҂֕��z������Ȃ��������Ƃ�\���Ă���B |
| �� |
���������̒��ł��A�ア����s�� |
GDP�̂T�������߂�l����W�ɂ��ẮA���{�̌o�ϑ���ʂ��o�Ă���ʂ����邪�A�����̒ቺ��c�Ƃ̌����A�ꎞ���팸�̉e���ŁA�S�ݓX��X�[�p�[�Ȃǂ̏����Ƃ͔���̌����������ȂǁA�S�̂Ƃ��Ă͒�����Ă���B
����ҕ����i���N�����������j�͂W���Ɂ�2.4���Ɖߋ��ő�̉������L�^�������ƁA10���ɂ���2.2���̉����ƂȂ��Ă���B���̂悤�ɕ������������Ă���̂́A��N���������Ζ��֘A���i�Ȃǂ̉��i�������������Ƃɉ����A�O�I�v���̉e�������Ȃ����i���A����ւ̎h���ƃR�X�g�����̌����ɂ�艿�i���������Ă��邽�߂ł���B
���i�����̔w�i�Ƃ��ẮA�����������I�ɉ�������Ȃ��ŒᏊ���ґw���������A����ɂ́A�s���̉e������ꎞ���Ȃǂ��啝�Ɍ����������Ƃɂ�����ނɑ���h����Ƃ��āA�ቿ�i���ɔ��Ԃ������������߂ƍl������B�ቿ�i���̂��߂ɂ́A�R�X�g�팸���K�v�ł��邱�Ƃ���A�J�������ւ̈����������͂ƂȂ��Ă���A���̈��z��f���萶������邱�Ƃ��K�v�ƂȂ��Ă��邽�߁A���J�g���ׂĂ̊W�҂����ꂼ��̖��������邱�Ƃ����߂��Ă���B
�Ȃ��A���t�{�����\����11���̌���o�ϕł́A�u�����̓����𑍍����Ă݂�ƁA�ɂ₩�ȃf�t���ɂ���v�Ƃ��āA�i�C�����������郊�X�N�����݂��邱�Ƃɗ��ӂ���K�v������Ƃ����B |
| �� |
�ߋ��ň��̌ٗp� |
���S���Ɨ��́A7����5.7���Ɖߋ��ň����L�^���A�X��5.3���A10��5.1���Ɖ��P���Ă��Ă���A���[�}���E�V���b�N�ȍ~�̋}���Ȍٗp�̈����Ɏ��~�߂����������i�D�����A�ߋ��ň��̏������Ă��邱�Ƃɕς��͂Ȃ��B�܂��A10���̗L�����l�{����0.44�{�ƂX���ɔ��0.01�|�C���g�㏸�������A�ߋ��Œ�̐����Ő��ڂ��Ă���B���Ј��̗L�����l�{����0.26�{�ŁA��N�̔����ȉ��̐����ɗ����Ă���B�܂��A���Z���̏A�E�s�ꂪ�[�����𑝂��Ă���A�����J���Ȃɂ��A���t�̍��Z���Ɨ\��҂ɑ���V�����̋��l���͖�13.5���l�ŁA�O�N������̔����߂��ɂ܂ŗ�������ł���B
����̌ٗp��ɂ��Đ�s���́A�������Ȃ�Ǝw�E���鐺���������A�A���͈��������A�ٗp�̈���E�n�o�Ɍ��������g�݂ɑS�͂��X�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |
| �� |
���������J������ |
2008�N�H�ȍ~�̐��E�I�ȕs���̒��ŁA�A�o�֘A�Y�Ƃ𒆐S�ɑ啝�Ȍ��Y���������ʘJ�����Ԃ��c�Ƃ𒆐S�ɑ啝�Ɍ��������B���Γ��v�Ō��������Ƃ̏���O�J�����Ԃ�2009�N1�`3�����́�45.6���i�O�N������j�A4�`6��������43.1���i���j�ƂȂ������ƁA7�`�X�����́�29.1���i���j�ƁA���Y�̎����������Ō��������k�������B�S�Y�ƂŌ�������O�J�����Ԃ��Q���A�R���Ɂ�20�����ƂȂ������ƁA���X�Ɍ��������k�����X���́�14.1���ƂȂ����B
�ٗp�̊m�ۂ�[�N�E���C�t�E�o�����X�̎����̊ϓ_������A���̂悤�Ɍ��������J�����Ԃ����Ƃ̒����ԘJ���ɖ߂����Ȃ����g�݂��K�v�ł���B |
II.�@�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪���
1.�@�o�c��
| �� |
�d�͊֘A�Y�Ƃ̌o�c���́A�d�͉�Ђ𒆐S�Ƃ��āA�i�C������Ăɂ��̔��d�͗ʂ̑啝�ȗ������݂͂�����̂́A�����Ȃǂ̉��i�ቺ�ɂ��R����啝�Ɍ������A����Ɉב������~���ɐU��Ă��邱�Ƃ⌴�q�͔��d���̐ݔ����p�������P����ȂNjƐт̉�������B�������Ȃ���A�A���ł̔��㍂�͒ʊ��Ł�10.1���̌����݂ł���A��s���ɑ���s���͕��@�ł��Ă��Ȃ��B |
| �� |
����A�e��Ƃ́A���Ԑݔ������̑啝�Ȍ����ɂ������̌����A��\�Z�H���̑����A�H���Z�k�̋����v���A����ɂ͍���̌������Ƃ̍s�����s�����ȏƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�������𑝂��Ă���B |
| �� |
����}�𒆐S�Ƃ����V���{�́A�������ʃK�X�r�o�팸�̒����ڕW���u90�N��25���팸�v���߂����Ƃ��āA�����r�o�ʎ�����x��Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�̓����A���g�����ł̌����ȂǁA�����鐭���������Ƃ��Ă���A�d�͊֘A�Y�Ƃւ̉e���͕K���ł���A��s���s�������������Ă���B |
| �� |
�G�l���M�[�Z�L�����e�B�̊m�ۂ���ђ�Y�f�Љ�̎����Ɍ����āA�[���E�G�~�b�V�����d���̒��S��S�����q�͂̊J�����i�ƈ��S�����ŗD�悵���ݔ����p���̌��オ���߂��Ă���B�����āA�n��Ƃ̂�邬�Ȃ��M���W�̍\�z�����߂��Ă���B |
| �� |
���̂悤�ȏ��ɂ����āA�e��Ƃ̌o�c��Ջ�����ړI�Ƃ����o�c�������͈ˑR�Ƃ��ďd�v�ȉۑ�ł���A�O���[�v��Ƃ݂̂Ȃ炸���͉�Ђ��܂߂������͔����Ǝ��v�͋��������߂��Ă������ŁA�J�������̈��������⍡��̌ٗp�s�������O�����B |
| �� |
�ߔN�̒c��̑�ʑސE�A��N�w�̒��r�ސE�A�̗p�v��̖��B���Ȃǂɂ��A�v������͌������A�ꕔ�ɂ͐l�ޕs�����ۑ�ƂȂ��Ă����Ƃ�����A�����ɂ킽�錒�S�Ȕ��W���߂������߂ɂ́A�J�������̌���ɂ��l�ނ̊m�ہA�Z�p�E�Z�\�̌p���A�E�ꊈ�͂̏������ɂ߂ďd�v�ȉۑ�ƂȂ��Ă���B |
2.�@�E��̏�
| �� |
�v������������A�Ɩ��̍��x���E���l���ɂ�莿�E�ʂƂ��ɋƖ����S�������A�J�����Ԃ������X���ɂ��钆�A�g�����͎�芪�����\���F�����A�e��o�c�{��̒B���ɂ�鎖�Ɗ�Ղ̋����A��Ɨϗ���@�ߏ���̓O��ȂǁA�֘A�Y�Ƃ���̂ƂȂ��Ď��g��ł���B |
| �� |
���S�Ɋւ��ẮA����20�N�x�̘J���ЊQ�͋��͉�Ђ��܂�552���i�O�N�䁣31���j�ō��~�܂�̏ɂ���A�O���[�v��Ƃ݂̂Ȃ炸�A���͉�Ђ��܂߂������E��܂ł̃R�~���j�P�[�V��������w�[�������A���S�ŗD��ƃ��[������̈ӎ���Z��������Ƌ��ɁA�ЊQ�����̐[�x��Ƒ�̊m���Ȏ��{�ɂ��A�ЊQ�h�~�̓O��ɓw�߂Ă���B |
| �� |
�Ɩ��ʂƗv���̕s������ߓx�ȋƐъǗ��^�̋Ɩ��^�c�Ȃǂɂ��A�����ԘJ������������g�������������Ă���A�����^���w���X�s���҂̑����ȂǐS�g�̌��N�ւ̉e�������O����邱�Ƃ���A���[�N����C�t��o�����X�̎����Ɍ��������g�݂����߂��Ă���B |
| �� |
�������鍋�J�Ȃǂ̎��R�ЊQ�ɂ����鑁�������A���ݓd���̈���^�]�A���o�N�����Ă��闬�ʐݔ��̕ۈ����ȂǁA�����o�ςɕs���ȃC���t���Ƃ��Ă̏d�v�����\���F�����āA�e��Ƃ����ꂼ��̐l�ƋZ�p�����W���A��̂ƂȂ��ē��錜���Ɉ��苟���ɓw�߂Ă���B |
III.�@�A����̏
2010�t�G���������ł́A���{�o�ρE�Љ�̒ꊄ��Ɏ��~�߂������A���������̒ቺ��j�~���A�S�J���҂̐������ێ��A�h�q����ϓ_������g�݂����͂ɓW�J����B���̂��߂ɂ́A�@���O���o�����X�̂Ƃꂽ�o�ς̎����A�A��ƕ���Ɖƌv����̔z���̃A���o�����X�̐����A�B�ٗp�̈���E�n�o�Ə����o�����X��}���Ă������Ƃ��s���ł���B
���������ϓ_����A�E��œ������ׂĂ̘J���҂�ΏۂɁA�����̈ێ��E���P�Ɏ��g�ށB���̂��߁A�����������ێ�����ƂƂ��ɁA�K�v�ȏꍇ�͊i�������Ɏ��g�ށB����ɁA�ϓ��E�ύt�Ɍ������������P��}��ƂƂ��ɁA�Œ�������̈����グ�ɂ���Ē�グ��}��B�����āA�����������ʂ��Љ�S�̂ɔg�y�����邽�߁A�����A����c�̋@�\������}��ƂƂ��ɁA�@��Œ�����������グ�邽�ߎ��g�݂��������A�Љ�S�̂̒�グ��}���Ă����B�܂��A���������ő����J�����Ԃ̏k����}��A�ٗp�̈���E�n�o�ɂȂ��Ă����ƂƂ��ɁA�ٗp�m�ۂɌ������J�g���c��O�ꂷ��B
����ɁA���������ł́A�i�C�A�ٗp�̈���E�n�o�A�����h�q��}�邽�߁A�Ԃ̗��ւƂ��Đ������x���g�݂��ʒu�Â��A�����������P�̂��߂̎��g�݂Ƃ��ē��������͂ɐ��i���Ă����B
1. ���g�݂̒��Ƒ̐�����
| �i1�j |
�S�J���҂�Ώۂɏt�G���������𐄐i
�K�J���҂��܂߂��ׂĂ̘J���҂�Ώۂɒ����A�J�����ԓ����܂߂��J���������̉��P�Ɏ��g�ށB���̂��߁A�g�����̘J�������̉��P��i�������̎��g�݂ƂƂ��ɁA�g�����ł͂Ȃ��J���҂ɑ��Ă��A�������P���͂��ߗl�X�ȉۑ�Ɏ��g�ށB�����āA��Ɠ��Œ��������̒����g��A�����̈����グ�ɂ���Ē�グ�̎��g�݂�W�J����B |
| �i2�j |
���������ێ��̎��g�݂̓O��
���������̒ቺ�Ɏ��~�߂������A���̐������ێ����邽�߂ɂ́A�������x�����A�ʃ|�C���g�ɂ������ΐ������d�����Ă����K�v������B�A���́A�����������g�݂��܂߁A���ׂĂ̑g���Œ����J�[�u���ێ�������g�݂��Y�ʂ̎w���̉��œO�ꂷ��B�܂��A���ƒ����̒����i���͊g��X���ɂ��邽�߁A���������ɂ����Ă��i�������̎��g�݂𐄐i����B |
| �i3�j |
�����J�����Ԃ̓O��k���ɂ��ٗp�̈���E�n�o
�A���́A180���l�̌ٗp�n�o���͂��߁A�ٗp�̈���E�n�o�Ɋւ�鐭�����x�̎����Ɍ��������g�݂���������ƂƂ��ɁA�����J�����Ԃ̓O��k���ɂ��ٗp�̈���E�n�o��}���Ă����B
���̂��߁A�d���ʂ̌����ɂ��A���̊ԂɌ��������J�����Ԃ����Ƃ̒����ԘJ���ɖ߂����Ȃ����Ƃ��܂߁A�Y�Ƃ̎��Ԃɉ��������������ɂ�鑍���J�����Ԃ̏k��
�A�J�����Ԃ̏���K���̓O��A�ߏd�J���������Ȃ����g�ݓ��ɂ��A���[�N�E���C�t�E�o�����X�̎����ƔK�J���҂��܂߂��ٗp�̈���E�n�o��}��B�܂��A�������Z���j�Ɋ�Â��Œᓞ�B�ڕW�̒B���ւ̎��g������A�J��@�����ɔ����J������̐����i���ԊO�E�x��������50���̎������j���s���B |
| �i4�j |
�����A����c�̑̐�����
2010�t�G���������𐄐i�������̎Љ�I���f����}�邽�߁A�]�[���̐ݒ�A���j�g���̓o�^�g��ƁA�����A����c�̋@�\�����̂��ߑ�\�����i�J���҂̐E��A�N��A���������Ȃǁj��ݒ肷��B���̂����ŁA���j�g���𒆐S�ɒ��������グ���ʂȂǂɂ��ĊJ�����A�����J���ҁA���g�D�J���҂ւƑ���̔g�y��}���Ă����B |
| �i5�j |
����E���x�Ƃ̘A�g����
�����𒆐S�Ƃ����i�C�̉ƌٗp�̈���E�n�o�Ő����h�q��}���Ă������߁A���������2010�t�G���������ł́A����܂ňȏ�ɐ���E���x�����Ɍ��������g�݂Ƃ̘A�g���������Ă����B |
2. ���ׂĂ̑g�������g�ނׂ��ۑ�i�~�j�}���^���ۑ�j
| �i1�j |
�����J�[�u�ێ�����K���m�ۂ���B |
| �i2�j |
�K�J���҂��܂߂��S�J���҂�ΏۂɁA�������͂��߂Ƃ���ҋ����P�Ɏ��g�ށB |
| �i3�j |
�����̒�グ��}�邽�ߊ�Ɠ��Œ��������̒����g��ƁA���̐����������グ��B |
| �i4�j |
���������J�����Ԃ����Ƃ̒����ԘJ���ɖ߂����Ȃ��悤�A�Y�Ǝ��Ԃ܂��������J�����Ԃ̒Z�k��A���ԊO�E�x���J���̊������̈����グ���ɂ���āA�ٗp�̈���E�n�o��}��B |
|
IV.�@�d�͑��A�Ƃ��Ă̊�{���j
�@ �d�͑��A2010�t�G���������́A��Y�f�Љ�ւ̒�����܂߂ēd�͊֘A�Y�Ƃ������ɘj���Ĕ��W�����Ă������߂ɁA�ٗp�̈ێ��g��A�J�g�̋��͂Ƌ��c�A���ʂ̌����ȕ��z�𒌂Ƃ����u���Y���R�����v�̈Ӌ`��J�g�ŋ��L�����A�u�l�ւ̓����v�̏d�v����i���A�����ւ̊��͂Ɍq���Ă������g�݂ƈʒu�t���A�A���t�G���������̎��Љ�I�Ȗ����ƁA�d�͑��A�Ƃ��Ă̓���I�Ή��̏d�v����F�����A���̊�{���j�ɂ����g�ށB
���ɁA���������g���𒆐S�ɁA�ʒ����������ߔN�ቺ�X���ɂ���A�d�͑��A�~�j�}��������Љ���i�����J���ȁF�����\����{���v�����j���������Ԃ����邱�Ƃ���A�J���ӗ~�̌���A�E�ꊈ�͂̏����A�l�ފm�ہE�琬�̊ϓ_����ቺ�X���Ɏ��~�߂������A�������܂ޘJ�������̒�グ���߂������Ƃ��ɂ߂ďd�v�ł���B
�d�͑��A�E�\�����A�͏]���ȏ�ɘA�g�𖧂ɂ��A�������̂��߂̋�̓I�Ȏx�����s�����ƂƂ���B
| �i1�j |
���������グ�ɂ��ẮA�����J�[�u�ێ����̊m�ۂɓO��I�ɂ������A���̏�ʼn����g���̎��Ԃɉ����āA�����̒�グ���߂�������������Ɏ��g�ށB |
| �i2�j |
�ܗ^�E�ꎞ���͔N�Ԓ����̈ꕔ�ł���A����I�Ȑ����������Ƃ��ĔN�ԂS�������m�ۂ���B |
| �i3�j |
�����J��@�i���ԊO�������̈����グ���j�ւ̑Ή����܂ޔN�ԑ����J�����ԒZ�k���͂��߂Ƃ����u�d���Ǝ������Ƃ̒��a�v���}��铭�����ւ̉��v�Ɏ��g�ށB |
| �i4�j |
�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����ґS�̂̒�グ��}�邽�߁A�p�[�g�^�C���J���ғ��̑ҋ����P�Ɍ��������g�݂��s���B |
|
V.�@��̓I���g��
1. �ٗp����E�J�������m�ۂ̎��g��
�@ �����ɂ����鎸�Ɨ����ꎞ�I�ɉߋ��ň����X�V����Ȃnjٗp��͐[���ȏ�ɂ���A�d�͊֘A�Y�Ƃɂ����Ă�����̌ٗp�s�������O����邱�Ƃ���A�d�͑��A�A�\�����A�y�ѕ���́A�Ή�����o�c���Ɍٗp����Ɋւ���\��������s�����ƂƂ��A�e�g���͑g�����̕s����z�肳���ɑΉ����邽�߁A�J�g���c��ɂ����鋦�c�Ə�L��A�J������ɂ�����J���҂̌����̊m�ۂȂǂɂ��āA�ȉ��̂Ƃ�����g�ށB
�@ �܂��A�d�͊֘A�Y�Ƃœ����҂̌ٗp����A���S�E���N�̊m�ہA�d���Ǝ������̒��a���}�����̐����Ȃǂ̎��_�ɗ����āA�\�����A��̘J�g���k��̏[���Ɏ��g�ށB
| �� |
�ٗp����Ɋւ���\����B |
| �� |
�l�������N���A�������Œ���m�ۂ����J������̐����E�[���B |
| �� |
�d�͑��A�u�J�g���E���c�Ɋւ���w�j�v����{�Ƃ����J�g���c��̏[���B
�i�Œ�l�����P��ȏ�A����J�Ẫ��[�����j |
2. ���������グ�̎��g��
�@ 2005�N�x����W�J���Ă����u�J�����_�������v�̐��ʂ܂��A���ׂẲ����g���͎��O�����Ƃ��āA�������Ԕc�����m���ɍs���A�����J�[�u�ێ����̊m�ۂɓO��I�ɂ������A���̏�ʼn����g���̎��Ԃɉ����āA�����̒�グ���߂�������������Ɏ��g�ށB
(1)�������Ԃ̔c��
���̎��O�����Ƃ��āA���ׂẲ����g���͎��Ђ̒������Ԃ�c�����A�����J�[�u�ێ����ɕK�v�Ȍ����̎Z�o���s���ƂƂ��ɁA�����J�[�u�̘c�݂�������z�̕�Ȃǂ̉ۑ�c�����s���B�܂��A�ߋ��̒����J�[�u�Ɣ�r���Ăǂ̂悤�ɕω����Ă��邩�̊m�F���s���B
(2)�������グ
�@�@�����J�[�u�ێ����̊m��
���������̒ቺ��j�~���A�E����������ێ����邽�߂ɂ��A�����J�[�u�ێ����̊m�ۂ����`�Ƃ��Ď��g�ށB
| �� |
�������x�i�������[�������x������Ă���j���m�����Ă�������g���͂��̒����\���ێ�����B |
| �� |
�������x�i�������[�������x������Ă���j���m�����Ă��Ȃ������g���́A�����J�[�u�ێ�����v������B
�@
�Ȃ��A�����J�[�u�ێ����̎Z�o������ȉ����g���́A�����J�[�u�ێ����Ƃ��āA�A�����������ڈ��z��v������B |
| �� |
�����J�[�u�ێ����̎Z�o������ȉ����g���́A�����J�[�u�ێ����Ƃ��Ėڈ��z�������͖ڈ�����v������B |
���ڈ��z�u4,500�~�v
�A�����������ɂ�������Ԓ����J�[�u�ێ����̑����z�B2008�N�x�̒n��~�j�}���N��ʒ����i�S�Y�ƁE�j���v�j���ʐ���18����45��1��1�N�ԍ��̕��ϊz�B |
| �� |
�ٗp�����D�悵�āA��������������̓�����팸�Ȃǂ��s�킴��Ȃ����������g���́A���������B |
| �� |
�d�͑��A�͋Ǝ�ʕ���̒����J�[�u�ێ����̈ꕔ�Ƃ��Ē�������������̏��J���������g���̗v������O�ɍs���A�d�͑��A���̑���`���ɓw�߂�B�Ȃ��A���̑��̉����g���ɂ����Ă��A�\�����A���ɑ��ď��J���ɓw�߂�B |
�A�@�������蕪�̊l��
�ߔN�̓d�͑��A�ƎЉ���i�����\����{���v�����j�̒ቺ���̊i�����l������ƂƂ��ɁA���ɋK�͂������������g���ɂ����Ă͎Љ����傫���������Ԃɂ��邱�ƁA����ɂ͘A�������������j�́u�������P��500�~�ȏて�v�܂��A�����g���̎��Ԃɉ����āA�ȉ��Ɏ������ڂ��w�W�Ƃ��āA�������蕪�u500�~�ȏ�v�̗v�����s���B
���������P���u500�~�ȏ�v
�@
�Љ����1��1�N�ԍ��̕��ϊz5,000�~�ƒ����ڈ��z4,500�~�̍��B
I�F�ʒ����������u�d�͑��A�~�j�}�������v�����������g���́A�Œ���K�v�Ȑ��v����m�ۂ���ϓ_����A�ʒ��������̈��グ�Ɏ��g�ށB
�y�d�͑��A�~�j�}�������z
�N�� |
18�� |
20�� |
25�� |
30�� |
35�� |
40�� |
�}�{ |
�P�g |
�P�g |
�P�g |
�z���+�q1 |
�z���+�q2 |
�z���+�q2 |
�����i�~�j |
153,800 |
162,300 |
183,600 |
219,500 |
277,500 |
310,700 |
II�F�u�d�͑��A�~�j�}�������v���m�ۂ�����ŁA�Љ���܂����ʒ��������̈����グ���K�v�Ɣ��f���������g���́A���\�̖ڕW�������Q�l�ɁA���̊l�����߂����B
�y�ڕW�����z
| �@ |
�ڕW����I |
�ڕW����II |
���� 30�E�Α�12�N |
262,000�~ |
289,000�~ |
���� 35�E�Α�17�N |
305,000�~ |
348,000�~ |
* �d�͑��A�������Ԓ����Ȃ�тɌ����J���Ȓ����\����{���v�����̉ߋ�5�N���ϊz�����Ă��Z�o�B�ڕW�����T�͒��ʁA�ڕW�����U�͑�3�l���ʁB
III�F�������x����ɂ��e���̌��Ɖ�
�ߋ��ɂ����ĘJ�g���ӂ����������x�ɂ��āA������������������z���肵���ꍇ�A���̌�̌ʒ��������̎��Ԃ�c�����A���Ђ̎Љ�I�ʒu����g�����̘J���ӗ~��������Ă��v�����s���B
IV�F�����J�[�u�̘c�݂�������z�̕�̐���
���Ђ̒������Ԃ�c�����A�c�݂�肪����A�������K�v�Ɣ��f�����ꍇ�́A���̉��P�Ɏ��g�ށB
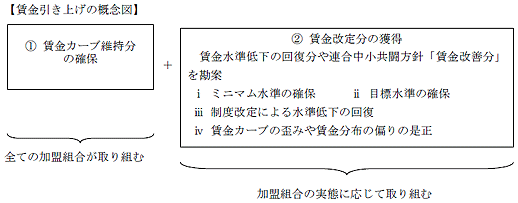
(3)�@�z�����̏[��
�����̈�����m�ۂ��A���������ł��b��E���������ɂȂ���z����ڎw���A�v������i�K����z�������d���������g�݂��s���B
(4) �������x�̊m��
�������x�E�̌n���m������Ă��Ȃ������g���́A�������Ԃ�c�����A���Ђ̉ۑ�𖾂炩�ɂ�����ŁA�J�g�ɂ�錟���E���c�̏��ݒu���A�������x�E�̌n�̊m���Ɍ������g�ށB���ɁA����I�Ȓ����������m�ۂ���ϓ_����A��������̃��[������}���Ă����B
(5) �Œ��������̎��g��
�p�[�g�^�C���J���ғ����܂߂��d�͊֘A�Y�Ƃɓ������ׂĂ̘J���҂̊�Ɠ��Œ�����Ƃ��āA�ȉ��̗v�������܂��āA�g�����Ƃ̍Œ����������������B
�y�Œ����������F�d�͑��A�~�j�}��������18�Α����z�Ƃ��Č��z�u153,800�~�ȏ�v�܂��͎��Ԋz�u890�~�ȏ�v�z
���d�͑��A�~�j�}������18�Α����z�i153,800�~�j���@��J�����ԁi174���ԁj��890�~
(6) ���C���̈����グ
�Z�p�E�Z�\�̌p����}�邤���ň���I�ȐV�K�̗p�͕K�v�ł���A�J�������̏�⓯�Ƒ��ЂƂ̔�r�E���͂��s���A�d�͊֘A�Y�Ƃ����߂�l�ނ��m�ۂł���悤�e�����g���ŗv���z�����肷��B
�Ȃ��A�d�͑��A�~�j�}������18�Α����z��������Ă�������g���͂��̊m�ۂɌ����Ď��g�ށB
3.�@�ܗ^�E�ꎞ���̎��g��
�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�N�Ԓ����̈ꕔ�Ƃ��Ĉ��肵���������x���鐶�����������Œ���m�ۂ��邱�Ƃ���{�Ƃ��āA���ɂ��v�����s���B
�܂��A�ē~�^�ɂ��N�ԗv���E�N�ԑÌ�����{�Ƃ���B
| (1) |
�v������
�u�N��4�������Œᐅ���v�Ƃ��A�ߋ��̑Ì����сA��ƋƐсA���Y�������E����ԂȂǂ����Ă��āA�S�������ɏ�ς݂�}�����v�����s���B |
| (2) |
�~�G���̈���
�~�G���ɂ��ẮA���������グ��̃x�[�X���g�p���A�ċG���ɏ����������Ƃ���B |
| (3) |
�x����
�ċG����6����{�A�~�G����12����{�Ƃ���B |
4.�d���Ǝ������̒��a���}�����̐���
(1)�@�����J��@�i���ԊO�������̈����グ���j�ւ̑Ή�
2008�N�x��10��O����c�iH21.9.8�j�Ŋm�F�����u�@�����ɔ����d�͑��A�Ƃ��Ă̊�{���O�v������������ŁA���̓��e����{�Ɏ��g�ށB
�@�@���ԊO�������̈����グ�ɂ���
| �� |
�����@�̓��e�ł���u1����60���Ԓ���50�������v�ɂ��āA��ƋK�͂⓭�����Ɋւ�炸�A���ׂĂ̐E��ɓK�p�����邽�߁A�K�p���P�\�����g���ɂ��Ă͗v�����s���B |
| �� |
�����Ԃɂ���ԘJ���́A�J���҂̌��N�ɉe����^����ƍl�����邱�Ƃ���A���ԊO�J���͏���J�����Ԃ߂������̂Ƃ��A���ԊO�J���̐ώZ���@�ɂ��ẮA�����E�x���̋�ʂȂ����Z���邱�ƂƂ���B |
�A�@���x����鎞�ԊO�J���ɂ���
| �� |
�����@�œw�͋`���Ƃ��ꂽ�u���x������i�����Ԃ�1�����̏ꍇ��45���ԁj���鎞�ԊO�J���͖@�芄�������闦�Ƃ���悤�w�߂邱�Ɓv�Ɋ�Â��A�@��ɒ���t���Ă���g���́A������30���̗v�����s���B |
�B�@��x�ɂɂ���
| �� |
�J���̑Ή��͖{�������Ŏx�������Ƃ������ł���Ƃ̍l�����Ȃǂ܂��A�����g���͌ʂɔ��f���邱�ƂƂ��A����I�ȑΉ��͋��߂Ȃ����ƂƂ���B |
�C�@�N���L���x�ɂ̎��ԒP�ʕt�^�ɂ���
| �� |
�L���x�ɂ͖{����J������P�ʂƂ��Ď擾������̂Ƃ̍l�����Ȃǂ܂��A�����g���͌ʂɔ��f���邱�ƂƂ��A����I�ȑΉ��͋��߂Ȃ����ƂƂ���B
�������A�E��j�[�Y�Ȃǂɂ�萧�x������ꍇ�ɂ́A���x�̉^�p��擾���тȂǂ��m�F���Ȃ�������̊g�������ȂǁA�T�d�ɑΉ����s�����ƂƂ���B |
(2)�@�N�ԑ����J�����Ԃ̒Z�k
�J���҂̐S�g�̌��N�͂��Ƃ��A���[�N�E���C�t�E�o�����X�̎����Ɍ����Ă��A�����ԘJ�����������A�����n�����������������ł�����Â��肪�K�v�ł���B�e�����g���́A�d�͑��A���Z�w�j�܂��A�N�ԑ����J������1800���ԒB�����߂����A��Ƃ̑Ή������߂�ƂƂ��ɁA�J�g��̂ƂȂ������g�݂��s�����ƂƂ���B
�@�@�J�����ԂɊւ���J�g���c�̏[��
| �� |
�N�Ԃ�ʂ����J�����ԂɊւ�����g�݂̃t�H���[��A���P���ׂ������ɂ��āA�J�g�̋��c��b���������s���A���艻�i�c���^�A�o���A�m�F�������܂ށj��}��ƂƂ��ɁA�����ԘJ�������Ɍ������J�g�s���v��̍���Ȃǂɓw�߂邱�ƂƂ���B�Ȃ��A���ׂẲ����g���́A����O�J�����Ԃ�N���L���x�Ɏ擾���ȂǁA�l�ʂ̘J�����Ԏ��тɂ��ăf�[�^�̊J�������߁A�������ƂɘJ�g�m�F���s�����ƂƂ���B |
�A�@�N�ԏ���J�����ԒZ�k�̎��g��
| �� |
�N�Ԃ̏���J�����Ԃ�2000���Ԃ��Ă�������g���́A�A�����Z���j�Ōf�����Ă���Œᓞ�B�ڕW�i2009�N�x���j�܂��A�x�������𑝂₷�Ȃǂ��ĔN�ԏ�����J�����Ԃ�2,000���Ԉȉ��ɂł���悤�v�����s���B |
�B�@����O�J�����Ԃ̍팸���̎��g��
| �� |
36����̓��ʏ����ɂ��āA�����ԘJ���h�~��J���҂̌��N��Q�h�~�̊ϓ_�ɗ������������s���B���̏�ŁA36���菅��̂��߂̎��ԊO�J���̊�{���[���ɂ��ĘJ�g�m�F���s���A�����ɐE����̎��m�O���}��B |
| �� |
���ׂĂ̑g�����̋x���J�����Ԃ��܂ގ��ԊO�J�����A1����45���Ԉȉ��ɗ}���邱�Ƃ���{�Ƃ��A���Ȃ��Ƃ��ߘJ���ɂȂ���Ƃ����P����100���ԁA�Ȃ�т�2�����A��80���Ԃ���ߏd�J���ɂȂ���Ȃ��Ɩ��^�c�����߂�B |
| �� |
�ߏd�J���ɌW����t�̖ʒk�w���ɂ��ẮA����80���Ԃ߂����ґS���Ɏ��{���邱�Ƃ���{�ɁA��45���Ԓ��ߎ҂Ō��N�ւ̔z�����K�v�Ȏ҂ɂ��Ă��A���̑ΏۂƂ��邱�Ƃ����߂�B |
| |
��80���Ԓ� |
��45���Ԓ��ߎ҂ŁA���N�ւ̔z�����K�v�Ȏ� |
| �@���̑Ώێ� |
��100���Ԓ��Ŕ�J�̒~�ς���
�i�\�o����j |
��80���Ԓ�100���Ԉȉ��ŁA��J�̒~�ς܂��͌��N��̕s������
�i�\�o����j |
��100���Ԓ��̎҂܂���2�����`6�����̕��ς���80���Ԃ����
�i�\�o�Ȃ��j |
| �@��㋁�߂���Ή� |
�ʐڎw�����m���Ɏ��{
�i�`���j |
�ʐڎw�����̎��{�ɓw�߂�
�i�w�͋`���j |
�Ώێ҂Ɋ܂߂邱�Ƃ��]�܂��� |
| �d�͑��A�̗v�� |
��t�ɂ��ʒk�w�������߂� |
�C�@�N���L���x�ɂ̎擾����̎��g��
| �� |
�J���҂̐S�g�̌��N���m�ۂ���ϓ_����A�N���L���x�ɂ̎擾�ڕW���A�d�͑��A���Z�w�j�́u�N��10���ȏ�v�Ƃ��A���ɁA�擾������5�������̑g�������Ȃ������Ƃ��߂����A�v��擾��A���擾�ȂǁA���Ԃɉ��������x�������߂�B |
| �� |
�N���L���x�ɂ̊��S�擾���T�˂ł��Ă���g���́A���N�x�t�^����15���ȏ��N��20���t�^�ƂȂ�܂ł̋Α��N���̒Z�k��v������B |
(3)�@������琬�x����
| �� |
����17�N����]�ƈ�301���ȏ�̊�Ƃɍ���E�͏o���`���t�����Ă����ʎ��Ǝ�s���v��́A������琬�x�������i�@���������镽��27�N�x���܂ł́A�P�̌v����Ԃ��I����Ă��A�܂����̍s���v������肵�͏o������K�v������B���̂��߁A���{�̃t�H���[���s���ƂƂ��ɁA���̍s���v�����Ɍ��������g�݂��s���B |
| �� |
300���ȉ��̊�Ƃł����l�̓w�͋`�����ۂ����Ă���A����101���ȏ�̊�Ƃ͕���23�N4������`��������邱�ƂɂȂ������Ƃ���A�@�̎�|�ɉ����ēs���{���J���ǂ֍s���v����o����悤���߂Ă����B |
�@�@�����玙�E���x�Ɩ@�ւ̑Ή�
���q����̊ϓ_����A�i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���d���Ǝq��Ă̗����x��������w���i���邽�߁A�j���Ƃ��Ɏq��ē������Ȃ��瓭�������邱�Ƃ��ł���ٗp�������邽�߁A�����@������21�N7��1���Ɍ��z����A����22�N6��30���Ɏ{�s�����B
����āA2006�N�x��5��O����c�iH19.8.3�j�Ŋm�F�����u�d�͑��A�@�d���Ǝ������̒��a�v�̍l��������{�Ƃ��āA�������e�܂����J�������A�ƋK���̉����E�����Ɏ��g�ށB
�Ȃ��A100���ȉ��̊�Ƃɂ����ẮA�ꕔ�̉������e�����z������3�N�ȓ��̐��߂Œ�߂���Ɏ{�s�����Ƃ����P�\�[�u���Ƃ��Ă��邪�A�E����Ԃ�j�[�Y��c�����A�K�v�ɉ����ē��Y�g���͗v�����s�����ƂƂ���B
�A�@���̑�
| �� |
�o�Y�A�q��Ă��E�����͂��߁A�P�g���C�Ҏx���ȂǁA�ƒ����n��Љ�ł̉Ƒ��I�ӔC���ʂ������߂̐��x�ɂ��āA�����E�[����}��ƂƂ��ɁA���x���p�̑��i�Ɍ����āA�J�g�̋��c��b���������s���A���x�擾��j�Q����v���̉����Ɏ��g�ށB���ɁA���Ɋւ��鐧�x�ɂ��ẮA���x���p�҂̑������݂��邱�Ƃ���A�E��j�[�Y��c�����A�[���Ɍ��������g�݂��s���B |
| �� |
�����āA�x�Ǝ҂̐E�ꕜ�A��̎x������A�������̐E��Ή����[���̊m���Ɍ����Ď��g�ށB |
5.�@�����ɂ킽���Ĉ��S�ł���J�������̊m��
(1)�@��N�ސE�Ҍp���ٗp���x�̐����E�[���̎��g��
��������Ҍٗp����@�ւ̑Ή���O�ꂵ�A��]�ґS����65�܂ł̏A�J���\�ƂȂ鐧�x�̎����Ɍ����A���x�̓_���E�������s���A���x���p�҂̓��������ɂȂ���ƂƂ��ɁA�E��S�̂̊��͌���ƂȂ鐧�x�\�z�Ɏ��g�ށB
������22�N4�����獂�N��Ҍٗp�m�ۑ[�u�̋`���Ώ۔N�64�Ɉ����グ����B
(2)�@�ސE�ꎞ�����x�̊m���E�����̎��g��
�@ �ސE�ꎞ�����x���m������Ă��Ȃ������g���́A������ƑސE���ϐ��x�Ȃǂ����p���āA�ސE�ꎞ�����x�̊m�����߂��������g�݂�i�߂�B
�@ �܂��A���x���m������Ă�������g���́A�d�͑��A�̃N���A�����ł���1,550���~�ȏ�̊m�ۂ��߂����B
(3)�@�ЊQ�⏞���x�̏[���̎��g��
�@ �d�͊֘A�Y�Ƃ̎Љ�I�g�����ʂ����d�ӂɂ����āA�]���ƂȂ����g�����̋Ɩ���ЊQ�⏞���x�́A�l���Ƃ������ɂ��ς����������l�ւ̕⏞�Ƃ����J�g���ʂ̗��O�������āA���ׂẲ����g���œd�͑��A�̃N���A����3,500���~�ȏ�i�Ɩ��㎀�S�E�L�}�ҁj�̕⏞�z���߂����B
7.�@�p�[�g�^�C���J���ғ��̑ҋ����P�̎��g��
�@ �������̓�ɉ���[�L���O�v�A���Љ�I�ȉۑ�ƂȂ��Ă��钆�A�p�[�g�^�C���J���ғ��̑ҋ����P�́A�d�͊֘A�Y�Ƃœ����ґS�̂̒�グ��}����̂ƈʒu�t���A�u�d�͑��A �p�[�g�^�C���J���ғ��̋ύt�ҋ��ɂނ������g�ݎw�j�v�Ɋ�Â��A�����J���҂̎��_����A�p�[�g�^�C���J���ғ��̘J�������S�ʂɘj��ҋ����P�̎��g�݂�i�߂�B
| �� |
�e��Ƃ��ٗp���Ă���p�[�g�^�C���J���ғ��̘J���������ɂ��āA���Ԕc�����s���������ŁA���Y�҂���јJ�g�̎O�҂ŋ��ʔF����}��A����̘J����������Ƒg�D���Ɍ��������g�݂ɂȂ���B |
| �� |
���Ј��Ɠ������ׂ��p�[�g�^�C���J���ғ��̐��Ј����܂��͐��Ј����Ɍ��������[�������s���B |
| �� |
���������グ�ɂ��ẮA�Œ�����v�����890�~��ڎw�����v���܂��͗v�����s���B�Ȃ�890�~���Ă���ꍇ�ɂ����Ă��A10�~�ȏ�̈����グ��v���܂��͗v�����s���B |
| ���Ј��Ɠ������ׂ��p�[�g�^�C���J���ҁ@���@�Ɩ����e����ѐӔC�A�l�ފ��p�̎d�g�݂�
�^�p�����Ј��Ɠ����ŁA���Ј��Ɠ�������J�����Ԃœ����A�_����Ԃ������܂��͔����X�V
�̎ҁB |
| �� |
���Ј��Ƃ͈قȂ铭���������Ă���p�[�g�^�C���J���ғ��ɂ��Ă��A�Ɩ����e��J�����ԓ������Ă��A�����̈����グ�A�ꎞ���̎x���A�ʋΔ�̎x���A�c���x�ɓ��̐����A���̑������������x���ɂ��Đ��Ј��Ƃ̋ύt�ҋ��Ɍ��������g�݂��s���B |
| �� |
���������グ�ɂ��ẮA�Œ��������z��890�~���߂����A���N�x�̒n��ʍŒ���������グ�z�i����10�~�j�Ȃǂ܂����v���܂��͗v�����s���B
�Ȃ��A890�~���Ă���ꍇ�ɂ����Ă��A���l�̍l�����Ɋ�Â������g�݂��s���B |
7.�@�Љ�I�ȉۑ�ւ̑Ή�
| (1) |
�ٔ������x�Ɋւ��戵���̑Ή�
�ٔ����@�ɂ��o�쓙�����߂�ꂽ�ꍇ�̎戵���ɂ��āA���������L�����������߂�ƂƂ��ɁA���̑��̎�舵���Ɋւ���J������̒����Ɏ��g�ށB�Ȃ��A�������s�g�Ɋւ��ĘJ�������������Ă���g���ɂ��Ă��A�ٔ����@�̓K�p�ɂ��āA�J�g�m�F���s���B
�i���j�ٔ����@�́A����21�N5������{�s�ρB |
| (2) |
�������x�v���ւ̎��g��
�A���̐������x�v���ɂ��āA�J���҂̈��S�E���肵�������̊m�ہA�����ȎЉ�̎������߂����āA�A���̒��j�Y�ʂƂ��Ă̐ӔC�Ɩ������ʂ������߁A�ϋɓI�ɎQ�悵�Ă����B |
8.�@���������g���̌����i�����̎��g��
�@ ���������g���̒���������J�������̒�グ��}�邽�߁A�d�͑��A�E�\�����A�́A�����g���̗v���č���̒i�K����A���̍l�����Ɋ�Â��Ď��g�݂���������B
| �� |
�������Ԕc���������{�A�d�͑��A�~�j�}�������ɖ��B�A�����J�[�u�ێ������m�ۂł��Ă��Ȃ����̉����g�����i�荞�݁A�d�_�w���œK�Ȏx�����s���B |
| �� |
�����g���x�����f���v�������쐬���A�����g���̎��Ԃ����܂��ċ�̓I�ȓW�J��}��B |
| �� |
�H�����̎E�����Ԃɑ��݂���u����W�v���A�t�����ɉe����^���邱�Ƃ��Ȃ��悤�A�e�\�����A�ŊJ�Â����J�g���k��Ȃǂ����p���āA�����𐮂��Ă����B |
|
VI.�@�i�ߕ�
�@ �A��2010�t�G���������̐i�ߕ��܂�����ŁA�d�͑��A�E�\�����A�E����E�����g���̘A�g���\���ɐ}��Ȃ���d�͑��A�̑��͂����W���Ď��g�ނ��ƂƂ���B
�@
�܂��A�A���̊e�틤���ƘA�g��}��Ȃ���A�L�������Ɍ����Ď��g�ށB
1.�@�v�����̒�o
�@ �ٗp����Ɋւ���\�����ꂨ��їv�����̒�o�ɂ��ẮA����22�N2��22����v�����Ƃ��āA��ĂɎ��{����B�������A����ɂ���ėv���ւ̑Ή�������g���́A�x���Ƃ�3�����܂łɗv������B
2.�@�����i�̐�
�i1�j���̐�
| �� |
�d�͑��A�́A���������i�ψ����ݒu���A�\�����A�E�����g���̌����i�Ɍ����ĐϋɓI�Ɏx���E�������s���B |
| �� |
�\�����A����ѕ���́A�����i�ψ����ݒu���Ċe�X�̐ӔC�̐����m�����A�����g���̑������L���ȉ����Ɍ����ĐϋɓI�Ɏx���E�������s���B |
| �� |
�����g���́A�\�����A�╔��ƘA�g��}��A���́E��������{�ɐ��͓I�Ɍ���W�J����B |
�i2�j���̑��i
| �� |
���������i�ψ���́A���܂������g���̌���L���ɓW�J���邽�߁A�u�����̐i�ߕ��v�M����B�����āA�A���������������M������j�ɂ��āA�d�͑��A���̎��Ԃ����܂��������ŁA���������g���̒��������グ�����L���ɐi�߂���悤�A���l�ɔ��M����B |
| �� |
�\�����A�́A�����g���̌����i��}�邽�߁A������]�[����݂��A�\�����A�Ɖ����g������̂ƂȂ�������W�J����B���ɁA�����g���̌����i�Ɍ����Ďx������������B |
| �� |
�t�G���������ɌW�����́A���𑣐i���邽�ߓK�X���M���Ă����B |
3. ��������
�@ ���̃��}��́A�A���̉������i�]�[���܂��A3�����{����{�ɒx���Ƃ�4�����܂ł̉������߂����B |
|

