
|
 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
�� �d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ�(����3)
����30�N4��12��
��3�������i�ψ��� �d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ�(����3)
�@�d�͑��A�����̊e�g���́A��Q�������i�ψ���Ŋm�F�����u�d�͑��A2018�t�G�������� �i�ߕ�(���̂Q)�v�܂��A�S��11�����݂�226�g�����v�������o���A��s����e������͂��߂Ƃ���94�g���������A�ܗ^�E�ꎞ���A�J��������蓙�̂����ꂩ�̍��ڂɂ��ĉ����Ɏ����Ă���B
�@�����ɂ��ẮA�}�N���̊ϓ_�ɉ����A���Y���̌�����Ƃ̎����I���W�ɕs���Ȑl�ނ̈ێ��E�m�ۓ��������Ƃ��ĔS�苭������W�J�������ʁA��������z�͍�N������X���ɂ���ق��A�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��Ă͈���x����g�����̍v���E�w�͓���w�i�Ɍ���W�J���A���z�ɑ���������z���l�������g��������ق��A�����̑g���ō�N�̐���������ȂǁA�d�͊֘A�Y�ƑS�̂́u��グ�E��x���v�A�u�i�������E�����v�ɂȂ��鐬�ʂƂȂ��Ă���B �@�㑱��������g���́A��s����g�����O�i���̂�������Ɏ����Ă���܂��A�\�����A�E�Ǝ�ʘA����E�d�͑��A�Ƃٖ̋��ȘA�g�̂��ƁA�v����|�ɉ������������}���悤�A�Ō�܂ŔS�苭������W�J���Ă������ƂƂ���B �L
1�D�S�̂̉�����
(1)���������グ
���A���̊T����
�@���@4��6���Ɍ��\���������̉����ɂ��A���ϒ��������ʼn������o����2,566�g���̂����A�������蕪�����m�ȑg��1643�g���̒菸�������{�������蕪�͉��d���ς�6,800�~�i2.30%�j�A���̂����������蕪�͉��d���ς�1,674�~�i0.55%�j�ƂȂ��Ă���A�z�E���Ƃ��ɍ�N�������̐����������Ă���B
�@�܂��A300�l�����̒����g���ł́A�������蕪�����m�ȑg��885�g���̒菸�������{�������蕪�͉��d���ς�5,606�~�i2.19%�j�A�������蕪�͉��d����1,570�~�i0.62%�j�ƂȂ��Ă���A�z�E���Ƃ��ɍ�N�������̐����������Ă���B ���d�͑��A�̊T����
�@���@4��11���ɏW�v���������̉����́A�����Ɏ�����72�g���̂����A�������蕪���l�������̂�27�g���ł���A�l��������37.5%�ƂȂ��Ă���B
�@���@�O�N��r���\��72�g���ɂ�����������蕪�́A���d���ς�471�~�i0.15%�j�ƂȂ��Ă���A�z�E���Ƃ��ɍ�N�̐����i316�~�A0.11%�j�������Ă���B �@�܂��A300�l�����̒����g��30�g���ɂ�����������蕪�́A���d���ς�534�~�i0.20%�j�ƂȂ��Ă���A ���E�z�Ƃ��ɍ�N�̐����i317�~�A0.12%�j��S�̕��ρi471�~�A0.15%�j�������Ă���B (2)�ܗ^�E�ꎞ��
���A���̊T����
�@4��4���Ɍ��\�����ꎞ���̉����ɂ��A�N�Ԍ����͉��d���ς�5.00�����i1,616,773�~�j�ƂȂ��Ă���A�����ō�N�������̐����i4.94�����A1,618,190�~�j�������Ă���B
���d�͑��A�̊T����
�@���@4��11���ɏW�v�����ܗ^�E�ꎞ���̉����́A�����Ɏ�����62�g���̂����A�N��4�������l�������g����45�g���ł���A�l��������72.6%�ƂȂ��Ă���B
�@���@�O�N��r���\��61�g���ɂ�����N�Ԍ����͉��d���ς�4.23�����i1,479,175�~�j�ƂȂ��Ă���A�����E�z�Ƃ��ɍ�N�̐����i4.10�����A1,429,533�~�j�������Ă���B (3)�������̌�������
�@��s����e������͂��߂Ƃ��鑽���̑g���ł́A�����ԘJ���̐������͂��߂Ƃ��铭�����̌�������A���l�ȓ��������ł���J�����̐����Ȃǂ̕K�v���ɂ��ĘJ�g�̋��ʔF���ɗ����Ƃ��ł��Ă���B���̂����ŁA���ԊO�J���̏���K���̖@��������������36����̌��x���Ԉ���������Ζ��ԃC���^�[�o�����x�̓����A�玙�E���E���Â��K�v�Ȏ҂�ΏۂƂ����Z���ԋΖ����x�̓����E�����ȂǁA�e�g���̐E����Ԃ܂����Ή���}���Ă���B
2�D����̐i�ߕ�
�@����̌��ɂ������ẮA�{���܂łɐ�s���ĉ����Ɏ������g�������o�����O�i���@����������ő���������A��2�������i�ψ���Ŋm�F�����u�d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ�(����2)�v�Ɋ�Â��A�㑱��������g���A�\�����A�A�d�͑��A����ۂƂȂ��Đ��͓I�ɒǂ��グ��}��ƂƂ��ɁA��N��������ł������������߂����A4�����̉����Ɍ����čő���̎��g�݂�}����̂Ƃ���B
�ȏ�
���d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ�(����2)
����30�N3��6��
��2�������i�ψ��� �d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ�(����2)
�@�d�͑��A�����̊e�g���́A��1�������i�ψ���Ŋm�F�����u�d�͑��A2018�t�G���������̐i�ߕ�(����1)�v���ӂ܂��A���̑�����2��20���ɗv�����s���Ĉȍ~�A�\�����A�E�d�͑��A�ƘA�g��}��Ȃ��琸�͓I�Ȍ���W�J���Ă���B
�@���������ɂ����ẮA�d�͊֘A�Y�Ƃ������ɂ킽�茒�S�ɔ��W�����Ă������߁A�d�͑��A�ɓ����҂��ׂĂ̌o�ϓI�E�Љ�I�n�ʂ̌����}��A�g�����Ƃ��̉Ƒ��̈���E���S�A��肪���E���������������ł��閣�͂���Y�Ƃ̍\�z�Ɍ�����������i�߂Ă����K�v������B �@���̂��߁A�o�ς������ɐ��ڂ��Ă��邱�Ƃ�J�g�ɂ���āu���������v���s�v��v�����ӂ��ꂽ���Ɠ����ӂ܂��A�o�c���ɁA���������グ���͂��߂Ƃ���u�l�ւ̓����v��ϋɓI�ɑ����ƂƂ��ɁA�E����n�m����J�g�ɂ���̓I�ȓ������̌�������i�߂邱�ƂŁA�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂̖����ւ̊��͂ɂȂ��Ă����ׂ��ł���B �@����̌��ɂ������ẮA����������{�F�����ēx���L����ƂƂ��ɁA�A���̓��������ӂ܂��A�����g���E�\�����A�E�d�͑��A����̂ƂȂ�A�v���̎�|�ɉ�����������}���悤�A�͋������𐄐i���Ă������ƂƂ���B �L 1�D�v������o����ѐ\������ɂ���
�@�v�������̒�o�Ɏ����Ă��Ȃ��g���́A�\�����A�ƘA�g��}��A�u�d�͑��A2018�t�G�����������j�v���ӂ܂��A��������O���ɒx���Ƃ��R�����܂łɗv���������o����B
2�D��̓I�Ȏ��g�݂ɂ���
(1)���������グ
�@�����ɂ��ẮA�Α��N���ɔ����Z�p�E�Z�\�̏K�n�ɑΉ���������J�[�u�ێ����̊m�ۂ͂��Ƃ��A�u�o�ς̎����I�����v�Ȃǃ}�N���̊ϓ_����̏�������A�Y�Ƃ̌��S�Ȕ��W�ɕs���Ȑl�ނ̈ێ��E�m�ۂ�Y�����㓙�Ɏ�������������グ�A�u�i�������v�u�����v�Ȃǂɂ��u��グ�E��x���v�̎����̂��߁A�v���l���ɂ�����������������B
�@�Ƃ�킯�A�g�D�l����300�l�ȉ��̉����g���ɂ����ẮA�����������Љ���������ɂ��邱�Ƃ��ӂ܂��A�u�i�������v�Ɍ��������g�݂����͂ɐ��i����B (2)�ܗ^�E�ꎞ��
�@�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�N�Ԓ����̈ꕔ�Ƃ��Ĉ��肵���������x���鐶���������Ƃ��ĔN��4�������Œᐅ���Ƃ��A�g�����̌o�c���{��ւ̍v���⌜���ȓw�͂ɕ邽�߁A�K���Ȑ��ʔz���̊ϓ_�ɗ����āA��N���т���̏�ς݂�}��ׂ��S�苭������W�J����B
(3)�d���Ǝ������̒��a���}�����̐���
�@�N�ԑ����J�����Ԃ̒Z�k�́A�S�g�̌��N�̕ێ��E���i��A�ƒ�ɂ���������A�n��Љ�Ƃ̂Ȃ���ȂnjX�l�̐����Ǝd���̒��a����������݂̂Ȃ炸�A���l�Ȑl�ނ�����ł���������̂��߂Ɍ������Ƃ̂ł��Ȃ��d�v�Ȏ��g�݂ł��邱�Ƃ���A��̓I���ʂ�������悤������������B�Ƃ�킯�A�����ԘJ���́A�ߏd�J���ɂ��̒��s�ǂ���^���w���X�s���A�ߘJ���Ƃ��������������N�����v���ƂȂ邱�Ƃ���A�J����@������������������s�I�Ȏ��g�݂�ϋɓI�ɐ��i����B
�@�d���ƈ玙�E���E���Â̗����x�����x�̐����E�[���ɂ��ẮA�M�d�ȋZ�p�E�Z�\��L����l�ނ��玙�E���E�a�C���Â𗝗R�ɗ��E���邱�Ƃ�h���A���������邱�Ƃ��ł���E������\�z���邱�ƂŁA�{�l�����łȂ��A��Ƃ̎����I�Ȑ����Ɏ����邱�Ƃ��ӂ܂��A�O�i���}����悤������������B (4)�N�������S�ł���J��������J�����̊m��
�@�Y�ƑS�̂Ől�ނ̈ێ��E�m�ۂ��d�v�ۑ�ƂȂ�Ȃ��A���N��ҁA�����A�Ⴊ���҂��d���ɂ�肪���E�������������ƂƂ��ɁA���S���ē��������邱�Ƃ��ł���J��������J�����̊m�ۂɌ����Č�����������B
�@�ސE�ꎞ������эЊQ�⏞���x�̐����E�[���̎��g�݂ɂ����ẮA�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂ɉۂ���ꂽ�Љ�I�g�����ʂ��������Ă��邱�ƂɓK�ɕ邱�Ƃ�A�g�����Ƃ��̉Ƒ��̈��S�E����ɂȂ���ϓ_����A�O�i���}����悤������������B (5)�K�J���҂̑ҋ����P
�@�p�[�g�^�C���J���҂��͂��߂Ƃ���K�J���҂̑ҋ����P�̎��g�݂ɂ����ẮA�J���������ɂ��Ď��Ԕc�����s���A���Y�҂���јJ�g�̎O�҂ŋ��ʔF����}��ƂƂ��ɁA�J���_��@���̖@�����ɓK�ɑΉ�����悤���g�ށB���̂����ŁA����J���E��������Ɍ������@�������\�肳��Ă��邱�Ɠ����ӂ܂��A�ҋ����P�Ɍ����O�i���}����悤������������B
3�D�����i�ɂ���
(1)�d�͑��A
�@�d�͑��A�́A����`������щ����g���ɍL���g�y���ʂ��y�ڂ��ϓ_����A�e���������g���̌��ɂ��āA�e�\�����A�Ƌ��L��}�邱�ƂƂ��A�A����̏t���Ɋւ�����j���ɂ��Ă��K�������s���Ă����B
�@�܂��A�����g���̌����L���ɐi�߂���悤�A���������������Ԕc���E���͂�o�c���͂̎x�����s���B (2)�\�����A
�@�\�����A�́A�����i�ψ����K�X�J�Â��A������]�[���̐ݒ�⎞�X�����ʓI�ȃI���O�̎��{�ȂǁA�����g���̑������L�������Ɍ����Č����i��}���Ă����B
�@�܂��A������q���Ă�������g���ɑ��ẮA�d�͑��A�ƘA�g���Ȃ���ʑΉ����܂ߎx�����s���B (3)�����g��
�@�����g���́A�\�����A��Ǝ�ʘA����ƘA�g��}��A��s����g���⓯�Ƒ��Ђ̌��ɂ��Ĕc������ƂƂ��ɁA������]�[�����������Ȃ���A���ʓI�Ȍ�������z�u����ȂǁA�v���̎�|�ɉ������������}����悤���͓I�Ɍ���W�J����B
4�D����̓����ɂ���
(1)��������
�@3�����̉������߂����čő���̎��g�݂��s���B
�@�܂��A3�����̉���������ꍇ�ł����Ă��A��N���������������߂������ƂƂ��A�x���Ƃ�4�����̉����Ɍ����ĉs�ӌ�����������B (2)��c�J��
�@��1����A���ӔC�҉�c��3��28��(��)�A��3�������i�ψ����4��12��(��)�ɊJ�Â���B
�ȏ�
�� �d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ��i����1�j
����30�N2��15��
��1�������i�ψ��� �d�͑��A2018�t�G���������@�i�ߕ��i����1�j
�@�d�͊֘A�Y�Ƃ������ɂ킽�茒�S�ɔ��W�����Ă������߂ɂ́A�Z���E�������I�Ȋϓ_����A�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂��ׂĂ̌o�ϓI�E�Љ�I�n�ʂ̌����}��ƂƂ��ɁA�g�����Ƃ��̉Ƒ��̐����̈���E���S�A��肪���E���������������ł��閣�͂���Y�Ƃ̍\�z�Ɍ��������g�݂��p�����Ă������Ƃ��K�v�Ȃ��Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B
�@�d�͑��A2018�t�G���������ł́A���S�ȎY�Ƃ̔��W�̊�ՂƂȂ�l�ނ̈ێ��E�m�ہA�Z�p�E�Z�\�̈ێ��E�p�����̒����Ȏ����Ɍ����A���������グ���͂��߂Ƃ���u�l�ւ̓����v�𑣂��ƂƂ��ɁA�E����n�m����J���g���ɂ�铭���҂̂��߂̓������̌�������i�߂邱�ƂŁA�����ւ̊��͂ɂȂ��Ă������Ƃ��d�v�Ƃ̔F���̂��ƁA�d�͑��A�P�W�t�����j�Ɋ�Â��A�����g���E����E�\�����A�E�d�͑��A�̘A�g���������A�ȉ��̂Ƃ�����𐄐i���Ă������ƂƂ���B 1�D���O���� �\�����A�A�����щ����g���́A�d�͑��A18�t�����j�Ɋ�Â��A�v�����̒�o��\�����ꂨ��і{�i�I���Ɍ��������O�����ɖ��S�������B �܂��A�������L���ȉ������߂����Đ��͓I�Ȍ����W�J�ł���悤���̐����m������B 2�D�v������o����ѐ\������ �v�����̒�o����ѐ\������ɂ��ẮA����30�N2��20��(��)�Ɉ�Ď��{����B �������A����ɂ���ėv���ւ̑Ή�����������g���́A��������O���ɒx���Ƃ��R�����܂łɎ��{����B 3�D�����i �Z�@�d�͑��A��̘A�g����̋��L�Ȃ�тɌ����i�̋�����}�邽�߁A�����i�̐����m�����A�����g���̌����x������B �Z�@�d�͑��A�́A���������g�����͂��߂Ƃ���e�����g���̌����L���ɐi�߂���悤�A�p���I�Ȓ������Ԕc���E���͂���ьo�c���͂̎x�����s���ƂƂ��ɁA���̎咣�_�Ȃǂ̏��M���Ă����B �Z�@�\�����A�́A�S�̏�̋��L�⎞�X�����ʓI�ȃI���O�̎��{�ȂǁA�����g���̑������L���ȉ����Ɍ������x�����s���B �Z�@�����g���́A�\�����A���ݒ肷�铝����]�[����O���Ɍ�������g�ݗ��āA�L�������Ɍ����Č��̑��i��}��B 4�D���ʂ̓��� ��2�������i�ψ����3��6��(��)14��00������J�Â��邱�ƂƂ��A����ȍ~�̓����ɂ��ẮA�����g���̌��A�A���⑼�Y�ʂ̓����Ȃǂ𑍍����Ă��Č��肷��B 5�D���̑� �Z�@�t�G���������Ɋւ�����ɂ��ẮA�K�X�2018�t�G�����������ɂ�蔭�M����B �Z�@�A���̃C���t���E���v�����A����c�⒆�������Ƃ̘A�g��}��A�A���̒��j�Y�ʂƂ��Ă̖����܂��A�����g���̒�グ�Ɏ�������g�݂�i�߂�B �ȁ@�� �� �d�͑��A2018�t�G�����������j������I(2018.2.15)
�@�d�͑��A�́A2��15��(��)�ɓ����s���ɂ����āA2017�N�x��1���ψ�����J�Â��A�d�͑��A2018�t�G���������̕��j�����肵���B �ݖ{���������  �c���߂钆���d�͑��A�@�ߓ������ψ�  2018�t�G�����������j�ɂ��Ē�N����@�R�e�J������ǒ�  �ݖ{��i���j�ƕl��悵�ӂݎQ�c�@�c���i���j�Ə��т܂����Q�c�@�c���i�E�j 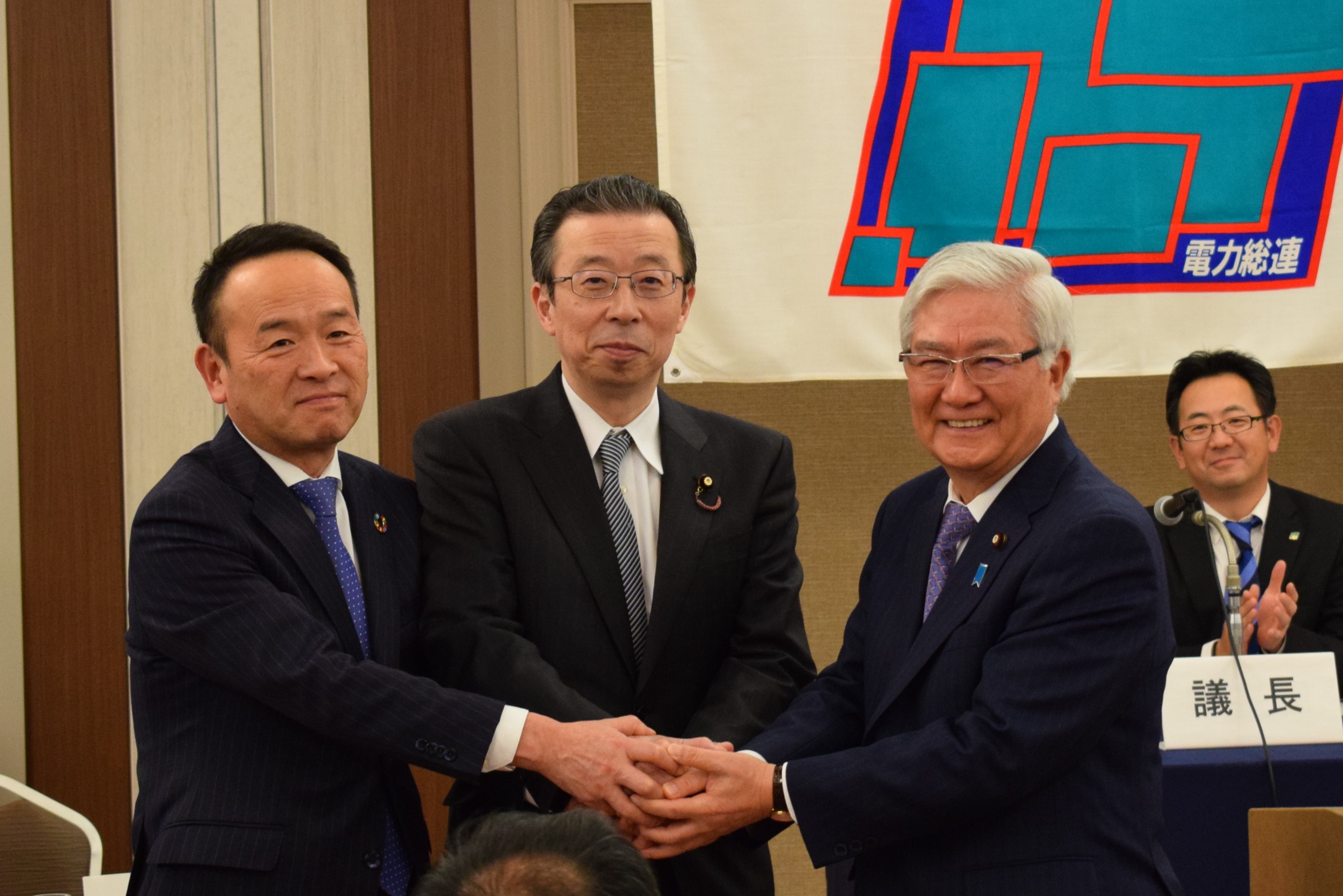 �����ψ���i 
����30�N2��15��
��1���ψ��� �d�͑��A2018�t�G�����������j
I.�@�͂��߂�
�A���́A2018�t�G�����������j�ɂ����āA�����q����A�J���͌����Ƃ����o�ρE�Љ�̍\���ω���A�Z�p�v�V�̉������ւ̑Ή��Ȃǂ̕ω����҂���Ȃ��ɂ����āA�Љ��o�ς������I���p���I�ɐ��������邽�߂ɂ́A�u��ۓI�ȎЉ�̍\�z�v�u�l�I�����̑��i�v�u�f�B�[�Z���g�E���[�N�̎����v���K�v�Ƃ̔F���������Ă���B ���̂����ŁA17�t������f���Ă����u�o�ς̎����I�����v���������邽�߁A���ׂĂ̓����҂́u��グ�E��x���v�u�i�������v�ɂ��p�����������̌���Ƃ���ɔ�������̊g�����������ƂƂ��ɁA������ƘJ���҂�K�J���҂̏������P�Ɍ����A�u���Ǐ]�E��������̒E�p�v�u�T�v���C�`�F�[���S�̂̕t�����l�̓K�����z�v�̗�����p���E�蒅�E�O�i��������g�݂�i�߂�Ƃ��Ă���B �܂��A�E����n�m����J�g�ɂ���Ē����ԘJ���̐������͂��߂Ƃ��铭�����̌�������i�߂�ƂƂ��ɁA���K�J���ҁE�K�J���҂��킸�A�X�l�̏�j�[�Y�ɂ��������l�ȓ�������I���ł���d�g�݂𐮂��邱�ƂŁA���ꂼ��̔\�͂����߁A����ɂ���Đ��ݏo���ꂽ�J���̎��I���㕪�ɉ������K���ȏ������m�ۂ��邱�Ƃ��K�v�Ƃ��Ă���B �d�͑��A2018�t�G���������ł́A�A��2018�t�����j���芪������܂��A�u�o�ς̎����I�����v�̎����Ȃǃ}�N���̊ϓ_����̏����̌����A�d�͊֘A�Y�Ƃ̌��S�Ȕ��W�ɕs���Ȑl�ނ̈ێ��E�m�ہA�o�c�������ւ̍v���E�w�͂ɕ邱�Ɠ���ړI�ɁA��������̈����グ�Ɍp�����Ď��g�݁A�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂́u��グ�E��x���v�������߂����B�Ƃ�킯�A�g�D�l����300�l�ȉ��̉����g���ɂ�������������͎Љ���������ɂ��邱�Ƃ���A�d�͊֘A�Y�Ƃ̌��S�Ȕ��W�ɕs���Ȑl�ނ̈ێ��E�m�ہA�Z�p�E�Z�\�̈ێ��p���ɂ��e�����y�ڂ����Ƃ̂Ȃ��悤�A�u�i�������v�𐄐i����B ���킹�āA�����҂̗���ɂ������������̌�������N�Ԓ����̈����グ�ƂƂ���18�t���ɂ�������g�݂̒��ƈʒu�Â��A�d�͊֘A�Y�Ƃœ����҂���ߘJ���E�ߘJ���E���N�������Ȃ����Ƃ͂��Ƃ��A���N��Q���R�h�~���̊ϓ_����A�����ԘJ�������ւ̎��g�݂������������͂ɐ��i����ƂƂ��ɁA�玙�E���E���ÂƂ��������C�t�C�x���g�ɉ��������l�ȓ������̎����ȂǁA�d���Ǝ������̒��a���}������̐����A���Ј��ƔK�J���҂̋ϓ��E�ύt�ҋ��Ɍ��������g�ݓ���i�߂�B ���g�݂ɂ������ẮA�g�����Ƃ��̉Ƒ��̐����̈���E���S�A��肪���E���������������ł��閣�͂���Y�Ƃ̎����Ɍ����A�����g���E�\�����A�E�d�͑��A���L�@�I�ȘA�g��}�邱�ƂŁA������ʂ�������悤�A�g�D�̑����͂��ő�������������g�݂�i�߂Ă������ƂƂ���B II�D�o�ώЉ�̏
���@���{�o�ϑS�ʂ̓����ɂ��ẮA1���̌���o�ϕi1��19�����t�{���\�j�ɂ����āA�i�C���f��O���������C�����A�ɂ₩�ɉ��Ă���Ƃ��A��s���ɂ��ẮA�ٗp�E�������̉��P�������Ȃ��ŁA�e�퐭��̌��ʂ������āA�ɂ₩�ȉ��������Ƃ����҂����Ƃ��Ă���B ���@2017�N7�`9�����̎l�����ʂ̎���GDP�������i12��8�����t�{���\�A2������l�j�͑O����{0.6���i�N�����Z�{2.5���j�ƂȂ��Ă���A7�l�����A���Ńv���X�������ێ����Ă���B �@�@�܂��A2017�N�x�̎���GDP�������ɂ��ẮA���{��s�i1��23�����\�j���{1.9���Ƃ��Ă���ق��A����41�@�֕��ρi1��16�����\�j�́{1.88���Ɨ\�����Ă���B ���@��Ƃ̎��v�ɂ��ẮA1���̌���o�ϕi1��19�����t�{���\�j�ɂ��A��Ǝ��v����ыƋ����f�Ƃ��ɉ��P���Ă���B ���@�����ɂ��ẮA12���̏���ҕ����w���i1��26�������Ȍ��\�j���A�����w���őO�N������1.0���㏸�A���N�H�i�����������w���őO�N������0.9���㏸���Ă���B �@�@�܂��A2017�N�x�̏���ҕ����w���i���N�H�i�����������w���j�Ɋւ��ẮA���{��s���{0.8���i1��23�����\�j�A����41�@�֕��ρi1��16�����\�j���{0.66���Ɨ\�����Ă���B �@�Ȃ��A���{��s��7��20���J�Â̋��Z�����ɂ����āA�����㏸�ڕW�i2���j�̒B���������u2018�N�x����v����u2019�N�x����v�ɐ摗�肵�����Ƃ�����A���̓����𒍎�����K�v������B ���@�ٗp��ɂ��ẮA12���̊��S���Ɨ��i1��30�������Ȍ��\�j��2.8���ƂȂ�A�����������S�ٗp�̐����ɂ���B�܂��A2017�N�x�̊��S���Ɨ��Ɋւ��ẮA����41�@�֕��ρi1��16�����\�j��2.8���Ɨ\�����Ă���B �@12���̗L�����l�{���i1��30�������J���Ȍ��\�j�́A1.59�{�ƂȂ��Ă���B���킹�Ă��ׂĂ̓s���{����1�{����ȂǁA�����Ɍٗp��̉��P���i��ł���B �@�܂��A����Z�ρi12��15�����{��s���\�j�ɂ��A�ٗp�l���̉ߕs������\���u�ٗp�l���c.�h�v�͑S�K�͑S�Y�ƍ��v�́u�ŋ߁v����31�A�u��s���v����33�ł���A�l��s���������ɂȂ��Ă��邪�A�Ƃ�킯������ƑS�Y�ƌv�ɂ����ẮA�u�ŋ߁v����34�A�u��s���v����39�ƂȂ��Ă���A���������[���ƂȂ��Ă���B ���@���{�́A�����{��k�Ђ���̕����E�n������ьF�{�n�k����̕����E�����Ɍ����Ď��g�ނƂƂ��ɁA�f�t������̒E�p���m���Ȃ��̂Ƃ��A�o�ύĐ��ƍ������S���̑o�����Ɏ������Ă����Ƃ��Ă���B���̂��߁A�u�o�ύ����^�c�Ɖ��v�̊�{���j2017�v�A�u�K�����v���{�v��v�A�u�j�b�|���ꉭ������v�����v���𒅎��Ɏ��s����Ƃ��Ă���B �@�Ȃ��A10��26���ɊJ�Â��ꂽ�o�ύ��������c�ł͌o�ϊE�ɑ��āA5�N�A���̒��グ�v�����s���Ă���B �@�܂��A���J�g���Q�悷��u���������v������c�v���J�Â��A2017�N3���ɂ́u���������v���s�v��v�����肵���B���̂����ŁA�J�������R�c��ł̘_�c���e�܂��A�����ԘJ���̏���K���@�Ă̂ق��A���x�v���t�F�b�V���i�����x�̑n�ݓ����܂�2015�N�J����@�����@�ē�����{���������������v�֘A�@�Ă�����֑�����o����Ƃ��Ă���B ���@�o�c�A�́A2018�N�Ōo�c�J���������ʈψ���i1��16�����\�j�ɂ����āA�f�t������̊��S�ȒE�p�ƌo�ς̍D�z�̂���Ȃ�g��Ɍ����Ē��������グ�̃������^���̈�w�̋����ɓw�߂�Ƃ��Ă���B III�D�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪���
1�D�o�c�� ���@�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪����ɂ��ẮA�d�̓V�X�e�����v�ɔ���2016�N4��������{���ꂽ�d�͏����S�ʎ��R���ɉ����A2017�N4������̃K�X�����S�ʎ��R���ɂ��A����ʓd�C���Ǝ҂⋌��ʃK�X���Ǝ҂ɂƂǂ܂炸�A�V�K�Q�����Ǝ҂��܂ރG�l���M�[�֘A��ƊԂ̋����͂��������������Ă���B�d�͊֘A�Y�Ɗe�Ђ́A��������������������߂ɁA�l�X�Ȍo�c��������������{���Ă���ق��A�O���[�v��ƂƂ̖������S���������܂߃O���[�v��̂ƂȂ������g�݂�i�߂Ă���B����ɂ͈ꕔ�ɂ����ăO���[�v�̘g���z������Ƃ̍ĕ҂��s���Ă���B ���@�G�l���M�[��{�v�挩�����̍s����A���������ɂ����錴�q�͎��Ƃ̊������Ɋւ��铮���A2050�N�Ɍ������������ʃK�X�팸�̒����ڕW�̂�����A�X�}�[�g���[�^�[�����̐i���ɔ������ۑ���͂��߂Ƃ��āA�d�͊֘A�Y�Ƃ̎��Ɖ^�c��J�����A�ٗp�ɉe����^����\���̂���ۑ肪�R�ς��Ă���B�܂��A�Y�ƊE�S�̂ɖڂ�������A��4���Y�Ɗv���Ƃ�����IoT�iInternet of Things�A���m�̃C���^�[�l�b�g�j�A�r�b�O�f�[�^���p�A�l�H�m�\�iAI�j���̋Z�p�v�V�ɂ���āA���Ɗ��⓭���������I�ɕω�����\��������A�����̓������������Ă����K�v������B ���@���q�͔��d���̍ĉғ��ɂ��ẮA2018�N1�����݁A�������^���q�F�iPWR�j�v�����g5��ĉғ����ʂ����Ă���ق��A��N12���ɂ͓����d�͔��芠�H���q�͔��d��6�E7���@�ɂ����ĕ������^���q�F�iBWR�j�Ƃ��ď��߂Č��q�F�ݒu�ύX���\���ɑ���R�����ʂ��܂Ƃ߂��R���������������ȂǁA�ĉғ��Ɍ��������g�݂������ɐi�߂��Ă���B����ŁA�����̌��q�͊֘A�{�݂ɂ�����V�K����ɌW��K�����R���̒������Ȃǂɂ��ˑR�Ƃ��čĉғ��̓����͕s�����ȏƂȂ��Ă���B�܂��A�ĉғ����Ă��锭�d���ɂ��Ă��i�@���X�N������Ă���B ���@�d�͊֘A�Y�Ɗe�Ђ̌o�c���ɂ��ẮA���Ԑݔ������̎��������̓����ɉ����A�{�i�I�Ȑk�Е����Ⓦ���I�����s�b�N�E�p�������s�b�N�֘A���v�Ȃǂɔ����ʂ������X���Ő��ڂ���Ȃ��A�����ȋƎ�E�n�悪�������ŁA�V�K���Ǝ҂̎Q�����͂��߂Ƃ��ċ������̌�����J���͕s�����ɋN������J����̑����Ȃǂɂ��A��芪�������������𑝂��Ă���Ǝ�E�n�������A�܂���͗l�ƂȂ��Ă���B�܂��A�o�c��Ջ�����ړI�Ƃ����A����Ȃ�o�c�������͊e�Ћ��ʂ̉ۑ�ł���A���͉�Ђ��܂߂��O���[�v��ƑS�̂̑����͔�������v�͋�����}����g�݂͌p�����Ă����Ƒz�肳���B ���@�d�͊e�Ђ̑�3�l�����A�����Z�ɂ��ẮA�̔��d�͗ʂ͑O�N�����Ɣ�ׂČ������邢�͉����ƂȂ������̂́A���㍂�͔R��������x�̉e����Đ��\�G�l���M�[�̌Œ艿�i���搧�x�̕��ۋ����t���̑����Ȃǂɂ��A�e�ЂƂ��ɑΑO�N������ő������Ă���B�o�푹�v�ɂ��ẮA�R����̑����Ȃǂ���ΑO�N������Ō��v�ƂȂ�����Ђ������������̂́A���q�͔��d���̍ĉғ��ɂ������֘A��̑��������}�������ȂLjꕔ�̉�Ђɂ����Ă͑ΑO�N������ő��v�ƂȂ����B�����āA�o�c�S�ʂɂ킽��O�ꂵ���������Ɍp���I�Ɏ��g���ƂȂǂɂ��A�����̓d�͉�Ђō������m�ۂ��Ă���B�܂��A�ʊ����ʂ��ɂ��ẮA�قƂ�ǂ̓d�͉�Ђō����ƂȂ錩�ʂ��ł���B 2�D�E��̏� ���@�d�̓V�X�e�����v�ɔ����d�͏����S�ʎ��R����A�K�X�����S�ʎ��R���ɂ��G�l���M�[�Y�ƊԂ̋����i�W���͂��߂Ƃ��āA�d�͊֘A�Y�ƑS�ʂɂ����ĐV���ȋ���������}���Ă���ق��A���z�d����̖@�I�����ւ̑Ή���I�����s�b�N�E�p�������s�b�N���v�Ȃǂɔ����ʑ����Ȃǂ̎��Ɗ��̂��ƂŁA�E��g�����́A�Ɩ��̍��x���E���l���ɂ�莿�E�ʂƂ��ɋƖ����S������������������Ȃ��ɂ����āA�����I�ȗv���s���ɂ�������炸�A���ʂ���o�c���ۑ�̉����Ɍ��������Ɏ��g�ނƂƂ��ɁA�����͋����Ɍ����A�O���[�v��̂ƂȂ�������Ȃ�o�c�������Ɍ����Ɏ��g��ł���B ���@��K�͎��R�ЊQ���͂��߂Ƃ���e��ЊQ����̑��������ȂǁA��������ʈ��苟���m�ۂ̎��g�݂͂��Ƃ��A���q�͊֘A�{�݂̐V�K����ւ̑Ή��A�Η͔��d���̓d���E�����X�N�⑾�z�����d���̎��R�ϓ��d���̋}���Ȋg��ɔ����Ή��ȂǎR�ς���i�ق̉ۑ�ɑ��A�ɂ߂č����ْ����̂��ƁA����̍�ƈ��S�̊m�ۂ��O��ɁA�d�͊֘A�Y�Ƃɓ������Ԃ���ۂƂȂ��Č����Ȏ��g�݂𑱂��Ă���B ���@����ŁA�J���͐l���̌�����Z�p�E�Z�\��L����҂̗��o�ɔ����J���͕s���͂��������������𑝂��Ă���A���͊�Ƃ��܂ߓd�͊֘A�Y�Ƃ̑����̊�Ƃɂ����ĘJ���͊m�ۂ�����ȏ������Ă���B�����āA���ԊO�J���̏���K�����ɔ����J�����Ԃ̒Z�k���i�W����A�J�������ʂ͂���Ɍ������邱�Ƃ���A�d�͊֘A�Y�Ƃ̊�ՂƂȂ�l�ނ̊m�ہE�琬�͂��������d�v���𑝂��Ă���B�Ƃ�킯�A��N�J���҂̌����͋Z�p�E�Z�\�̈ێ��E�p����E����̊������ɂ��e�����y�ڂ����˂Ȃ��i�ق̉ۑ�ƂȂ��Ă���B IV�D�A���̕��j�i�����j
1�D2018�t�G���������̎��g�ݓ��e �i1�j�u��グ�E��x���v�u�i�������v�̎��g�݂̌p�� �@�����_�ł̓��{�o�ς̐�s���́A�����E�C�O�v�������݂ɉe�������A�ɂ₩�Ȑ����������܂�Ă��邪�A��Ǝ��v���ߋ��ō����L�^���钆�A�J�����z���͒ቺ�𑱂��A���������������ƂȂ��Ă���A�l����ɂ��Ă͎�̏�������͌�������̂́A�Ɍ����������݂͂��Ȃ��B �@GDP�̖�6�����߂�l������Ȃ���A�J�g�ł߂����Ă����u�o�ς̎����I�����v�u�o�ύD�z�̎����v�Ƃ����Љ�I�ڕW�͒B�����꓾�Ȃ��B �@�����҂̃��`�x�[�V�������ێ��E���コ���Ă������߂ɂ́A�u�l�ւ̓����v���s���ł���A���ׂĂ̘J�g���Љ�I�����ƐӔC���ӎ����ĘJ���������̉��P���͂��邱�Ƃ��K�v�ł���B �@���������āA2018�t�G���������ɂ����Ă��A��������̈����グ�ɂ������A���������グ�̗�����p���E�蒅������ƂƂ��ɁA�Ƃ�킯�A�K�J���҂́u��グ�E��x���v�u�i�������v�̎����������߂邽�߂ɂ��A��Ɠ��Œ��������̒����g��␅���̈����グ�A�K�p�J���҂̊g��Ɏ��g�݁A�@��Œ�����̉��P�ɔg�y�����A�u�N��������1,000�~�v�̎������͂��邱�Ƃ��s���ł���B�������i��p���āA�X�̊�ƁE�E��ɂ�����u��グ�E��x���v�u�i�������v�ɍ\���g�D����ۂƂȂ������g�݂��p�����Ă����B �@���������ϓ_������A���������A���ڒ����̓��B�ڕW�̎����A�~�j�}����̊m�ۂɎ��g�ޕK�v������B���̏�Œ��グ�v�������́A���ꂼ��̎Y�ƑS�̂́u��グ�E��x���v�u�i�������v�Ɋ�^������g�݂���������ϓ_����A2�����x����Ƃ��A��������������i�����J�[�u�ێ��������j���܂�4�����x�Ƃ���B �i2�j�u���Ǐ]�E��菀���Ȃǂ̍\����]������^���v�̌p���I�Ȏ��g�� ①�@�ʒ����̎Љ���m�ۂƑ���`���Ɍ����� �@2017�N�t�G���������ɂ�����u���Ǐ]�E��菀���Ȃǂ̍\����]������^���v�́A�A���E�\���g�D�E�����g������̂ƂȂ������g�݂��s�������ʁA�u���グ���v�u�菸�������ݒ��グ�v����N����Ɠ����ɁA�u���グ���v�̗����������铙�A�����̎�̓I�Ȏ��g�݂�����ꂽ�B�����������p���E�蒅������ƂƂ��ɁA����ɑO�i�����Ă������Ƃ��d�v�ł���B �@�����g���̒��������グ�Ɍ����ẮA�������Ԃ̔c���ƒ������x�̊m���͕s���ł���B�A���u�n��~�j�}���^���v��ʂ��āA�n��ɂ������������̌`���ɐϋɓI�ɎQ�悷��ƂƂ��ɁA��Ίz�ł̐����ɂ������A�������茴���̊e�������ڂւ̔z�����ɘJ���g��������܂ňȏ�ɐϋɓI�Ɋւ���Ă������Ƃ��K�v�ł���B���̊ϓ_�����܂��A�������x�̐�����������Ԕc���A��������������i�����J�[�u�ێ��������j�̘J�g�m�F�ȂǁA���O�̏������d�v�ł��邱�Ƃ�O�ꂵ�Ă������Ƃ��K�v�ł���B ②�@����̓K�����̐��i �@������Ƃ̒��グ�����m�ۂɂ͎���̓K�����̐��i���s���ł���A�u�T�v���C�`�F�[���S�̂Ő��ݏo�����t�����l�̓K�����z�v���K�v�ł���B���킹�āA���ꂼ��̒i�K�Ő��ݏo�����t�����l�́A���S�ň��S�œ��������̂���E�ꂪ��Ղɂ����Ă������ݏo�������̂ł���B����̓K�����ƌ��S�ň��S�œ��������̂���E��̎����������ɐ����i�߂���悤�A�E��J�g�A�o�c�Ғc�̂ƂƂ��ɎЉ�S�̂ɑi���Ă����B �@�����āA�����҂͓����ɏ���҂ł�����B��l�ЂƂ肪�ϗ��I�ȏ���s������X���H���Ă������Ƃ������I�ȎЉ�Ɍ�������ȉc�݂ł���A����ҋ���̐��i�ƂƂ��ɁA�����҂̗��ꂩ��Љ�ɌĂт����Ă������Ƃ��K�v�ł���B �i3�j�u���ׂĂ̘J���҂̗���ɂ������������v�����ւ̎��g�� �@��Ƃ̑����ɕs���ȁu�l�ނ̊m�ہE�蒅�v�Ɓu�l�ވ琬�v�Ɍ����ẮA�E����n�m����J�g�ɂ���Ē����ԘJ���̐������͂��߂Ƃ��铭���������ߒ����A���S�Ō��N�Ŏ����\�ȐE����\�z���Ă����ƂƂ��ɁA���K�J���ҁE�K�J���҂��킸�X�l�̏�j�[�Y�ɂ��������l�ȓ�������I���ł���d�g�݂𐮂��Ă������Ƃ��K�v�ł���B�����E��œ������ׂĂ̘J���҂̋ϓ��E�ύt�ҋ��̎�����Ј����̎��g�݁A���S���Ĉ玙�E���E���ÂƎd���̗������\�Ƃ�����g�݂Ȃǃ��[�N�E���C�t�E�o�����X�����Ɍ��������g�݂��K�v�ł���B 2�D��̓I�ȗv������ �i1�j���グ�v�� ①�@������� ���@���ׂĂ̑g���͌�������ɂ������A�����̈����グ���߂����B�v���̑g�ݗ��ẮA��������������i�����J�[�u�ێ��������j���m�ۂ�����ŁA�u��グ�E��x���v�u�i�������v�ɂ��������e�Ƃ���B ���@���̍ۂɂ́A�����̏グ���݂̂Ȃ炸�A�߂����ׂ����������ւ̓��B�Ȃǁu���������̐�Βl�v�ɂ��������g�݂�i�߂�B�\���g�D�͂��ꂼ��̎Y�Ƃ��ƂɌʖ����̍Œᓞ�B�����E���B�ڕW���������A�Љ�I�ȋ��L�ɓw�߂�B�P�g�͑g�����̌ʒ������Ԃ�c�����A��������������J�[�u�����Ă䂪�݂�i���̗L�����m�F������ŁA��������P������g�݂��s���B ���@�������x���������̒P�g�́A�\���g�D�̎w���̂��ƁA���x�̊m���E�����Ɍ��������g�݂���������B ���@�������̔K�J���҂̒����ɂ��ẮA���Ј��Ƃ̋ϓ��ҋ��̊ϓ_������P�����߂�B ②�@�K�͊Ԋi���̐����i�����̒��グ�v���j ��Ɛ���99.7�����߁A�S�]�ƈ��̖�7�����ٗp���钆����Ƃ̌o�c��Ղ̈���ƁA�����œ����J���҂̘J�������̌��エ��ѐl�ނ̊m�ہE�琬�́A���{�o�ς́u��グ�E��x���v�u�i�������v�̕K�v�����ł���A���S�Ŏ����I�������I�Ȕ��W�ɂƂ��ĕs���ł���B �u���������v��ݒu���A�u�����������j�v�ɂ��ƂÂ��āA��������̈����グ�ɂ������A�N���m�ۂ̊ϓ_���܂ߐ����̊m�ہE������͂���B ���@�����g���̕��ϒ�������Ƃ��������グ�z���x�[�X�Ƃ�����ŁA�u��グ�E��x���v�u�i�������v���͂���ϓ_�ŁA�A�������g�����ϒ����Ƃ̊i���̊g����������鐅����ݒ肷��B���Ȃ킿�A�A�������g���S�̕��ϒ���������2�������z�Ƃ̍��z����悹�������z����グ�����ڕW�i6,000�~�j�Ƃ��A�����J�[�u�ێ����i1�N�E1�Ίԍ��j�i4,500�~�j���܂߁A���z��10,500�~�ȏ��ڈ��ɒ��������グ�����߂�B ���@�u��グ�E��x���v�u�i�������v�̎������͂��邽�߁A�\���g�D�͂��ꂼ��̎Y�Ǝ��Ԃ܂��āu���B�ڕW�����v��ݒ肷��B�܂��A�s���{�����ƂɘA�����r���O�E�F�C�W�ɂ��ƂÂ��u�Œᓞ�B�����v��ݒ肵�A���ׂĂ̘J���҂����̐������N���A���邱�Ƃ��߂����B ③�@�ٗp�`�ԊԊi���̐����i�������̈����グ�j ���������グ�̎��g�݂́A�Ƃ�킯�A�K�J���҂̘J���������́u��グ�E��x���v�u�i�������v�Ɛ��K�J���҂Ƃ̋ϓ��ҋ��̎������͂��邽�߁A���̂����ꂩ�̎��g�݂�W�J����B ���@�u�N��������1,000�~�v����������B ���@���łɎ���1,000�~���̏ꍇ�́A37�~��ڈ��Ɉ����グ��v������B ���@�u�s���{���ʃ��r���O�E�F�C�W�v�����鐅�����߂����Ď��g�ށB ���@�������[���̓����E���m���̎��g�݂���������B�������[�����m������Ă���ꍇ�́A���̏��������m�ۂ�����ŁA�u��グ�E��x���v�u�i�������v�ɂ��������e�Ƃ���B ④�@�j���Ԓ����i���̐��� �j���̋Α��N����Ǘ��E�䗦�̍��ق��j���Ԃ̒����i���̎�v���ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A�E��ɂ�����j���Ԓ����i���̐����Ɍ����Ď��g�݂�i�߂�B ���@�P�g�́A�����f�[�^�ɂ��ƂÂ��Ēj���ʁE�N��Ƃ̒������z��c�����āu�����鉻�v�i�����v���b�g��@�Ȃǁj���͂���ƂƂ��ɖ��_��_�����A���P���������g�݂�i�߂�B ���@�����֘A�蓖�i���������A�Ƒ��蓖�Ȃǁj�̎x���ɂ�����Z���[��́u���ю�v�v���͎����I�ȊԐڍ��ʂɂ�����̂ŁA�p�~�����߂�B�܂��A�����݂̂ɏZ���[�Ȃǂ̏ؖ����ނ̒�o�����߂邱�Ƃ͒j���ٗp�@��ϓ��@�ŋ֎~�Ƃ���Ă��邽�߁A���������s���B ⑤�@��Ɠ��Œ���� ���@���ׂĂ̑g���́A��Ɠ��Œ�������Y�Ƃ̌������S�ۂ���ɂӂ��킵�������ŗv�����A���艻���͂���B�܂��K�p�J���҂̊g����߂����B ���@���ׂĂ̒����̊�b�ł��鏉�C���ɂ��ĎЉ�����m�ۂ���B �@�@��18�������C���̎Q�l�ڕW�l�c�c172,500�~ ⑥�@�ꎞ�� ��������̈����グ�ɂ������A�N���m�ۂ̊ϓ_���܂ߐ����̌���E�m�ۂ��͂��邱�ƂƂ���B ⑦�@������ƁE�K�J���ғ��̑ސE���t���x�̐��� ���@��ƔN���̂Ȃ����Ə��ɂ����ẮA��ƔN�����x�̐��������Ǝ�ɋ��߂�B���̍ہA��ƔN���͒����̌㕥���Ƃ��Ă̐��i�Ɋӂ݁A�m�苋�t��ƔN���iDB�j�𒆐S�ɐ��x�v����������B ���@�K�J���҂Ɋ�ƔN�����x�������悤�A�ސE���K���̐������͂���B �i2�j���ׂĂ̘J���҂̗���ɂ������u�������v�̌����� �@���N�œ�����������J�����ԂƉߘJ���[���̎����A�����q����E�l�������Љ�i�ނ킪���̎Љ�\���܂��A�u�Љ���̎��ԁv�̏[�����܂߃��[�N�E���C�t�E�o�����X�Љ�̎������߂����āA�X�l�̏�j�[�Y�ɍ������������Ə����̂�����ɂ��đ��̓I�Ȍ����Ƌ��c���s���B�Ƃ�킯�i�ق̉ۑ�ł��鑍���J�����ԏk���Ɍ����āA�u�E��_���`�F�b�N���X�g�v�Ȃǂ����p���A�J�����ԊǗ��̓O���N���L���x�ɂ̎擾���i�ȂǂɎ��g�ށB ①�@�����ԘJ���̐��� �@�����t�����ԊO�J���̏���K���ȂǁA�����ԘJ�������Ɍ������J����@�������s���邱�Ƃ̎�|�ƈӋ`�܂��A��s�I�ɐE��̊�ՂÂ���Ɏ��g�ށB ���@36����̒����ɂ��� �E�@36����́A�u��45���ԁA�N360���Ԉȓ��v�������ɒ�������B �E�@��ނ����ʏ������������ꍇ�ɂ����Ă��A�N720���Ԉȓ��Ƃ��A�����܂��A���}���I�Ȏ��ԂƂȂ�悤���g�ށB �E�@�x���J�����܂߁A�N720���Ԉȓ��ƂȂ�悤�Ɏ��g�ށB �E�@�{���̓K�p�P�\�ƂȂ��Ă���Ǝ�ɂ��Ă��A�����ɋ߂Â��邽�߂̘J�g���c���s���ƂƂ��ɁA�K�p���O�ƂȂ��Ă���Ɩ��ɂ��Ă��A�{����K�p����悤�J�g���c��i�߂�B ���@�K�p�P�\����Ă��钆����Ƃɂ����Ă��A��60���Ԃ��銄����������50���ȏ�Ɉ����グ��B ���@�Ζ��ԃC���^�[�o���K���i����11���ԁj�̓����ɂ��āA�J�g���c��i�߂�B ���@�J���҂̌��N�m�ۂ̊ϓ_����A�Ǘ��ēҁA�݂Ȃ��J���K�p�҂��܂ނ��ׂĂ̘J���҂̎��J�����Ԃ��q�ϓI�ȕ��@�Ŕc������d�g�݂�����B ���@�N���L���x�ɂ̎擾���i �@�N�x�J�b�g�[���Ɍ����Ď��g�ނƂƂ��ɁA�J����@�����ɂ�莖�Ǝ҂ɔN�x5���̎��G�w�茠���`��������邱�Ƃ܂��A5�������҂��Ȃ������g�݂𐄐i����B ���@50�l�����̎��Ə�ɂ����Ă����S�q���ψ���̐ݒu���s���B ② �E��ɂ�����ϓ��ҋ������Ɍ��������g�� �@�ٗp�`�Ԃɂ�����炸�d���ɉ������K���ȏ����̊m�ۂɌ�������Ր����ɐ�s�I�Ɏ��g�ށB ���@�ٗp����Ɍ��������g�� �X�l�̃j�[�Y�ɉ��������������I���ł��鐧�x�̐����𐄐i����B �E�@���Ј��ւ̓]�����[���E���x�����A�܂����x�̉^�p�̓_����ʂ��āA���Ј�������]����҂̌ٗp����𑣐i����B �E�@2018�N4���������J���_��@��18���̖����]�����[�����K�p�����P�[�X���{�i�I�ɐ����邱�Ƃ܂��A�����]�����邢�͐��Ј��o�p�Ɍ��������x�̍\�z�ƌَ~�ߖh�~�Ɍ������J�g���c���s���ƂƂ��ɁA���Y�J���҂ւ̎��m��O�ꂷ��B ���@�u����J����������v�̎����Ɍ����Ė@�������s���邱�Ƃ܂��A�A�������s�����u����J����������K�C�h���C���Ă̎�����i���́j�`���l�ȓ������̂��ƂŔ[�������鏈�������̂��߂Ɂ`�v���Q�l�ɁA�E��ɂ�����ٗp�`�ԊԂ̕s�����ȘJ�������̓_���E���P�Ɏ��g�ށB �E�@�ꎞ���̎x�� �E�@���������S�ʂ���ш��S�Ǘ��Ɋւ�����g�� �E�@�Љ�ی��̉����̊m�F�E�O��Ɖ�����]�҂ւ̑Ή� �E�@�L���x�ɂ̎擾���i �E�@�玙�E���x�Ƃ̎擾�͐��Ј��Ɠ��l�̐��x�Ƃ���B �E�@�Čٗp�ҁi��N�ސE�ҁj�̏����Ɋւ�����g�� �i3�j���[�N���[���̎��g�� �@���ׂĂ̐E��ɂ�����f�B�[�Z���g�E���[�N�̎����A���[�N�E���C�t�E�o�����X�̐��i�A�R���v���C�A���X�̓O����͂���ϓ_������g�݂�i�߂�B ①�@�����J����@�Ɋւ�����g�� �@�����t�����ԊO�J���̏���K������肵�����g�݂ɉ����āA�J�����ԋK���̎����������߂�ׂ��A①36����̓_���i�x���J���̗}���A���x���Ԃ���ꍇ�̌��N�m�ۑ[�u�A�ߔ����J���g���E�ߔ�����\�҂̃`�F�b�N�A36����̎��m��)�A②�J�����ԊǗ��̐V�K�C�h���C�����܂����J�����ԊǗ��E�K���c���̓O��A③���Ə�O�݂Ȃ�����эٗʘJ�����̓K���^�p�Ɍ������_��(�J�g����E�J�g�ψ���A���N�E�����m�ۑ[�u�̎��{�A�J�����Ԃ̏�)���s���B ②�@����J����������̎����Ɍ������@�����Ɋւ�����g�� �@�ٗp�`�ԊԂɂ�����ϓ��ҋ������i����J����������j�̎����Ɍ������@����(�p�[�g�^�C���J���@�A�J���_��@�y�јJ���Ҕh���@����)�̓��e�܂��āA①�J���g���ւ̉����̗L�����킸�A�p�[�g�^�C����L���_��œ����K�ٗp�J���҂̘J���������ɂ��Ă̓_���A②�X�̘J�������E�ҋ����Ƃɂ��̖ړI�E�����ɏƂ炵�ĕs�����ƂȂ��Ă��Ȃ����̊m�F�A③�p�[�g�^�C����L���_��œ����J���҂̑g����������т��̐��܂����J�g���c�̎��{�ȂǔK�ٗp�J���҂��܂߂��W�c�I�J�g�W�̋����Ɏ��g�ށB ③�@�����J���Ҕh���@�Ɋւ�����g�� �@�u�����J���Ҕh���@�Ɋւ���A���̎��g�݁v(��2�����s�ψ���m�F�^2015.11.20)���Q�l�ɁA2015�N�����@�Ɋւ���h���\���Ԃ̊��Ԑ���������O�ɁA�v�����c�̎��{�y�шӌ�����Ɋւ��鏀��(�������Ƃ̔h���J���҂̐l���A���ԓ��̊m�F)���s���B �@�܂��A����J����������Ɍ������@�����ɂ����āA�h���J���҂Ɣh����J���҂Ƃ̋ϓ��E�ύt�ҋ��������Ƃ��ꂽ���Ƃ܂��A�h���J���҂̒����E�J��������_��������Ŏ��Ǝ�ɕK�v�ȑΉ��i�ϓ��E�ύt�ҋ����\�Ȑ����ł̔h�������ݒ蓙�j�����߂�B����ɁA�H���E�x�e���E�X�ߎ��Ȃǂ̕��������{�݂ɂ��ẮA�h���J���҂ɕs�����ȏ����Ȃǂ��ݒ肳��邱�ƂȂ����������p�ł���悤�Ɏ��g�ށB ④�@�Ⴊ���Ҍٗp�Ɋւ�����g�� �@2018�N4������Q�Ҍٗp���i�@�ɂ��ƂÂ��@��ٗp����2.2���i���E�n��������2.5���A����ψ���2.4���j�Ɉ����グ���邱�Ƃ܂��āA�E��ɂ������Q�Ҍٗp���̔c���ƁA���̒B���Ɏ��g�ށB�܂��A�u�Ⴊ���҂ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ����s���ȍ��ʓI�戵���̋֎~�v�A�u�����I�z���̒`���v�A�u���k�̐��̐����E��������ѕ��������̉����v�����Ǝ҂̐Ӗ��Ƃ��ꂽ���Ƃ��A�J������E�A�ƋK���̃`�F�b�N�〈�����Ɏ��g�ށB ⑤�@�L���J���_��i�����]�����[���j�Ɋւ�����g�� �@2018�N4���������J���_��@��18���̖����]�����[�����K�p�����P�[�X���{�i�I�ɐ����邱�Ƃ܂��A�ΏۂƂȂ�L���_��J���҂ւ̎��m����і����]�����i�̎��g�݂ɉ����A�u�A���w�����J���_��@�x�Ɋւ�����g�݂ɂ��āi��13�����s�ψ���m�F�^2012.10.18�j�v����{�ɁA�����]����̘J�������̑Ή��A�����]�����[�����ړI�َ̌~�߂̖h�~�A�N�[�����O���Ԃ̈��p�h�~�A�َ~�ߖ@���̎��m�A�����]�����[���̑ΏۂƂȂ�L���_��J���҂̘J���g���������i�Ȃǂ̎��g�݂�i�߂�B �E�@�Z���ԘJ���҂ɑ���Љ�ی��̓K�p�g��Ɋւ�����g�� �@2016�N10�����501�l�ȏ�̊�Ɠ��ɂ�����Z���ԘJ���҂ɑ���Љ�ی��̓K�p���g�傳�ꂽ���Ƃ܂��A①�Љ�ی����K�p�����ׂ��J���҂��S���K�p����Ă��邩�_���E�m�F����ƂƂ��ɁA②���Ǝ҂��K�p�g���������邽�߂ɒZ���ԘJ���҂̘J�������̕s���v�ύX���s��Ȃ����Ƃ��m�F����B �@�܂��A2017�N4�������500�l�ȉ��̖��Ԋ�Ƃɂ��Ă��A�J�g���ӂɂ��ƂÂ��Z���ԘJ���҂ւ̓K�p�g�傪�\�ƂȂ������Ƃ܂��A③500�l�ȉ��̊�Ƃɂ����ĒZ���ԘJ���҂֎Љ�ی���K�p����悤���Ǝ�ɋ��߂�Ȃǂ̎��g�݂�i�߂�B �F�@�玙�E���E���ÂƎd���̗����̐��i�Ɋւ�����g�� �玙�E���ɂ��ẮA�u�i4�j�j�������̐��i�v���Q�ƁB �@�u���ÂƐE�Ɛ����̗����x���Ɍ��������g�ݎw�j�v(��14�����s�ψ���m�F�^2016.11.10)���Q�l�ɁA�����ɂ킽�鎡�Â��K�v�Ȏ��a�������J���҂���\�o���������ꍇ�ɉ~���ȑΉ����ł���悤�A�J������E�A�ƋK���ȂǏ��K���̐�����i�߂�B �i4�j�j�������̐��i �@�j���̐l�������d����A�d���Ɛ����̒��a������Љ�̎������߂����A�E��ɂ�����j�������◼���x���̑��i�Ɍ����A�A���K�C�h���C���Ȃǂ����p���Ď��g�݂�i�߂�B ①�@�����������i�@�A�����j���ٗp�@��ϓ��@���̒蒅�E�_�� �@�����������i�@������j���ٗp�@��ϓ��@�̒蒅�E�_���Ɍ����A�ȉ��̉ۑ�Ɏ��g�ށB���E���c�ɂ������ẮA�ł��������ؓI�ȃf�[�^�ɂ��ƂÂ������������A���P�����߂Ă����B ���@�����̏��i�E���i�̒x��A�z�u��d���̔z�����j���ňقȂ邱�ƂȂǁA�j���Ԋi���̏�_���E�J�g���c���s���A�ϋɓI�ȍ��ʐ����[�u�i�|�W�e�B�u�E�A�N�V�����j�ɂ����P���͂���B ���@�����I�ȗ��R�̂Ȃ��]�����]���Ȃ����ǂ����_�����A�������͂��� ���@�D�P�E�o�Y�Ȃǂ𗝗R�Ƃ���s���v�戵���̗L���ɂ��Č����A�������͂���B ���@�����ԃZ�N�n���A�W�F���_�[�E�n���X�����g���܂߂��Z�N�V���A���E�n���X�����g�h�~�[�u�̎��������S�ۂ���Ă��邩������B ���@�u���I�w���y�ѐ����F�Ɋւ��鍷�ʋ֎~�Ɍ��������g�݃K�C�h���C���v�����p���A�A�Ɗ��̉��P���Ɏ��g�ށB ���@�����������i�@�ɂ��ƂÂ����Ǝ�s���v�����ɘJ�g�Ŏ��g�ށB����ɂ������ẮA�e���Ə��̏ɂ��ƂÂ��āA�����c���E���͂��A�K�v�ȖڕW����g�ݓ��e��ݒ肷��B ���@�s���v�悪�����ɐi�W���Ă��邩�A�o�c�b�`�ɐϋɓI�Ɋ֗^����B ���@�֘A����@���⏗���������i�@�ɂ��ƂÂ����肳�ꂽ�s���v��̓��e�ɂ��āA�w�K��̏��ݒu����Ȃǎ��m���͂���B ②�@�玙����Ǝd���̗����Ɍ����������� �@�u�����玙�E���x�Ɩ@���Ɋւ���A���̎��g�݂ɂ��āv�i��11�����s�ψ���m�F�^2016.8.25�j�ɂ��ƂÂ��A�ȉ��̉ۑ�Ɏ��g�ށB ���@�����玙�E���x�Ɩ@�̎��m�E�_�����͂���ƂƂ��ɁA�����x����̊g�[�̊ϓ_����A�����������e�ւ̊g�[�ɂ��ĘJ������̉���Ɏ��g�ށB ���@�L���_��J���҂ɑ��Đ��x���g�[����B ���@�玙�x�ƁA���x�ƁA�q�̊Ō�x�ɁA���x�ɁA�Z���ԋΖ��A����O�J���̖Ə��̐\���o��擾�ɂ��A���ق��邢�͏��i�E���i�̐l���l�ۂȂǂɂ����ă}�C�i�X�]���Ƃ���ȂǁA�s���v��舵�����s���Ȃ��悤�J�g�Ŋm�F�E�O�ꂷ��B ���@�}�^�j�e�B�E�n���X�����g��p�^�j�e�B�E�n���X�����g�A�P�A�i���j�E�n���X�����g�Ȃǂ��͂��߂Ƃ���A������n���X�����g���ꌳ�I�ɖh�~������g�݂��e��Ƃɓ���������B�����ɁA�D�Y�w�ی쐧�x��ꐫ���N�Ǘ��ɂ��Ď��m����Ă��邩�_�����A�D�P�E�o�Y����т���Ɋւ�鐧�x�𗘗p�������Ƃɂ��s���v��舵���̋֎~��O�ꂷ��B ���@�����̏A�ƌp�����̌����j���̃��[�N�E���C�t�E�o�����X�̊ϓ_����A�j���̈玙�x�Ǝ擾���i�Ɏ��g�ށB ���@�����x�����x����ی����x�Ɋւ�����ȂǁA�d���Ɖ��̗������x�����邽�߂̑��k������ݒu����悤�e��Ƃɓ���������B ���@�s�D���ÂƎd���̗����Ɍ����A�擾���R�ɕs�D���Â��܂߂��x�ɓ��i���ړI�x�ɂ܂��͐ϗ��x�ɓ����܂ށj�̐��x�����Ɏ��g�ށB ③�@������琬�x�������i�@�ɂ��ƂÂ����g�݂̐��i ���@���[�N�E���C�t�E�o�����X�̐��i�Ɍ������J���g���̕��j�m�ɂ��A�J�g���c��ʂ��āA�v����ԁA�ڕW�A���{���@�E�̐��Ȃǂ��m�F����B����ɁA�쐬�����s���v��̎����ɂ��u����݂�v�}�[�N�A����сu�v���`�i����݂�v�̎擾���߂����B ���@�u����݂�v�}�[�N����сu�v���`�i����݂�v���擾�����E��ɂ����āA���̌�̎��g�݂���ނ��Ă��Ȃ����J�g�Ŋm�F���A�v����e�̎����������߂�B 3�D�^���̗��ւƂ��Ắu����E���x�����̎��g�݁v �@���ׂĂ̓����҂́u��グ�E��x���v�u�i�������v�Ɍ����āA����E���x�����̎��g�݂��t�G���������ɂ�����J�����������P�̎��g�݂ƂƂ��ɉ^���̗��ւƂ��Đ����i�߂�B �@��̓I�ɂ́A�u2018�N�x�@�d�_��������̎��g�ݕ��j�v�܂��A�u�������Ƃ����Ƃ�����S�Љ�v�̎����Ɍ������ȉ��̐���ۑ�ɂ��āA���{�E���}�ւ̓��������A�R�c��E����R�c�Ή��A�X�銈���Ȃǂ�ʂ������_���N�ȂǁA�A���{���E�\���g�D�E�n���A�����̂ƂȂ��ĕ��L���^����W�J����B �i1�j��ƊԂɂ���������E�K���Ȏ���W�̊m���Ɍ��������g�� �i2�j�łɂ�鏊���ĕ��z�@�\�̋����Ɍ��������g�� �i3�j�ٗp�`�Ԃɂ������Ȃ��ϓ��ҋ������̖@�����A����ю��ԊO�J���̏���K���̊m���Ȏ����Ɍ��������g�� �i4�j��ÁE���E�ۈ�T�[�r�X�̐l�ފm�ۂɌ��������g�� �i5�j�q�ǂ��E�q��Ďx���̏[���Ƒҋ@�����̉������̍����m�ۂɌ��������g�� �i6�j����̋@��ϓ������Ɍ���������̖������E���w���̊g�[�Ɍ��������g�� V�D�d�͑��A�̊�{���j
�@�d�͊֘A�Y�Ƃ������ɂ킽�茒�S�ɔ��W�����Ă������߂ɂ́A�Z���E�������I�Ȋϓ_����A�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂��ׂĂ̌o�ϓI�E�Љ�I�n�ʂ̌����}��ƂƂ��ɁA�g�����Ƃ��̉Ƒ��̐����̈���E���S�A��肪���E���������������ł��閣�͂���Y�Ƃ̍\�z�Ɍ��������g�݂��p�����Ă������Ƃ��K�v�Ȃ��Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B 1�D�����ɂ��ẮA�����J�[�u�ێ������m�ۂ��������ŁA�u�o�ς̎����I�����v�Ȃǃ}�N���̊ϓ_�ɉ����A�d�͊֘A�Y�Ƃ̌��S�Ȕ��W�ɕs���Ȑl�ނ̈ێ��E�m�ۓ��Ɏ�����悤��������Ɏ��g�݁A�����ēd�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂́u��グ�E��x���v�u�i�������v�u�����v���p���E�O�i������B 2�D�ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�N�Ԓ����̈ꕔ�Ƃ��Ĉ��肵���������x���鐶�����������Œ���m�ۂ��邱�Ƃ���{�Ɏ��g�ނ��ƂƂ��A�ߋ��̑Ì����сA��ƋƐсA���Y�������E����ԂȂǂ����Ă����v�����s���B 3�D�d���Ǝ������̒��a���}������̐����ɂ��ẮA�ߘJ���E�ߘJ���E���ɋN�������Ȃ����Ƃ͂��Ƃ��A���N��Q�̖��R�h�~���Ɍ����āA���ԊO�J���̏���K���������������A��s�I�Ȏ��g�݂ɂ���Ē����ԘJ���̑����������߂����ƂƂ��ɁA�玙�E���E���ÂƂ��������C�t�C�x���g�ɉ�������葽�l�ȓ��������\�z����ȂǁA���[�N�E���C�t�E�o�����X�̎������߂������g�݂�i�߂�B 4�D�d�͊֘A�Y�Ƃœ����N�������S���ē��������邱�Ƃ��ł���悤�A���N��Ҍٗp�A�Ⴊ���Ҍٗp�A�����������i���A�J�����̊m�ہE���P�A���x�̐����E�[���Ɍ������g�ށB 5�D�K�J���҂̑ҋ����P�̎��g�݂ɂ��ẮA�J������������̊�ՂƂȂ�g�D����i�߂�ƂƂ��ɁA����J����������̎����Ɍ������@�������������A�����E��œ������ԂƂ��āA���Ј��Ƃ̋ϓ��E�ύt�ҋ��̊m���ɂȂ�����g�݂�i�߁A�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����ґS�̂̒�グ��}��B VI�D��̓I�Ȏ��g��
1�D�ٗp����Ɛl�ފm�ۂւ̎��g�� �@�@�@�d�͊֘A�Y�Ƃ���芪�����̕ω��ɔ����A�o�c����������̂���Ȃ�[���A��Ƃ̍ĕ҂�O���[�v��ƂƂ̖����̌������Ȃǂ��i�߂��Ă���B�\���g�D�ɂ���ẮA�������o�c���̌p���Ȃǂ���A�ꕔ�ɂ����Čٗp�ɑ���s���������Ă���B �܂��A���q���ɔ�����N�J���҂̌�����d�͊֘A�Y�Ƃ���芪�����ω��ɔ����A�V�K�̗p��������������ƂȂ��Ă���ق��A�����Ȍo�ςɂ��J���͎����̂Ђ����ɂ��l��s�������݉����Ă���B����ɔ����A�d�͊֘A�Y�Ƃ̌���ł́A���Ƃ��x����l�ނ̖����I�ȕs����Z�p�E�Z�\�̈ێ��E�p��������ƂȂ鎖�Ԃ��ꕔ�ɎU�������ق��A�E����̊������ɂ��e�������˂Ȃ��[���ȉۑ�ƂȂ��Ă���B ������A�d�͊֘A�Y�Ƃ����S�ɔ��W���Ă������߂ɂ́A�����ɓ����҂̌ٗp�s���̕��@�Ɛl�ނ̊m�ہE�琬���d�v�ł���A�\�����A�E�����g���������͂����ď��ۑ�̉����Ɍ����Ď��g�݂�i�߂�B ���@�����g���́A��Ƃ̌o�c��o�c�v��Ȃǂ��m���ɔc�����������ŁA�o�c��Ղ̈���Ɍ������J�g���c���s���ƂƂ��ɁA�ٗp�����l�ނ̊m�ہE�琬�̏d�v���ɂ��āA�J�g�̋��ʔF�����������Ă����B ���@�����g���́A�ٗp����Ɏ���������̐����Ɍ����āA�l�������Ɋւ��鎖���ɂ��Ċm�F����ƂƂ��ɁA�J������̒����A�����E�[���Ɏ��g�ށB ���@�\�����A�́A�����g���Ԃ̘A�g�����������[�߁A�E��ۑ��I�m�ɔc������ƂƂ��ɁA�ٗp�����l�ނ̊m�ہE�琬�ɌW��鏔�ۑ�̉����Ɍ����āA�J�g���k��̏[���Ɏ��g�ށB ���@�d�͑��A�E�\�����A�E�����g���E�e����́A�ɉ����āA�\����̎��{���܂߁A�ٗp�����l�ނ̊m�ہE�琬�ɂȂ�����g�݂��s���B 2�D�����̎��g�� �����g���͎��O�����Ƃ��āA���Ђ̒������Ԕc�����m���ɍs���������ŁA�����J�[�u�ێ����̊m�ۂɉ����A�u�o�ς̎����I�����v�Ȃǃ}�N���̊ϓ_����̏�������A�d�͊֘A�Y�Ƃ��x����l�ނ̈ێ��E�m�ۂȂǂɎ�������������グ�A�u�i�������v�E�u�����v�Ȃǂ�ʂ��āA�d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂́u��グ�E��x���v���߂����A3,000�~�ȏ�̒�������Ɏ��g�ށB 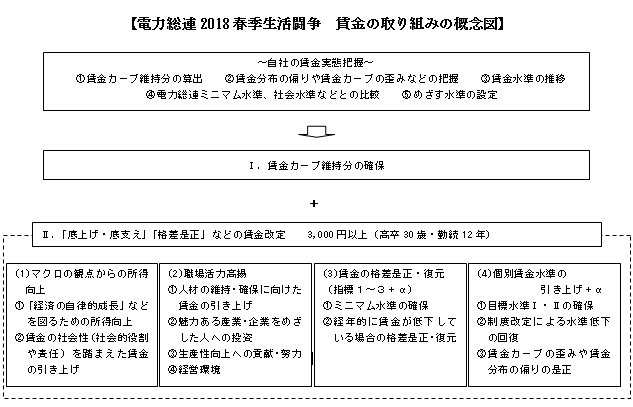 �i1�j���Ђ̒������Ԃ̔c�� ���̎��O�����Ƃ��āA�������Ԃ�c���������J�[�u�ێ����ɕK�v�Ȍ����̎Z�o���s���ƂƂ��ɁA�����J�[�u�̘c�݂�������z�̕�Ȃǂ̉ۑ�c�����s���B�܂��A�ߋ��̒����J�[�u�Ɣ�r���āA�����������o�N�I�ɒቺ���Ă���Ȃǂ̗v���̌����\���ɍs���B �������J�[�u�̘c�݂Ƃ́F���f�������J�[�u�Ɣ�r���X���̓x������c�݂ɂ��Ĕc������ ���������z�̕�Ƃ́F�N��Ԃ�j���ԂȂǂł̃o���c�L�̗L���ɂ��Ĕc������ �i2�j�����J�[�u�ێ����̊m�� ���@�������x�i�������[�������x������Ă���j���m�����Ă�������g���́A���̒����\���ێ�����B ���@�������x�i�������[�������x������Ă���j���m�����Ă��Ȃ������g���́A�����J�[�u�ێ�����v������B ���@�ٗp�����D�悵�āA��������������̓�����팸�Ȃǂ��s�킴��Ȃ����������g���́A���������B �i3�j�}�N���̊ϓ_����́u��������v�Ɍ��������������グ�̎��g�� �u�o�ς̎����I�����v��}�邽�߂̏�������A�����̎Љ�܂��������̈����グ�Ɏ��g�ށB �i4�j�E�ꊈ�͍��g�̊ϓ_����̒��������グ�̎��g�� �l�ނ̈ێ��E�m�ۂɌ������J�������̈����グ�▣�͂���Y�Ƃ��߂������u�l�ւ̓����v�A���Y������Ɍ������v���E�w�́A�o�c���Ȃǂ𑍍��I�Ɋ��Ă��A�E�ꊈ�͍��g�Ɍ����Ē����̈����グ�Ɏ��g�ށB �i5�j�����́u�i�������v�E�u�����v�ւ̎��g�� ���Ђ̒������Ԃ�c�����A�d�͑��A�~�j�}����������ʂɂ�������g����o�N�I�ɒ����������ቺ���Ă��Ă�������g���́A�ȉ��Ɍf����w�W���Q�l�ɁA�v�����������肵�A���������̊i�������E�����ɐϋɓI�Ɏ��g�ށB ①�@�ʒ����������u�d�͑��A�~�j�}�������v�����������g���́A�Œ���K�v�Ȑ��v����m�ۂ���ϓ_����A���̐����ɓ��B����悤���g�ށB �y�d�͑��A�~�j�}�������z
�������͐l���@�W�����v�����ɎZ�o ���n��ʍŒ�����ɖ@��J�����ԁi174���ԁj���悶���l���~�j�}����������n��́A�n��ʍŒ�����ɖ@��J�����Ԃ��悶���l��ڎw���B ②�@�o�N�I�ɒ����������ቺ���Ă�������g���́A���̎��Ԃ�c�����A�Љ���i�����J���ȁF�����\����{���v�����E�K�͌v�j���߂����Ƃ����l�����Ɋ�Â��A�i����������ѕ����Ɏ��g�ށB�Ȃ��A�d�͑��A�����g��300���ȉ��̌ʒ���30�|�C���g�i�P�����ρj�ł̎w�W�������Ǝ��̂Ƃ���ƂȂ�B �i�Q�l�j
�i6�j�ʒ��������̈����グ ���Ђ̒������Ԃ�ʂ̎���Ȃǂ����Ă��A�ʒ��������̈����グ���K�v�Ɣ��f���������g���́A�Љ���̊m�ۂ␅���ቺ�̉A�����J�[�u�̘c�݂�������z�̕�̐����ȂǁA�ȉ��Ɍf����w�W�Ȃǂ܂����g�ށB ①�@�Љ�����߂��������g���́A���\�̖ڕW�������Q�l�ɁA���̊l���Ɏ��g�ށB �y�ڕW�����z
���d�͑��A�������Ԓ����Ȃ�тɌ����J���Ȓ����\����{���v�����̉ߋ�5�N���ϊz�����Ă��Z�o�B�ڕW����I�͒��ʁA�ڕW�����U�͑�3�l���ʁB ������18�i���C���j�ɂ��Ă͘A�������g���ɂ������v�g���̍������C�������l�����ݒ�B ②�@�������x����ɂ��e���̌��Ɖ� �J�g���ӂ����������x�ɂ��āA���Ɗ����܂��A��������̈ꎞ�I���z�������������������z���肵���ꍇ�Ȃǂ́A���̌�̌ʒ��������̎��Ԃ�c�����A���Ђ̎Љ�I�ʒu����g�����̘J���ӗ~��������Ă��v�����s���B ③�@�����J�[�u�̘c�݂�������z�̕�̐��� ���Ђ̒������Ԃ�c�����A�c�݂�肪����A�������K�v�Ɣ��f�����ꍇ�́A���̉��P�Ɏ��g�ށB �i7�j�z�����̏[�� �����̈�����m�ۂ��A���������ł�肪�����������ɂȂ���z�����߂����A�v������i�K����z�������d���������g�݂��s���B �i8�j�������x�̊m�� �������x�E�̌n���m������Ă��Ȃ������g���́A�������Ԃ�c�����A���Ђ̉ۑ�𖾂炩�ɂ��������ŁA�J�g�ɂ�錟���E���c�̏��ݒu���A�������x�E�̌n�̊m���Ɍ������g�ށB�Ƃ��ɁA����I�Ȓ����������m�ۂ���ϓ_����A��������̃��[������}���Ă����B �i9�j�Œ��������̎��g�� �p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂Ȃǂ��܂߂��d�͊֘A�Y�Ƃɓ����҂��ׂĂ̊�Ɠ��Œ�����Ƃ��āA�ȉ��̗v�������܂��āA�g�����Ƃ̍Œ����������������B �y�Œ����������F�����s�E�_�ސ�̒n��ʍŒ�������Ԋz���l�����A18�Α����z�Ƃ��Č��z�u167,000�~�ȏ�v�܂��͎��Ԋz�u960�~�ȏ�v�z �������s�i958�~�j�_�ސ쌧�i956�~�j���l�����A18�Α����z�i960�~�j�~�@��J�����ԁi174���ԁj��167,000�~ �i10�j���C���̈����グ �Z�p�E�Z�\�̌p����}�邤���ň���I�ȐV�K�̗p�͕K�v�ł���A�J�������̏�⓯�Ƒ��ЂƂ̔�r�E���͂��s���A�d�͊֘A�Y�Ƃ��x����L�p�Ȑl�ނ��m�ۂł���悤�e�����g���ŗv���z�����肷��B�Ȃ��A�d�͑��A�~�j�}������18�Α����z��������Ă�������g���͂��̊m�ۂɌ����Ď��g�ށB 3�D�ܗ^�E�ꎞ���̎��g�� �ܗ^�E�ꎞ���ɂ��ẮA�N�Ԓ����̈ꕔ�Ƃ��Ĉ��肵���������x���鐶�����������Œ���m�ۂ��邱�Ƃ���{�Ƃ��āA���ɂ��v�����s���B �i1�j�v������ �u�N��4�������Œᐅ���v�Ƃ���B�Ȃ��A�ߋ��̑Ì����сA��ƋƐсA���Y�������E����ԂȂǂ����Ă����v�����s���B �@�i2�j�v���E�Ì����� �ܗ^�E�ꎞ���́A�N�Ԓ����̈ꕔ�Ƃ��Ĉʒu�Â��A�N�Ԏ����̈����}�邽�߁A�ē~�^�ɂ��N�ԗv���E�N�ԑÌ�����{�Ƃ���B �i3�j�~�G���̈��� �~�G���ɂ��ẮA���������グ��̃x�[�X���g�p���A�ċG���ɏ����������Ƃ���B �i4�j�x���� �ċG����6����{�A�~�G����12����{�Ƃ���B 4�D�d���Ǝ������̒��a���}������̐��� �i1�j�N�ԑ����J�����Ԃ̒Z�k �����ԘJ���́A�ƒ�ɂ����������n��Љ�Ƃ̂Ȃ���A���Ȍ[���Ȃǂ̌l�̐����Ǝd���̒��a�ɉe����^���邱�Ƃ͂��Ƃ��A�ߏd�J���ɂ��̒��s�ǂ���^���w���X�s���A�ߘJ���Ƃ��������������N�����ق��A�������ҁA����҂ȂǑ��l�Ȑl�ނ�����ł���Љ�̍\�z��j�Q����v���ƂȂ�B �e�����g���́u�d�͑��A���Z�w�j�v�̍l�����܂��A�J���҂̐g�́E���_�̕ی��ƒ됶���E�Љ�����c�ނ��߂̐������Ԃ̊m�ۂ�O���ɁA36����̌��x���Ԉ��������ɂ�鏊��O�J�����Ԃ̒Z�k��Ζ��ԃC���^�[�o���K�����ɂ��x�����Ԃ̊m�ہA�N���L���x�Ɏ擾�����㓙�ɂȂ���ׂ��ő�����g�ނȂǁA�������̌�������ϋɓI�ɐ��i����B�����ĔN�ԑ����J������1800���Ԃ̒B�����߂����B �Ƃ�킯�A�����t�����ԊO�J���̏���K���Ȃǒ����ԘJ�������Ɍ������J����@�������\�肳��Ă��邱�Ƃ̎�|��Ӌ`�܂������g�݂𐄐i����B ①�@�J�����ԂɊւ���J�g���c�̏[�� ���@�N�Ԃ�ʂ����J�����ԂɊւ�����g�݂̃t�H���[��A���P���ׂ������ɂ��āA�J�g�ψ����ʂ��āA�J�g�̋��c��b���������s���A���艻�i�c���^�A�o���A�m�F�������܂ށj��}��ƂƂ��ɁA36����̓��ʏ����̌��x���Ԉ���������x�����Ԋm�ێ{�����A�����ԘJ�������Ɍ������J�g�s���v��̍���ɓw�߂�B�Ȃ��A���ׂẲ����g���́A����O�J�����Ԃ�N���L���x�Ɏ擾���ȂǁA�l�ʂ̘J�����Ԏ��тɂ��ăf�[�^�̊J�������߁A�������ƂɘJ�g�Ή����s���A�K�v�ɉ����ċƖ��ʂ̋ϕ�����l���z�u�̌������Ȃǂ����߂�B ���@�J�����ԊǗ��ɂ��ẮA�R���v���C�A���X�̊ϓ_�����܂��A�����J���ȁu�J�����Ԃ̓K���Ȕc���̂��߂Ɏg�p�҂��u���ׂ��[�u�Ɋւ���K�C�h���C���v�ɑ�������舵���ƂȂ�悤���g�ށB ②�@�N���L���x�ɂ̎擾����̎��g�� ���@�J���҂̐S�g�̌��N���m�ۂ���ϓ_����A�N���L���x�ɂ̎擾�ڕW���A�u�d�͑��A���Z�w�j�v�́u�N��10���ȏ�v���߂����B�Ƃ��ɁA�J����@�����ɂ�莖�Ǝ҂ɔN�x5���̎��G�w�茠���`���������\��ł��邱�Ƃ܂��A�擾������5�������̑g�������Ȃ����悤�A�v��擾��A���擾�ȂǁA���Ԃɉ��������x�������߂�B ���@�N���L���x�ɂ̊��S�擾���T�˂ł��Ă���g���́A���N�x�t�^������15���ȏ�Ƃ��邱�Ƃ�N��20���t�^�ƂȂ�܂ł̋Α��N���̒Z�k��v������B ���@�E��ɂ����āA�v��I�Ɍ�1���ȏ�͗L���x�ɂ̎擾���ł���悤�A�E����̐�����[�����Ȃǂ��s���B ③�@�N�ԏ���J�����ԒZ�k�̎��g�� ���@�N�ԏ���J�����Ԃ�2000���Ԃ��Ă�������g���́A�u�d�͑��A ���Z�w�j�v�Ɋ�Â��A�x�������𑝂₷�ȂǔN�ԏ���J�����Ԃ�2000���Ԉȉ��Ƃ���悤�v�����s���B ④�@����O�J�����Ԃ̍팸�Ȃǂ̎��g�� ���@����O�J�����Ԃ̍팸�Ɍ����A36����̒����ɂ��āA�ȉ��̓��e����{�Ɏ��g�݂�i�߂�B �E�@�x���J�����Ԃ��܂ގ��ԊO�J�����Ԃ́A1����45���Ԉȓ��A�N360���Ԉȓ��ɗ}���邱�Ƃ������Ƃ���B �E�@��ނ����ʏ������������ꍇ�ɂ����ẮA�x���J�����Ԃ��܂߂ĔN720���Ԉȓ��Ƃ��邱�Ƃ���{�Ƃ��A�����i1����45���Ԉȓ��A�N360���Ԉȓ��j�܂��A���}���I�Ȏ��ԂƂȂ�悤���g�ށB �E�@�x���J�����܂߂ĔN720���Ԃ�����Ȃ��ꍇ�ł����Ă��A�J����@�����ɂ�蓱�������\��̎��ԊO�J���̏�����ԁi1����100���ԁA2�����Ȃ���6��������80���ԁj�ɒ���t�����܂܂ƂȂ�ʂ悤�A�Ɩ��^�c��l���z�u�̌������Ɍ������J�g���c���s���A�x���J�����Ԃ��܂ߔN720���Ԉȓ��ɋ߂Â���ׂ��A�i�K�I�Ɉ����������s���B �E�@���ԊO�J���̌��x��K�p���O�Ɩ��i���ƁE�����ԉ^�]�Ɩ��Ȃǁj�ɂ����Ă��A���Ǝ�Ɠ��l�̏�����Ԃ�ݒ肷�邱�Ɠ�����{�Ɏ��g�݂�i�߂�B �E�@���ԊO�J�����Ԃ̐ώZ�́A����J�����Ԃ�����J�����ԂƂ���B ���@�ߏd�J���ɌW����t�̖ʒk�w���ɂ��ẮA��80���Ԃ߂����ґS���Ɏ��{���邱�Ƃ���{�ɁA��45���Ԓ��ߎ҂Ō��N�ւ̔z�����K�v�Ȏ҂ɂ��Ă��A���̑ΏۂƂ��邱�Ƃ����߂�B ���@����O�J�����ԍ팸�ɂ��ẮA�A���́u���Z���V�s�v��u�d�͑��A ���Z�w�j�v�Ȃǂ��Q�l�ɐE����Ԃɉ����Ď��g�݂����߂�i�莞�ގГ���v��N�x�擾���x�̎��g�݂Ȃǁj�B ���@�Ζ��ԃC���^�[�o���K���̓����ȂǁA�\���ȋx�����Ԃ̊m�ۂɌ����A�E����Ԃɉ������������̂��鐧�x�����������߂�B ⑤�@���ԊO�������̈����グ�Ȃǂ̎��g�� ���@1����60���Ԃ��鎞�ԊO�J���̊������ɂ��ẮA����̃_�u���X�^���_�[�h����������ϓ_����A�P�\�ΏۂƂȂ��Ă��钆����Ƃɂ��Ă�50���ȏ�̑��������Ɏ��g�ށB ���@�u���x������i�����Ԃ�1�����̏ꍇ��45���ԁj���鎞�ԊO�J���͖@�芄�������闦�Ƃ���悤�w�߂�v�Ƃ���K��Ɋ�Â��A�@��ɒ���t���Ă���ꍇ�͊�����30���ȏ�̗v�����s���B�܂��A�@����闦�ƂȂ��Ă���ꍇ�ɂ����Ă�30���ȏ�ƂȂ�悤���g�ށB ���@���ԊO�J���̐ώZ�͏���J�����Ԃ߂������̂Ƃ��A���ԊO�J���̐ώZ���@�ɂ��ẮA�����E�x���̋�ʂȂ����Z����悤���߂�B ���@��x�ɂ̓����ɂ������ẮA�J���Ή��͖{�������Ŏx�������Ƃ������ł���Ƃ̍l�����܂��A�����g���͌ʂɔ��f���邱�ƂƂ���B ���@�N���L���x�ɂ̎��ԒP�ʕt�^�̓����ɂ������ẮA�L���x�ɂ͖{��1�J������P�ʂƂ��Ď擾������̂Ƃ̍l�����܂��A�����g���͌ʂɔ��f����B�������A���x������ꍇ�ɂ́A���x�̉^�p��擾���т��m�F���Ȃ���������g�傷��ȂǁA�T�d�ɑΉ����s���B �i2�j�d���ƈ玙�E���E���Â̗����x���̎��g�� ①�@�����玙�E���x�Ɩ@�Ȃǂւ̑Ή� 2017�N1��1���{�s�́u�����玙�E���x�Ɩ@�v�ȂLj�A�̖@�����́A�j���Ƃ��Ɏq��Ă�������Ȃ��瓭�������邱�Ƃ��ł���A�Ɗ��̐�����ړI�Ƃ��A��Ƃ̋K�͂��킸�玙�E���x�Ƃ̐��x��������L���_��J���҂̋x�Ǝ擾�v���̊ɘa�A�n���X�����g�̖h�~�[�u�Ȃǂ̎��{���`���t������̂ł���B �܂��A���N10��1���{�s�̖@�����ł́A�ۈ珊�Ȃǂɓ����ł����ސE��]�V�Ȃ�����鎖�Ԃ�h�����߂ɍŒ�2�܂ň玙�x�Ƃ̍ĉ������\�Ƃ���Ȃǂ̌��������s��ꂽ�B �ߔN�̑��l�ȉƑ��`�ԁE�ٗp�`�ԂɑΉ����������x�����x����ɂ�闣�E�h�~�Ɍ��������x�̏[���ȂǁA�@�����̎�|�܂������g�݂�i�߂�B ���@�@�����܂������x�ƂȂ��Ă��邩�E��̒����E�_�����s���ƂƂ��ɁA���x��|����e�̐E����m��}��Ȃǂ̘J�g�Ή����s���B ���@�D�P�E�o�Y�E�玙�x�ƁE���x�ƂȂǂ𗝗R�Ƃ�����i�⓯���ɂ��n���X�����g�h�~�[�u�����߂�ƂƂ��ɁA�h���J���҂Ɋւ��ẮA�h���������ł͂Ȃ��h����ɂ����l�̑[�u��s���v�戵���̋֎~�K�肪�K�p����邱�Ƃ���A�E����̉��P�Ɍ������J�g�Ή����s���B ②�@�d���ƈ玙�E���E���Â̗����x�����x�̐����E�g�[ �l�ނ̈ێ��E�m�ۂ��d�v�ۑ�ƂȂ�Ȃ��A�M�d�ȋZ�p�E�Z�\��L����l�ނ��玙�E���E�a�C���Â𗝗R�ɗ��E���邱�Ƃ�h���A�d���Ɖƒ�ɂ���������𗼗����Ȃ��瓭�������邱�Ƃ̂ł���E��̎����Ɍ����A�u�d�͑��A �d���Ǝ������̒��a�v�̍l�����܂��A���C�t�C�x���g�ɉ������_��ȓ��������ł���悤�A���̓��e����{�Ɋ�������i�߂�B ���@�玙�x�Ƃ��擾�ł���q�̔N��ɂ��āA�@�ɂ����Ă͌���1�܂Łi�ۈ珊�ɓ����ł��Ȃ��ꍇ�͍Œ�2�܂ʼn����\�j�ƂȂ��Ă��邪�A��]���鎞�ɕۈ珊�ɓ����ł��Ȃ����Ԃ��������Ƃ�ۈ珊�Ȃǂ̓������������4���Ƃ������Ƃ܂��A3�̔N�x�����߂����B�܂��A�E��̃j�[�Y��n�掖��ɉ����āA�O���[�v��ƂƂ̋����ݒu������ɁA���Ə����������̐ݒu�Ɍ������g�ށB ���@�玙�ɂ��Z���ԋΖ����x�ɂ��ẮA���A�w�����i���w�Z�A�w�O�j�܂ł�ΏۂƂ��A���ɖ��A�w������ΏۂƂ��Ă���ꍇ�́A���ی㎙���N���u�̑ҋ@��������A���Z���̈��S�m�ۂȂǂɊӂ݁A�ΏۂƂ���N��̊g����߂����B ���@2017�N10��1���{�s�̉����玙�E���x�Ɩ@�œw�͋`�������ꂽ�u�玙�ړI�x�Ɂi�z��ҏo�Y�x�ɁA�q�̍s���Q���̂��߂̋x�ɓ��j�v�̓����ɓw�߂�B ���@���x�Ƃ́A�����Ԃ̌��ɂ߂�����Ȃ��Ƃ�K�v�Ƃ������Ԃ��l�ɂ���ĈقȂ邱�Ƃ���A�@��̉��x�Ɗ��ԁi�ʎZ93���j����������̕t�^��@��i3��j�ȏ�̕����擾���\�Ƃ���_��Ȑ��x�\�z���߂����ƂƂ��ɁA�@��̉��x�Ɂi�Ώ�1�l������5���j�ȏ�̓����t�^�⎞�ԒP�ʂł̎擾�A�Z���ԋΖ���t���b�N�X�^�C�����x�ȂǁA�_��ȓ��������ł���悤�E����Ԃɍ��킹���J�g�Ή����s���B ���@�����ɂ킽�鎡�Â��K�v�Ȏ��a�������J���҂��A���a�ɑ���E��̗���s���E�x���s���ɂ���ė��E������A�Ɩ��ɂ���Ď��a�������邱�ƂȂ��A�K�Ȏ��Â��Ȃ��瓭����������悤�A�A�Əꏊ�ύX�A��Ɠ]���A�J�����ԒZ�k�Ȃǂ̔z����u�����x���v�����v�̍���A���ԒP�ʋx�ɂ�Z���ԋΖ����x�̏[���ȂǁA�ΏێҌX�l�̏ɉ������Ή����\�ƂȂ�悤���g�ށB ���@�x�Ɓi�x�E�j�҂̐E�ꕜ�A�Ɍ����A�u�E�ꕜ�A�x���v�����v�̍���⎎���o�А��x�Ȃǂ̏[���Ɏ��g�ށB�܂��A�����^���w���X�ɂ��x�E�҂����E�Ƌx�Ƃ��J��Ԃ��ꍇ�ɂ����ẮA��Ë@�ւɂ�镜�E�x���v���O�����i�����[�N�v���O�����j�����p����ȂǁA�x����g�[�Ɍ������g�ށB ���@���x���p�҂̐E�ꕜ�A��̎x������⌇�����̐E��Ή����[���̊m���Ɍ����Ď��g�ނƂƂ��ɁA��ނȂ�����ɂ�藣�E������Ȃ��ƂȂ����ꍇ�̍ďA�E�E�Čٗp���x�����Ȃǐ��x�[���Ɍ����Ď��g�ށB ���@�玙�E���݂̂Ȃ炸�P�g���C�Ҏx���ȂǁA�ƒ����n��Љ�ɂ�����Ƒ��I�ӔC���ʂ����Ȃ��瓭�������邱�Ƃ��ł���������Ɍ����āA���ԒP�ʂł̋x�Ɏ擾��t���b�N�X�^�C�����x�̓����ȂǁA�E����Ԃɍ��킹�����g�݂��s���B ���@�����x�����x�̗��p���i�̂��߂ɂ́A���x�̏[���ɉ����ė��p���₷�����Â��肪�s���Ȃ��Ƃ���A�E����Ԃ�c�����������ŁA�K�v�ɉ����ĘJ�g���c���s���ƂƂ��ɁA�����g���͈玙�E���E���ÂƎd���̗����Ɋւ��鑊�k�@�\�̋����ɓw�߂�B ���@������琬�x�������i�@�̎�|�Ɋ�Â��A�s���v��̎��{�̃t�H���[��A�s���v��̍X�V�̎��g�݂��s���B�Ȃ��A�`�����̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ�100���ȉ��̑g���ɂ����Ă��A������琬�̊ϓ_����A�E��܂����J�g�Ή����s���B ���@������琬�x�������i�@�Ɋ�Â��s���v��ɒ�߂��ڕW��B�����A���̊�������u�q��ăT�|�[�g��Ɓv�������J����b���F�肷��u����݂�E�v���`�i����݂�v���x�ɂ��ẮA�����₷���J����������Ƃ����ϓ_�ɉ����A�l�ނ̊m�ۂ�������B�ɂ�������_�]���Ȃǂ̗D���[�u�����邱�Ƃ����܂��A�F��擾�Ɍ��������g�݂�ʂ��Ă���Ȃ��������i�߂�B �@5�D�N�������S�ł���J��������J�����̊m�� �i1�j���N��Ҍٗp�ւ̑Ή� 2013�N4��1���{�s�̉������N��Ҍٗp����@�̎�|�Ɋ�Â��A���N��҂̊��͍��g�ɂȂ���悤�A�ȉ��̓��e����{�Ɏ��g�ށB ���@�p���ٗp���x�����A�J�g����ɂ��Ώێ҂̊��݂��Ă���ꍇ�́A��]�ґS����ΏۂɁA65�܂ł̌p���ٗp�Ƃ���J������̒������s���B ���@����܂łɔ|�����o���Ɋ�Â��Z�p�E�Z�\���������A��肪���E���������������āA��Ƃ̔��W�ɐϋɓI�ɍv���ł���悤�A�J�������̐����⑽�l�ȓ������Ɍ������J�g�Ή����s���B�Ƃ�킯�A���������ɂ��ẮA�J���̉��l��v���ɂӂ��킵���A���A���N����ɂ�����Љ���̊m�ۂ��߂��������g�݂�}��B ���@���N��҂̏A�Əꏊ���m�ۂ��邽�߁A�����₷���E��̑n�o�A��Ɗ��A�\�͊J���A���N�Ǘ��ȂǁA���N��҂̈ӗ~�ɂȂ���A�Ɗ��̐����Ɍ������J�g�Ή����s���ƂƂ��ɁA�g�D���Ɍ����Ď��g�ށB �i2�j�����������i�@�Ɋ�Â����g�� 2016�N4��1���{�s�̏����������i�@��A���u��4���j�������Q�搄�i�v��v����ѓd�͑��A�u�j�������Q��Љ�̎����Ɍ��������g�݁v�܂��A�ȉ��̓��e����{�Ɏ��g�ށB ���@�����̊������i�Ɍ����A�E����Ԃ�ۑ�̔c�����s���A�s���v��ɔ��f����悤�J�g�Ή����s���B�Ȃ��A�`�����̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ�300���ȉ��̑g���ɂ����Ă��A�@�̎�|�܂��A���l�Ȏ戵���ƂȂ�悤���g�ށB ���@�t�G���������̎��g�݂�ʂ��āA�E��j�[�Y��ۑ�Ȃǂ̔c���ɓw�߂�ƂƂ��ɁA�K�J���҂ɂ����Ă����l�Ȏ戵���ƂȂ�悤���g�ށB ���@�����̊������i�Ɋւ�����g�݂̎��{�Ȃǂ��D�ꂽ��Ƃ������J����b���F�肷��u����ڂ��v���x�ɂ��ẮA�N���������₷���J����������Ƃ����ϓ_�ɉ����A�l�ނ̊m�ۂ�������B�ɂ�������_�]���Ȃǂ̗D���[�u�����邱�Ƃ܂��A�F��擾�Ɍ��������g�݂�ʂ��Ă���Ȃ��������i�߂�B �i3�j�Ⴊ���҂ւ̑Ή� �Ⴊ���҂��������ʂɎЉ�̈���Ƃ��ċ��ɐ����ł���u�����Љ�v�����������������i���邱�Ƃ�ړI�Ƃ����Q�Ҍٗp���i�@�ł́A��W�E�̗p�A�����A�z�u�A���i���͂��߂Ƃ��邠�����ʂɂ����āA�Ⴊ���҂ł��邱�Ƃ𗝗R�Ƃ��鍷�ʂ��֎~����ƂƂ��ɁA�����I�Ȕz���̎��{���`��������Ă���B�_�C�o�[�V�e�B�i���l���j�d�����E����̎����Ɍ����A�Ⴊ���҂ɑ��鍷�ʂ��Ȃ����A�����₷�����ւ̔z�����\���ɂȂ���Ă��邩�E����Ԃ̔c���ɓw�߂�ƂƂ��ɁA�K�v�ɉ����ĐE����̉��P�Ɏ��g�ށB �i4�j�ސE�ꎞ�����x�̊m���E�����̎��g�� ���I�N���̎x���J�n�N��̈����グ��A�}�N���o�σX���C�h�ɂ���Č��I�N���̐������}�������X���ɂ���Ȃ��A���S�����V����߂������߂̑ސE�ꎞ���̉ʂ��������͂��傫���Ȃ��Ă���B���̂��߁A�ސE�ꎞ�����x���m������Ă��Ȃ������g���́A������ƑސE���ϐ��x�����p����ȂǁA�����m�����߂��������g�݂�i�߂�B�܂��A���x���m������Ă�������g���́A�d�͑��A�̃N���A�����ł���1,550���~�ȏ�̊m�ۂ��߂����B �i5�j�ЊQ�⏞���x�̏[���̎��g�� �d�͊֘A�Y�Ƃ̎Љ�I�g�����ʂ����d�ӂ�S���]���ƂȂ����g�����̋Ɩ���ЊQ�⏞���x�́A�l���Ƃ��������̂ɂ��ウ���������l�ւ̕⏞�Ƃ����J�g���ʂ̗��O�������āA���x���m������Ă��Ȃ��P�g�ɂ��ẮA���x���Ɍ������d�_�I�Ȏ��g�݂��s���B�܂��A�m������Ă���ꍇ���A���ׂẲ����g���œd�͑��A�̃N���A����3,500���~�ȏ�i�Ɩ��㎀�S�E�L�}�{�ҁj�̕⏞�z���߂����B �i6�j�X�g���X�`�F�b�N���x�̊��p�ɂ��� 2015�N12��1���{�s�̉����J�����S�q���@�̎�|�Ɋ�Â��A�ȉ��̓��e����{�ɂ��ꂼ��̐E��ɂ����ĘJ�g��̂ƂȂ������g�݂�i�߂�B ���@�J�g�ψ���E���S�q���ψ���Ȃǂ�ʂ����J�g�Ή����s���A�Ώێ҂̎��E�ʒk���{���̌����A���x�̏[���Ɍ����Ď��g�ނƂƂ��ɁA�h���J���҂ɑ���X�g���X�`�F�b�N�̎��{�ɂ��Ă��m�F���s���B���킹�āA�X�g���X�`�F�b�N�̏d�v���ɂ��ĐE��g�����ɍēx���m���s���B ���@�`�����̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ�50�������̎��Ə�ɂ����Ă��A�����^���w���X�s���̖��R�h�~�̊ϓ_����A���{�Ɍ������J�g�Ή����s���B ���@�X�g���X�`�F�b�N�̌��ʂɂ��ẮA�l�����肳��Ȃ��悤�v���C�o�V�[�ی��O��Ƃ��A�J�g�ψ���E���S�q���ψ���Ȃǂɂ����ďW�c���͂��s���A�J�g�ŐE����̉��P�ɂȂ���悤���g�ށB 6�D�K�J���҂̑ҋ����P�̎��g�� �K�J���҂̒����E�J�������́u��グ�E��x���v���Љ�I�ɋ��߂��Ă���Ȃ��A�d�͑��A�ɂ����Ă��A�K�J���҂̑ҋ����P�͓d�͊֘A�Y�Ƃœ����ґS�̂̒�グ��}�邱�ƂɂȂ���Ƃ̍l���̂��ƁA�u�d�͑��A
�p�[�g�^�C���J���ғ��̋ϓ��ҋ��ɂނ������g�ݎw�j�v�Ɋ�Â������g�݂�i�߂Ă���B �i1�j�p�[�g�^�C���J���ҁE�L���J���_��҂Ȃǂ̑ҋ����P�̎��g�� ���@�e��Ƃ��ٗp���Ă���p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂Ȃǂɂ��āA�J�������Ȃǂ̎��Ԕc���A�j�[�Y��c�����邽�߂̑Θb�����Ȃǂ����{���A���Y�҂���јJ�g�̎O�҂ŋ��ʔF����}��A�J����������Ƒg�D���Ɍ��������g�݂ɂȂ���B ���@�g�D���Ɍ����ẮA2013�N4��1���{�s�̉����J���_��@�ɂ��A�L���_��J���҂ɑ��閳���]�����[���K�p��2018�N4��1������J�n����邱�Ƃ��D�@�ƂƂ炦���g�݂̉������ɂȂ���B ���@���Ј��Ɠ������ׂ��p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂Ȃǂ̐��Ј����܂��͐��Ј��Ɍ��������[�������s���B ���@���Ј��Ɠ������ׂ��p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂Ȃǂɂ��ẮA���Ј��Ƃ̋ϓ��ҋ��Ɍ����Ď��g�ށB ���@���Ј��ƈقȂ铭���������Ă���p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂Ȃǂɂ��Ă��A�E�����e��J�����ԂȂǂ����Ă��A�������[���̖��m���A�ꎞ���̎x���A�ʋΔ�̎x���A�c���x�ɂȂǂ̐����A���̑������������x�Ȃǂɂ��āA���Ј��Ƃ̋ϓ��E�ύt�ҋ��Ɍ����Ď��g�ށB ���@2018�N4������5�N���Ĕ����X�V�����L���_��J���҂ɑ��閳���]�������������邱�Ƃ܂��A�L���_��J���҂̎��Ԃ�c�����������ŁA���Ј��]�����܂ޖ����]���Ɋւ��郋�[�������m���ɍs���B ���@�p�[�g�^�C���J���ҁE�L���_��J���҂������_��J���҂֓]�������ۂ̘J�������ɂ��ẮA���Ј��Ƃ̋ϓ��E�ύt���l�����A�������ɑ������������ƂȂ�悤�J�g�Ή����s���B ���@���������グ�ɂ��ẮA�Œ��������z���l����960�~���߂����A�E�����e�A�_����Ԃ̎��ԂȂǂ܂����v���܂��͗v�����s���B�Ȃ��A960�~���Ă���ꍇ�́A���N�x�̒n��ʍŒ���������グ�z�i����25�~�j�Ȃǂ܂����v���܂��͗v�����s���B �i2�j�h���J���҂̎��g�� 2015�N9��30���{�s�̉����J���Ҕh���@�̎�|�܂��A�h���J���҂̂�肢�������̌ٗp�̈����L�����A�A�b�v��}�邱�Ƃ��ł���悤�A�ȉ��̓��e����{�Ɏ��g�ށB ���@�����E��œ����h���J���҂ɂ��āA�Ɩ����e�A����K�́A�_����ԁA�A�J�ꏊ�A�_������A�_���Ж���Ώۂɏ��J�������߂�ȂǁA���Ԕc�����s���B ���@���ꎖ�Ə���3�N���Ď����ۂ̘J���g���ɑ���ӌ�����ɂ����ẮA�v���Ɋւ��鎖����ٗp�������ԂȂǂɂ��āA�J�g�Ή����s���B ���@�h����ɉۂ���ꂽ�ٗp����[�u��ϓ��E�ύt�ҋ��A�ق�����w�͋`���Ȃǂ̎��{�ɂ��Ă��K�X�����߂�B ���@�h���J���҂ɑ��A�h����̕�W���̎��m���K�Ɏ��{����Ă��邩�K�X�����߂�B 7�D�������x�v���ւ̎��g�� �A���͐���E���x�����̎��g�݂��t�G���������ƂƂ��ɂ��ׂĂ̓����҂̒�グ�E��x���A�i�������Ɍ������^���̗��ւƂ��Đ����i�߂�Ƃ��Ă��邱�Ƃ���A�A���̒��j�Y�ʂƂ��Ă̖����ƐӔC���ʂ������߁A�ϋɓI�ɎQ�悵�Ă����B 8�D�����g���̌����i�����ւ̎��g�� �����g���̌ٗp����A����������J�������̈ێ������}�邽�߁A�d�͑��A�E�\�����A�́A�����g���̗v���č���̒i�K����A���A�g�𖧂ɂ��A�x�����s���ƂƂ��ɁA����W�̓K�����Ɍ����A���̍l�����Ɋ�Â��Ď��g�݂���������B ���@���Ђ̌o�c���܂����A���Y�J�g�̐^���Ș_�c�ɂ���̓I�ȉ������}���悤�x�����s���B�܂��A���������Ƃ��āA����W�����Y�J�g�����ɂ��t�����Ɉ��e�����y�ڂ����Ƃ��Ȃ��悤�A�\�����v�����s���ƂƂ��ɁA�O���[�v��Ɠ��ɂ�����K���ȉ��i�]�łƌ�������̐��i�ɂ��Ă��A�e�\�����A�ŊJ�Â����J�g���k���ʃI���O�Ȃǂ����p�������g�݂�}��B ���@�J�����_�������̌��ʁA�J������Ȃǂɉ��P�E�[�����K�v�ȉ����g����������Ԕc���������{�A�d�͑��A�~�j�}�������ɖ��B�A�����J�[�u�ێ������m�ۂł��Ă��Ȃ��Ȃǂ̉����g���ƘA�g���������A�����g���̎��Ԃɂ��������g�݂ɂ��ďd�_�I�Ȏx�����s���B ���@�Ǝ�ʕ���Ƃ̒����J�[�u�ێ����̈ꕔ�Ƃ��āA��������������̏��J���������g���̗v���č���O�ɍs���A�d�͑��A���̑���`���ɓw�߂�B�Ȃ��A���̑��̉����g���ɂ����Ă��A�\�����A���ɑ��ď��J���ɓw�߂�B VII�D�i�ߕ�
�A��2018�t�G���������̐i�ߕ��܂��������ŁA�d�͑��A�E�\�����A�E����E�����g���̘A�g���\���ɐ}��Ȃ���d�͑��A�̑��͂����W���Ď��g�ނ��ƂƂ���B�܂��A�A���̊e�틤���ƘA�g��}��Ȃ���A�L�������Ɍ����Ď��g�ށB 1�D�v�����̒�o �v�����̒�o�ɂ��ẮA����30�N2��20���i�j��v�����Ƃ��āA��ĂɎ��{����B�������A����ɂ���ėv���ւ̑Ή�����������g���́A�x���Ƃ�3�����܂łɗv������B 2�D�����i�̐� �i1�j���̐� ���@�d�͑��A�́A���������i�ψ����ݒu���A�\�����A�E�����g���̌����i�Ɍ����ĐϋɓI�Ɏx���E�������s���B ���@�\�����A����ѕ���́A�����i�ψ����ݒu���Ċe�X�̐ӔC�̐����m�����A�����g���̑������L���ȉ����Ɍ����ĐϋɓI�Ɏx���E�������s���B ���@�����g���́A�\�����A�╔��ƘA�g��}��A�����E��������{�ɐ��͓I�Ɍ���W�J����B �i2�j���̑��i ���@���������i�ψ���́A���܂������g���̌���L���ɓW�J���邽�߁A�u�����̐i�ߕ��v�M����B�����āA�A���������������M������j�ɂ��āA�d�͑��A���̎��Ԃ����܂��������ŁA�����g���̒������グ�����L���ɐi�߂���悤���l�ɔ��M����B ���@�\�����A����ѕ���́A�����g���̌����i��}�邽�߁A������]�[����݂���̂ƂȂ�������W�J����B���ɍ\�����A�́A�����g���̌����i�Ɍ����Ďx������������B ���@�t�G���������ɌW�����́A���𑣐i���邽�ߓK�X���M���Ă����B 3�D�������� ���̃��}��́A�A���̉������i�]�[���܂��ݒ肷�邱�ƂƂ��A�x���Ƃ�4�����܂ł̉������߂����B �ȏ�
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| �S���d�͊֘A�Y�ƘJ���g�����A���z�[���y�[�W�Ɍf�ڂ��ꂽ�摜���̑��̓��e�̖��f�]�ڂ͂��f��v���܂��B Copyright(C) 2004 The Federation of Electric Power Related Industry Worker's Unions of Japan all rightreserved. |